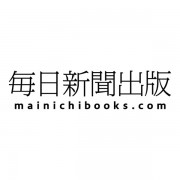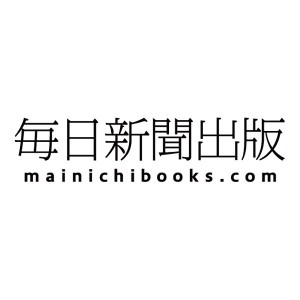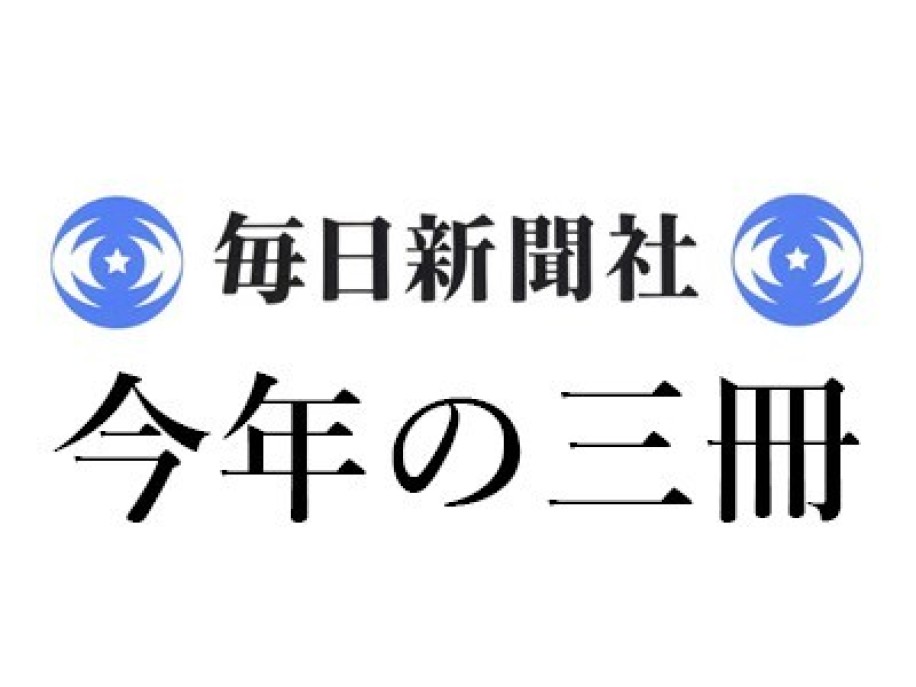本文抜粋
『清六の戦争 ある従軍記者の軌跡』(毎日新聞出版)
太平洋戦争末期、爆撃下の洞窟で新聞を作り続けた記者がいた。毎日新聞の伊藤清六(1907~1945)だ。死と隣り合わせの兵士たちがむさぼるように読んだという、ガリ版刷りの新聞「神州毎日」。壕の中でペンを走らせたとき、彼は何を思い、何を願ったのか。その時、新聞は何を伝え、何を伝えなかったのか。時が流れて75年後、自らも記者となった著者が、祖先の足跡をたどる旅に出る――
2020年7月~8月に毎日新聞に掲載され、第26回平和・協同ジャーナリスト基金賞・奨励賞と第15回疋田桂一郎賞を受賞した連載、待望の書籍化。
初めて見るその人は、穏やかな表情の中にも、意志の強さをたたえた目をしていた。
2012年、私は、東京・竹橋の毎日新聞東京本社で色あせた一枚の写真に出会った。若いころの父や、かすかな記憶に残る親戚たちに似た顔立ちに、懐かしささえ感じた。それが、私の曽祖父の弟、伊藤清六だった。
写真は、私が見つけるのを長い間待っていたように思えた。
清六の存在を初めて知ったのは、私の毎日新聞入社が決まった2004年のことだ。父が「昔、毎日新聞にいて、フィリピンで戦死した親戚がいる」と教えてくれた。
新聞社といっても、仕事は幅広い。現在でも「新聞社は仕事のデパート」と言われるほど多種多様な仕事がある。記者のほかに編集や校閲、営業や販売、広告、文化事業などがあり、加えて戦前は、活版工や印刷工も多くいた。所属の部署によって仕事の内容はまるで違う。このときはまだ、清六が記者だったのかさえわからなかった。父も、詳しいことは知らないという。
また、「フィリピンで戦死した」というのも、当然のように「兵士として出征したのだろう」と思っていた。清六は、私にとってまだ遠い存在で、想像することも難しかった。
2005年に入社し、仙台支局に配属されてからは、警察取材やスポーツ取材などに明け暮れた。清六のことを調べる余裕も、術もなかった。
父から「清六さんの息子さんが仙台に住んでいるらしいから会いに行ってみよう」と誘われていたが、日々の忙しさに追われているうちにその方の訃報が届き、ますますその存在は遠のいてしまった。
2011年、私は東京本社の資料を管理する情報調査部に配属された。資料整理を兼ねて社の古い資料がどう保管されているか、宝物を探すような気持ちで倉庫の棚や箱をのぞいているうち、ふと、父の話を思い出したのだ。
写真は情報調査部の、社員の顔写真を収めたキャビネットにあった。あいうえお順に、過去に在籍した社員の顔写真が並んでいる。「い」の引き出しをたどっていくと、「本社員 伊藤清六」とある写真を見つけた。70年近くも前に亡くなった親戚の写真が、こんなにも身近に眠っていたことが不思議に思えた。
ほかに手がかりはないかと、記録や書籍を眺める日々が続いたが、結果は思わしくなかった。
ところがある日、ジャーナリズム関係の本が並んだ書棚に、ぼろぼろになった本を見つけた。それは、1952年に毎日新聞社が出版した物故社員の追悼冊子だった。ページをめくると、「伊藤清六」の名前があった。私は、その人生に一気に引き込まれた。
清六は戦前に農政記者として働いていたが、戦争末期の1944年、毎日新聞社がフィリピンで経営していた「マニラ新聞」に取材部長として出向し、戦局が悪化するとルソン島の山中で日本兵のために陣中新聞を作っていた。最期は、多くの仲間とともに山中をさまよい、餓死するという悲惨な結末だった。戦時中にフィリピンで死亡した毎日新聞の関係者は56人。死亡時の詳細が不明な人も多いという。
清六の人生の輪郭が見えると、私は手当たり次第に戦時中のフィリピンに関連する資料や書籍を読みあさった。公的な戦争記録『戦史叢書』はもちろん、フィリピン戦の戦史、清六と同時期にフィリピンにいた人たちの回想記など、数多くの本が出版されていた。同時に、社内に残る社報や人事記録、OB会誌なども調べた。新聞などのメディアが戦争にどう関わっていたのかを分析した研究書にも目を通した。
日本の新聞社が占領地で経営した新聞社の取材部門の責任者となれば、戦争と新聞の関係を考えるうえで、重要な存在だ。「身内のことを知りたい」という好奇心から始まった調査は、少しずつ「戦時中の新聞記者は何をしたのか」というテーマに形を変えていった。
[書き手]伊藤絵理子
2020年7月~8月に毎日新聞に掲載され、第26回平和・協同ジャーナリスト基金賞・奨励賞と第15回疋田桂一郎賞を受賞した連載、待望の書籍化。
初めて見るその人は、穏やかな表情の中にも、意志の強さをたたえた目をしていた。
2012年、私は、東京・竹橋の毎日新聞東京本社で色あせた一枚の写真に出会った。若いころの父や、かすかな記憶に残る親戚たちに似た顔立ちに、懐かしささえ感じた。それが、私の曽祖父の弟、伊藤清六だった。
写真は、私が見つけるのを長い間待っていたように思えた。
清六の存在を初めて知ったのは、私の毎日新聞入社が決まった2004年のことだ。父が「昔、毎日新聞にいて、フィリピンで戦死した親戚がいる」と教えてくれた。
新聞社といっても、仕事は幅広い。現在でも「新聞社は仕事のデパート」と言われるほど多種多様な仕事がある。記者のほかに編集や校閲、営業や販売、広告、文化事業などがあり、加えて戦前は、活版工や印刷工も多くいた。所属の部署によって仕事の内容はまるで違う。このときはまだ、清六が記者だったのかさえわからなかった。父も、詳しいことは知らないという。
また、「フィリピンで戦死した」というのも、当然のように「兵士として出征したのだろう」と思っていた。清六は、私にとってまだ遠い存在で、想像することも難しかった。
2005年に入社し、仙台支局に配属されてからは、警察取材やスポーツ取材などに明け暮れた。清六のことを調べる余裕も、術もなかった。
父から「清六さんの息子さんが仙台に住んでいるらしいから会いに行ってみよう」と誘われていたが、日々の忙しさに追われているうちにその方の訃報が届き、ますますその存在は遠のいてしまった。
2011年、私は東京本社の資料を管理する情報調査部に配属された。資料整理を兼ねて社の古い資料がどう保管されているか、宝物を探すような気持ちで倉庫の棚や箱をのぞいているうち、ふと、父の話を思い出したのだ。
写真は情報調査部の、社員の顔写真を収めたキャビネットにあった。あいうえお順に、過去に在籍した社員の顔写真が並んでいる。「い」の引き出しをたどっていくと、「本社員 伊藤清六」とある写真を見つけた。70年近くも前に亡くなった親戚の写真が、こんなにも身近に眠っていたことが不思議に思えた。
ほかに手がかりはないかと、記録や書籍を眺める日々が続いたが、結果は思わしくなかった。
ところがある日、ジャーナリズム関係の本が並んだ書棚に、ぼろぼろになった本を見つけた。それは、1952年に毎日新聞社が出版した物故社員の追悼冊子だった。ページをめくると、「伊藤清六」の名前があった。私は、その人生に一気に引き込まれた。
清六は戦前に農政記者として働いていたが、戦争末期の1944年、毎日新聞社がフィリピンで経営していた「マニラ新聞」に取材部長として出向し、戦局が悪化するとルソン島の山中で日本兵のために陣中新聞を作っていた。最期は、多くの仲間とともに山中をさまよい、餓死するという悲惨な結末だった。戦時中にフィリピンで死亡した毎日新聞の関係者は56人。死亡時の詳細が不明な人も多いという。
清六の人生の輪郭が見えると、私は手当たり次第に戦時中のフィリピンに関連する資料や書籍を読みあさった。公的な戦争記録『戦史叢書』はもちろん、フィリピン戦の戦史、清六と同時期にフィリピンにいた人たちの回想記など、数多くの本が出版されていた。同時に、社内に残る社報や人事記録、OB会誌なども調べた。新聞などのメディアが戦争にどう関わっていたのかを分析した研究書にも目を通した。
日本の新聞社が占領地で経営した新聞社の取材部門の責任者となれば、戦争と新聞の関係を考えるうえで、重要な存在だ。「身内のことを知りたい」という好奇心から始まった調査は、少しずつ「戦時中の新聞記者は何をしたのか」というテーマに形を変えていった。
[書き手]伊藤絵理子
ALL REVIEWSをフォローする