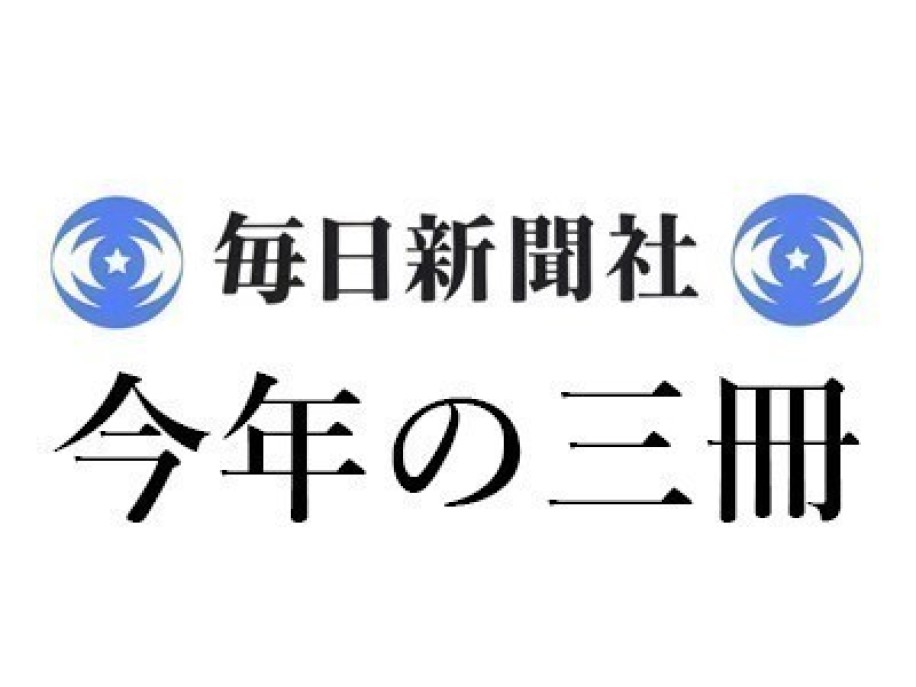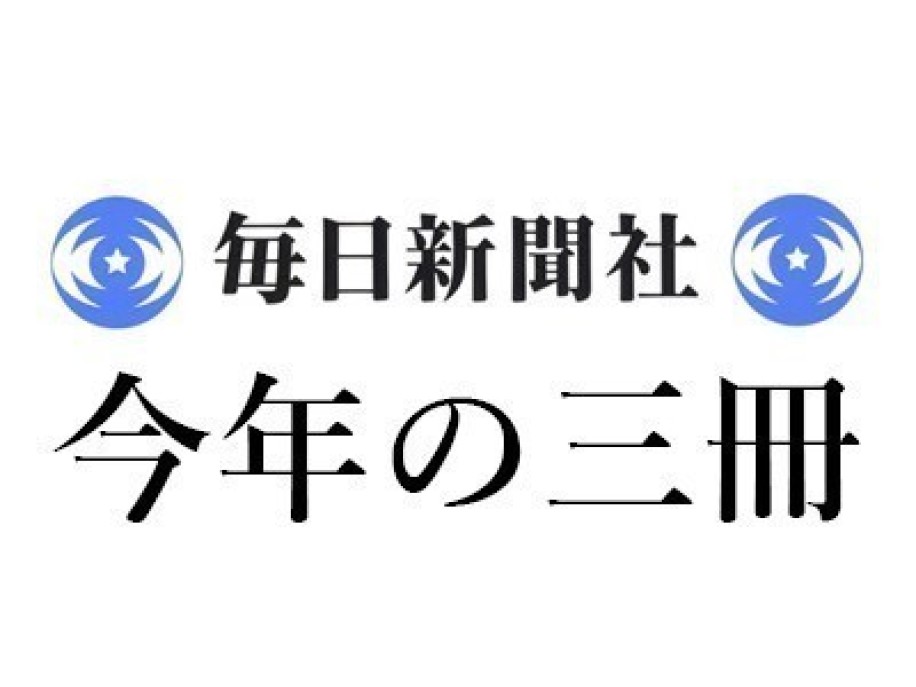書評
『紬の里』(新潮社)
もうひとつの『雪国』
かつての流行作家、立原正秋の『紬の里』を読む。三十五年前に書かれたなつかしい日本の雪の物語だ(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1996年頃)。舞台は雪深い越後。織物の町・塩沢で、母と娘を抱えて機織りにいそしむ三十一歳の寡婦・志保子の前に、ある初雪の日、東京の美術大学の教師・高階が現れ、志保子の胸に火をともしてゆく。それから毎年、雪が降りだすと高階はやってきて、二人は四度目の冬に結ばれる。
逢う瀬が重ねられ、志保子の思いは一途に高階にむけられる。高階の思いも深まるばかりだが、雪国そのものになのか、雪に埋もれて機を織る女になのか、しかとは定められない。そんな彼の前にもう一人の雪国の女、若い芸者・織江が現れる。
高階は雪国に移り住むことになるが、彼が居ついた湯沢の常宿で重ねられる逢う瀬は、しだいに不穏になってゆく。彼は織江ともぬきさしならなくなってゆくのだ。
高階は男の身勝手という以上のどうしようもない性(さが)のままに、志保子を追いつめる。志保子は嫉妬に苦しみながらも、深まる一方の交情に「ゆきまどい」、「ゆきくれる」。二人の深い嘆きは、あくまでも沈着なひんやりとした語り口に支えられて、それだけよけい読者に痛切にひびく。志保子の情念のなまなましさなど、かえって清流の底の小石のようにあらわにみえて、どきりとさせられる。
こらえにこらえていた志保子はラストで燃えあがる。織江の家に居つづけになっている高階を迎えにいった志保子は、「宿でお待ちしております」といって離れにひき返し、窓ぎわに座って待つ。暗くなっても高階は来ない。目の前の雪山と対面しているうちに志保子の胸に「あかい火」がともる。
志保子は火が大きくならないようにと気持を鎮めてみたが、気がついたときには炎(ほむら)は途方もない大きさで拡がり、雪山が全山朱に染まって燃えていた。ああ、わたしはここで死ぬかもしれない! 志保子は燃えている雪山を視つめて声をあげた。
まるで雪女が正体をあらわしたようなこの姿を描くために、作者はこれまで沈着に振るまっていたのでは、と思えるほどの見事な終わり方だ。志保子が滅びようとしているのに高階は来ない。宙ぶらりんのまま終えるのも、作者の深謀ではないか。
こんなふうにも読める。そもそも彼は、小説の外からのように雪国にいる志保子の前に現れた。それは、「雪だわ」といって窓をあけるとそこに高階が立っていた、という冒頭の書きぶりからも明らかだ。そして、ラストでは、高階はこっそり小説の中から抜けだし、冒頭にむかっている。志保子を滅ぼさないためには、もう一度初めからはじめるしかないとでもいうように。
雪山に対座したまま燃えつきようとする志保子を救うために、律儀に大急ぎに雪国のとば口にとって返す高階の姿なんて、小説のヒーローとしてはなかなかのものだ。
作者の工夫は他にもある。「ゆく」という使用頻度の格別に高い語に、「雪」が隠されている。それに気がついて、目をこらすと、どのページにもしんしんと雪が降っている。志保子の姿を追いながら僕はしきりに、川端康成の『雪国』の駒子のセリフ、「ほんとうに人を好きになれるのはもう女だけ」を思い出していた。『紬の里』にはたしかに『雪国』が透けてみえる。
この三十五年のあいだに東京も激変したし湯沢も変わった。だが日本列島には雪が降りつづける。第三の『雪国』がそろそろ書かれていいころだが、さてどんな仕立てになるか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする