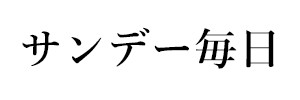書評
『おまんが紅,接木の台,雪女』(講談社)
素直に読ませるという技巧
てっきり女性と思い込んでいた作家がふたりいる。ひとりは近松秋江(しゅうこう)。これを僕は近松秋江(あきえ)と読んで、大正の女流作家だろうと思っていた。近松秋江。大正期花柳小説の傑作『黒髪』の作者で、僕は、むかし秋江(あきえ)と読んだ罪ほろぼしというわけでもないが、昨年、秋江自身も作中人物として登場する、その名も『黒髪』という小説を書いた。
もうひとりは和田芳恵(よしえ)。もちろん、女流だと思い込んでいたのは作品を読まないうちの話で、読めば作者が男か女かぐらいたちどころにわかる。
老境の〈私〉とはたちを過ぎたばかりの女性速記者・悠子との秘かな情事を描いた「接木(つぎき)の台」は和田芳恵の代表作とされている。
私が、すぱっと根元から斬りたおされ、その樹皮へ悠子の小さな枝を接木して、幻の花を咲かせるつもりだった。(「接木の台」)
和田は明治三十九年の生まれで、坂口安吾と同年だ。デビューも早く、昭和十年代だが、作家生活の前半は恵まれず、生活も苦しかった。昭和三十八年、『塵の中』で直木賞を受賞したが、それでも売れる作家とはならなかった。珍しい。
ところが、昭和四十九年(一九七四年)、六十八歳のとき発表したわずか二十五枚の短篇「接木の台」が圧倒的な評価を受け、その年の読売文学賞に輝いた。
和田は自らを「七十にして、新人」と呼んだが、その七十歳で亡くなった。「接木の台」を発表してから亡くなるまでのわずかの間に、まるで火山が噴火するように、「抱寝」「囃し詞」「母の寝言」「老木の花」などの傑作短篇、それに自伝的長篇小説『暗い流れ』が書かれた。『暗い流れ』は、作者がみずからを皮はぎしてみせた『ヰタ・セクスアリス』で、これもすごい。以前、集英社文庫に入っていたがいまはない。早く文庫で復活しないかな。
晩年の短篇群は、「接木の台」に代表されるように、老人と若い女の痴情を、年期の入った職人の技で巧緻に描いていて感心させられるが、匂いたつようなエロチシズムがあるわけではない。
「頭髪はあらかた白くなり、欠けた前歯の奥からちらちら舌がのぞく」老人の妄念(「色っぽく死にたいものだと、私はそのくせ、心の隅で思いあせっていた」)(「接木の台」)が、一瞬、幻影のように呼び寄せた若い女との交情は、ただ哀しいばかりである。
しかし、これはただの老人文学ではない。老いと若さ、という、対置すれば互いの壁としかなりようのない一種のタブー、障害を越えて結びつきあおうとする「恋愛小説」といえる。
そして、こうした私小説的情痴小説群に、和田芳恵という女性名を冠してみるとき、紫式部から樋口一葉へと連なる日本の女流文学の系譜に位置する作家であるかのような、一瞬の錯覚がおきる。
そういえば、和田芳恵は一葉研究の第一人者で『一葉の日記』の作者だった。債鬼に追われて身を隠し、入口の戸を釘で打ちつけた畳のない部屋で、何年間もこつこつと『一葉の日記』を、まるで貼絵の山下清のように書きついでいたという。
晩年の作に評価が高いが、それ以前の短篇群、透彫(すかしぼり)の職人夫婦の淡々とした日常を描いた「冬の声」、青年記者と遠野出身の娼婦の交流を描いた「おまんが紅(べに)」も僕はすきだ。素直に読んで、素直に感動できる。読者に素直に読ませるという技巧、これこそ最高級の職人芸といえるのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする