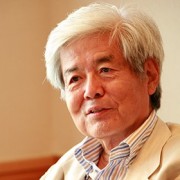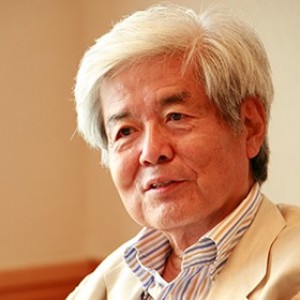書評
『里山に暮らすアナグマたち: フィールドワーカーと野生動物』(東京大学出版会)
研究室にこもらぬ学者の力
里山に暮らす哺乳類は多いが、その中で著者が主に研究対象としたのがアナグマである。アナグマ研究についてはイギリスのオックスフォード大学が有名で、この大学の近傍には本書にも記されるワイタムの森があり、アナグマが高密度に生息する。著者はこの大学にも留学して研鑽を積む。アナグマは里山の動物とはいえ、ふだんあまり見慣れない動物で、私は二十数年前に、当時は岩手県大船渡市にあった北里大学水産学部の校門で一度見ただけである。夜行性のアナグマを昼間に人里で見るのは珍しい。つい二、三年前、箱根の別荘で客人たちと外食して戻った時に、客が子連れのアナグマが裏庭を歩いていたので写真を撮ったと言っていた。この家族にも残念ながらその後出会っていない。本書はアナグマだけについて書かれたものではない。副題が示すように、里山の動物についてフィールドワークをしてきた女性研究者が、自分の研究歴を仲間との関わり合いも含めて、丹念にまとめたものである。わざわざ女性と書くのは、女性のフィールドワーカーが少ないというだけではなく、動物の生態研究では著しい男女差が出る場合があるからである。
著者は幼い時から動物好きで大学生でケニアに留学し、「動物の行動の意味をわかるようになりたい」と強く思い、動物学を志したという。同じ動物学研究の中でもフィールドワークは見ようによっては過酷な作業であり、好きだからこそできるという面がある。著者はそれだけではなく水泳で鍛えた体力を背景に野外作業に挑戦する。体験から発する著者の文章は克明で力があり、実験室にこもらず様々な実地研究を志す若者たちを力づけるであろう。
里山に生息する哺乳類で著者が対象としてきたのは、キツネ、タヌキ、イタチ、テン、アナグマである。後の3者は種としては日本固有とされる。そのほかに、ハクビシン、アライグマなどの移入種がいる。アナグマを除けば、これらの動物は日本の里山を歩き回っていれば、いずれは出会う相手である。
本書は七章に分けられている。第一章は「里山というフィールド」の総説、第二章は著者とアナグマとの具体的な関係、第三章では「里山のフィールド」として東京都日の出町でのアナグマの生態が記され、第四章はもう一つのフィールドとして水戸市での調査が紹介される。第五章がイギリスのフィールド、オックスフォード近郊のワイタムの森での研究と、そこでの研究者たちとの交流が描かれる。イギリスでは動物の福祉あるいは愛護に関する関心が高いので、著者は「研究者がどのようにして批判を乗り越えて作業を行っているのかにも興味があった」「結論からいうと、『十分に配慮を払うものの、実験を行うと決めたら、データになるまで手加減しないでやり遂げる』というのが彼らの動物を用いた研究に対する姿勢だと思った」ということを学ぶ。
偶然とはいえ、本書の出版にやや遅れて、パトリック・バーカムの『アナグマ国へ』(新潮社)が今月末(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2021年1月)、出版される。イギリスでのアナグマをめぐる社会状況が歴史を含めて丁寧に記されており、人と動物との関わりについて教えられることが多い。併読すれば興味深いと思う。
ALL REVIEWSをフォローする