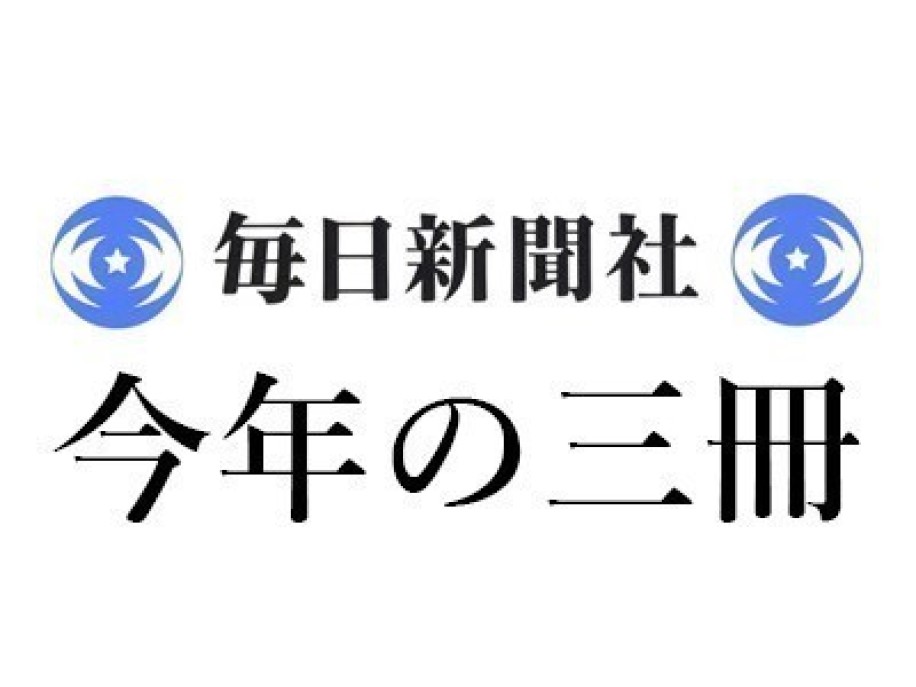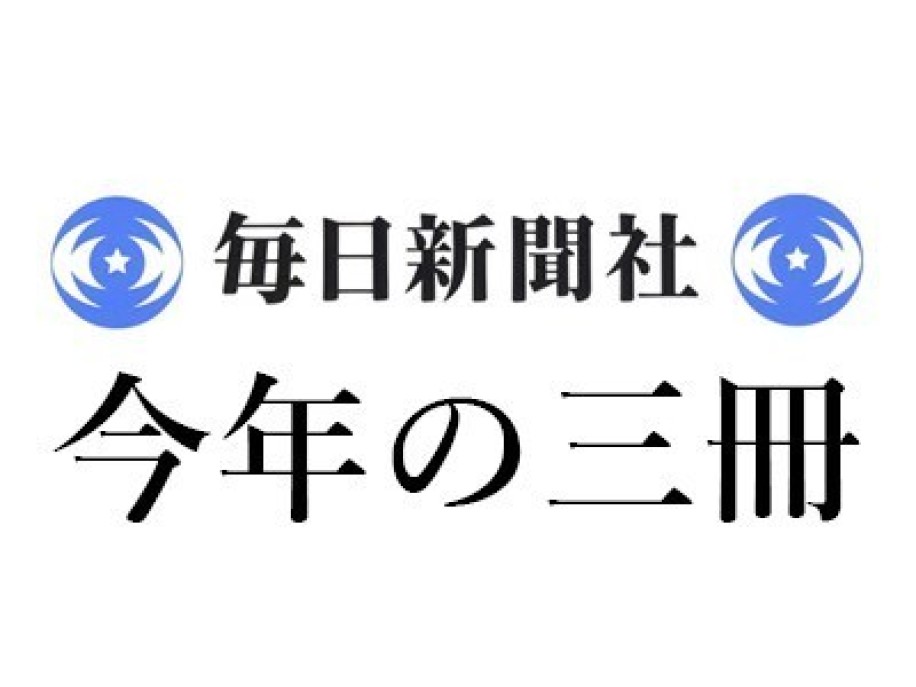書評
『最終目的地』(新潮社)
それぞれの過去とふいに現れる未来
大学院生であり、教員でもある一人のアメリカ人青年が、三人の人物に宛(あ)てて書いた一通の手紙から、この小説は始まる。三人の人物というのはある作家の遺言執行者たちで、主人公のアメリカ人青年は、その作家の伝記を書こうとしている。そのために、遺言執行者たちの「承認」が欲しい、というのが手紙の内容で、受け取った三人の人物――すでに亡くなっている作家の、兄と妻と愛人――は、それぞれに反応する。この三人は、ウルグアイのオチョス・リオスという町に住んでいる。亡くなった作家の屋敷に妻キャロラインと愛人アーデンが、アーデンの娘の幼いポーシャと共に暮しており、そこからすこし離れたべつの家に、兄アダムが年若い男性パートナーと暮している。この人々の、優雅で物悲しい暮しぶり、オチョス・リオスという辺鄙(へんぴ)で美しい土地、そこに流れる時間の穏やかさと物憂さ、が、なんといってもすばらしい。風景も、人々の会話や表情も、衣食住のさりげなくも濃(こま)やかなディテイルも、一つずつくっきり描写されるので、気がつくと私もそこにいて、彼らや彼らの土地にすっかり魅せられていた。何しろピーター・キャメロンは、カーテンの揺らぎ一つ、昼食のテーブルにのったスープ一つおろそかにしないのだ。
小説の構造上、主人公はアメリカ人青年だといえるだろうし、やや(というか、かなり)頼りない彼の人物造形や、しっかりもののガールフレンドとの関係、ウルグアイの人々との出会いがもたらすことになる変化、といったアメリカ青春小説風のあれこれは、もともとピーター・キャメロンの得意とするところであり、事実、アメリカの章とウルグアイの章の際立ったコントラストはこの本の読みどころの一つでもあるのだけれど、でも真の主人公は誰かと問われれば、世捨て人のように暮している三人(プラス幼いポーシャ、プラスアダムのパートナーのピート)だとこたえることも可能だし、時間だとこたえることも、さらには表舞台に一度も登場しない、亡くなった作家のユルス・グントだとこたえることも、無論可能なのだ。登場人物たちの人生は、ユルス・グントただ一人の人生によって交差し、結びついているのだ。
物語に戻ると、冒頭に置かれた手紙で「承認」を得られなかったアメリカ人青年オマーは、じかに会って彼らを説得しようと単身ウルグアイに乗り込む。べつべつの時の流れが偶然合わさることで、新しく(そしてよんどころなく)ひらけてしまう未来。未来があるということは、希望であると同時に絶望でもある。誰もひとところにとどまっていられないという意味において。
へんくつな老人のアダムや、かつて男娼(だんしょう)をしていたピート、画家であり感情の揺れやすいキャロラインや、健全さ故に孤独なアーデン、いちばん過去がすくないからこそ、存在そのものが過去を体現しているともいえるポーシャ。ユルス・グントという人物によってゆるやかに結びつけられていた彼らの人生が、しずかにほどけていくさまの、美しさと喪失感、あかるさと取り返しのつかなさ。
見事なのは、過去をめぐる物語なのに回想シーンがほとんどないこと。それが小説に陰翳(いんえい)と深みを与えている。目に見えず、説明されることもなく、それでも確かに存在する過去と、思いもかけないふうにふいに、出現する未来。
多用される会話、ぶれのないカメラワーク、そして、物語の終盤に、人々のいる場所。
ためいきがでるくらい美しい小説だった。
ALL REVIEWSをフォローする