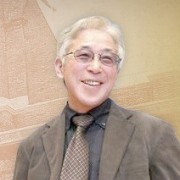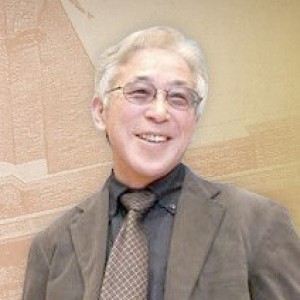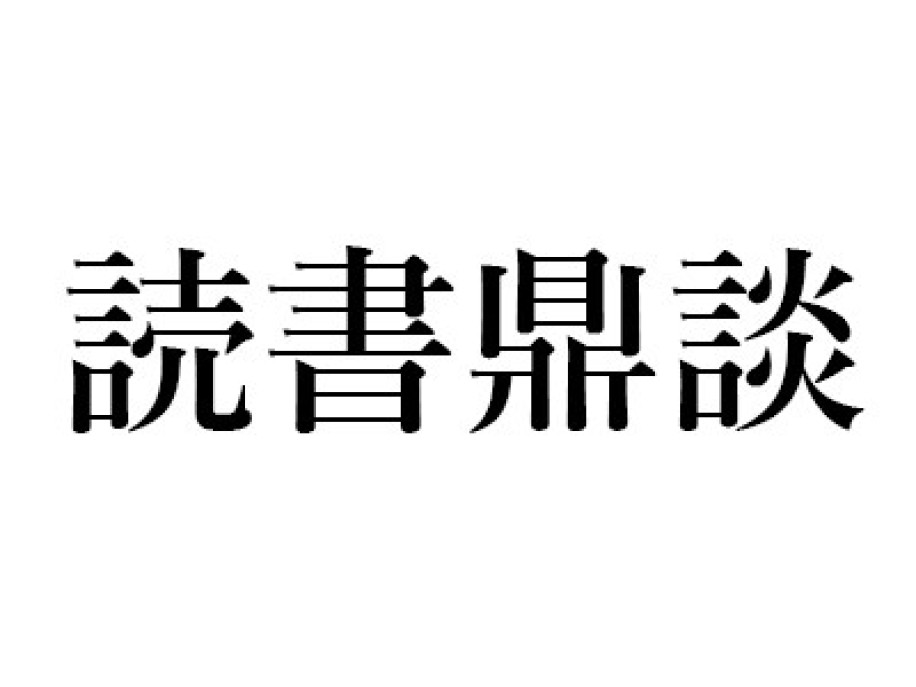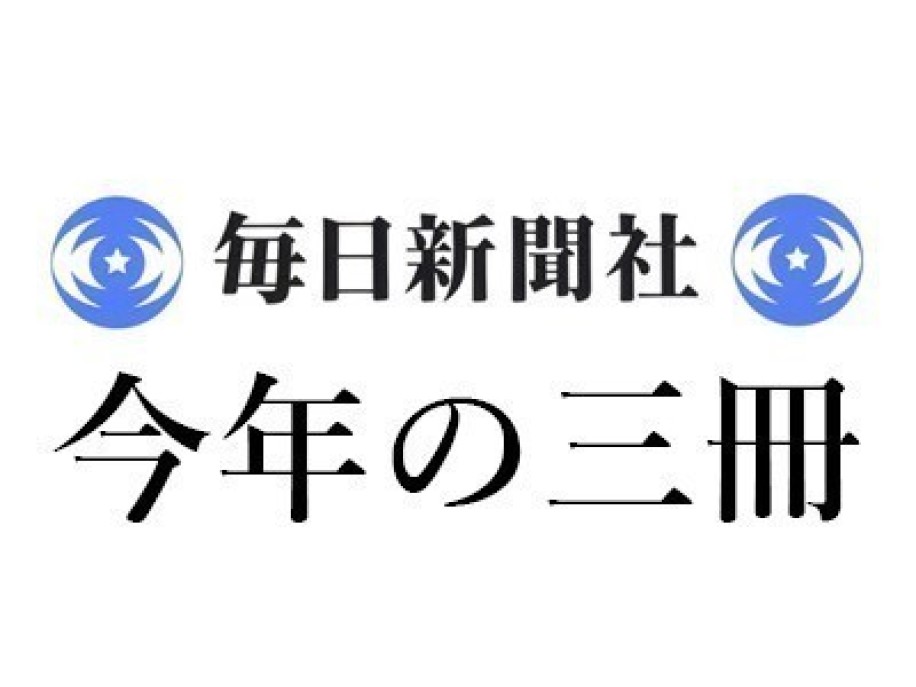書評
『ヒュパティア:後期ローマ帝国の女性知識人』(白水社)
非業の死に凝縮された世界史
二〇〇九年の映画≪アゴラ≫(邦題≪アレクサンドリア≫)は多くの人々に衝撃だったにちがいない。キリスト教徒が少ない日本人にはなじみが薄いが、五世紀初めのヒュパティアの伝説は千六百年にわたって語り継がれてきた。一人の人間、しかも女性の死が、一つの時代の終わりを象徴する出来事になったのだ。ヒュパティアは、四世紀半ば、名高い哲学者・数学者テオンの娘としてエジプトの学芸文化都市アレクサンドリアに生まれた。そのころ、キリスト教は公認されていたが、異教徒が大半をなし、神殿は人々であふれていた。裕福な家庭に育ったヒュパティアは、神々を奉じる伝統的な宗教に彩られた教程のもとで教育されただろう。
ところが、子供のころ、故郷の都市でキリスト教徒が多数派になりつつあった。いまだに神殿は開かれ、神々の像と神々への崇敬はどこでも見られたから、異教とキリスト教の境界はあいまいだった。
このような時勢のなかで、ヒュパティアは学問の道へと歩みだした。文法学校から修辞学学校へと進学し、十代後半には数学と哲学を学び、二十代後半には知的生活の議論を磨きあげた。三十歳ごろには、アレクサンドリアのもっとも傑出した知識人となっていたという。
ヒュパティアの生きた世界は、女性が平等らしきものを享受できる社会ではなかったが、覚悟さえあれば才能ある女性には自由にふるまえる余地があった。彼女は通常の訓練では満足しなかったし、父親よりも数学の才能に恵まれていた。学生から父の同僚の一人となり、やがて哲学塾の学頭となったとき、その名声には犠牲がともなっており、生涯純潔を選び、結婚しないことを公言せざるをえなかった。
三九二年、キリスト教徒の手でセラピス神殿が破壊された。そのとき、アレクサンドリアの人々はこの百年足らずの間におきた宗教世界の変化をもはや無視できないと思ったらしい。どうやら異教とキリスト教との分断は深刻なのだと感じながら、世界はもう理解しがたい姿に変わってしまったのだと認めないわけにはいかなかった。
ヒュパティアが率いる学塾は弟子のなかから政界と宗教界に要人を輩出しており、新プラトン主義者の公的知識人の役割を担っていた。しかしながら、アレクサンドリアのエリートの間に隠れていた分断が明るみになる。キリスト教主教とローマ帝国総督とが衝突したのである。しかも、総督とヒュパティアはしばしば会見しているというから、ヒュパティアは魔術で総督をたらしこんだのだとの噂がささやかれていた。
四一五年三月、あるキリスト教徒の一味の群衆が路上へ繰り出し獰猛な気分でいたとき、たまたま外出したヒュパティアにめぐり合ってしまった。ヒュパティアは捕らえられ、衣服と身体は陶片で引き裂かれ、目はえぐり出され、その骸は路上で引き回されたすえに燃やされたという。
ヒュパティアの非業の死は、キリスト教会の腐敗・ギリシア的理性の終焉・宗教的原理主義の萌芽を象徴するものであり、悲劇のヒロインでも聖女でもない。その生涯と伝説をめぐって、本書は個人史のなかに凝縮された世界史の精髄を語ってくれる。
ALL REVIEWSをフォローする