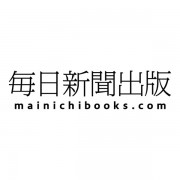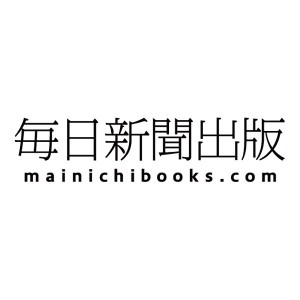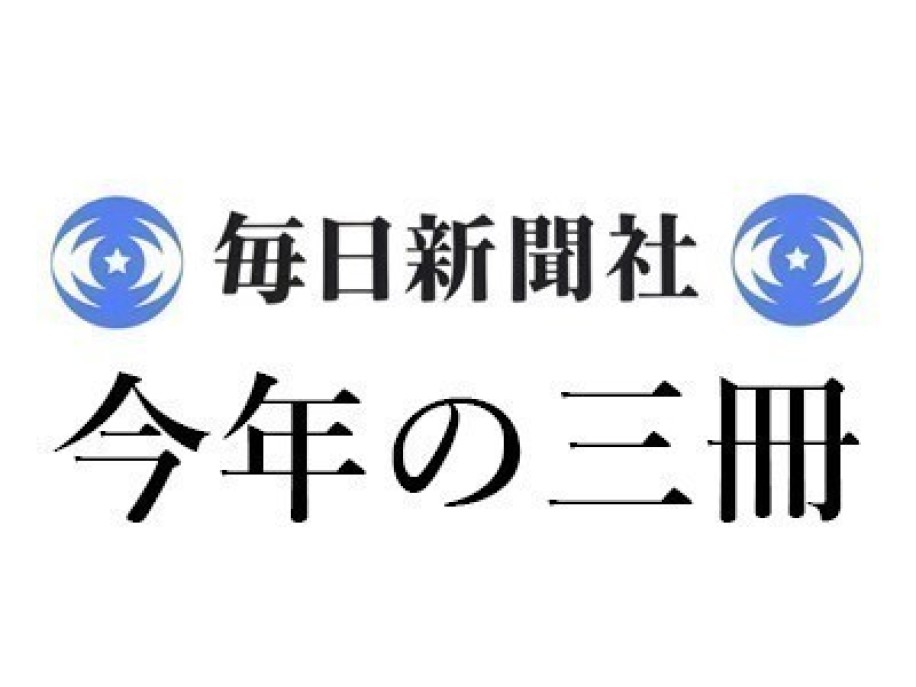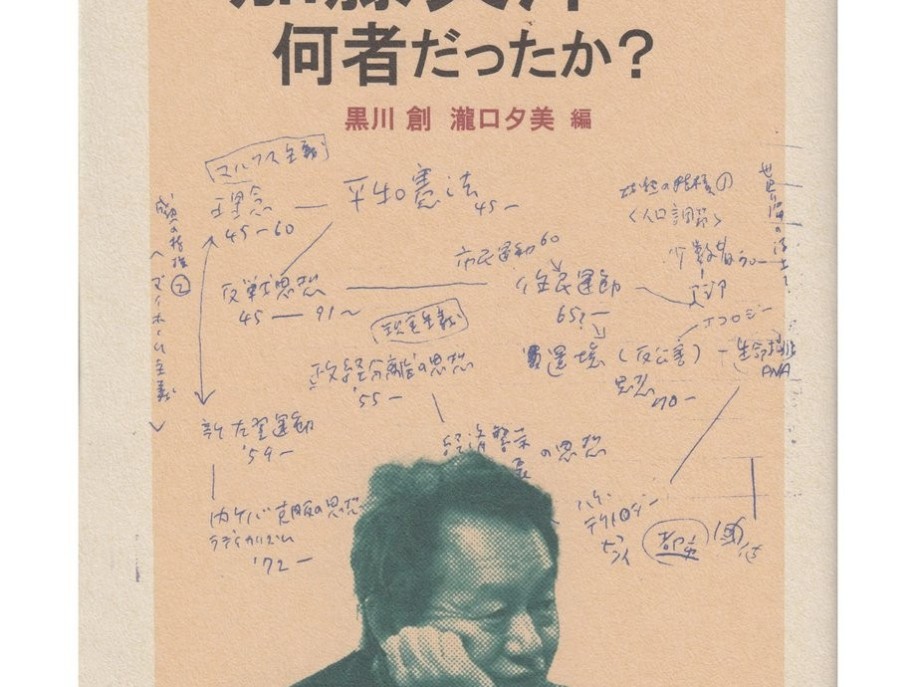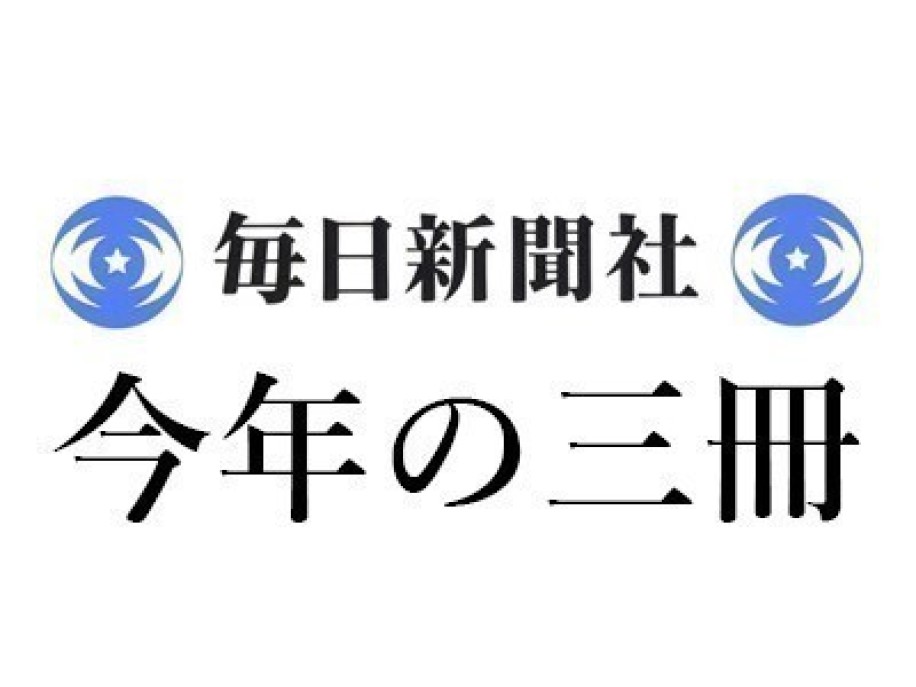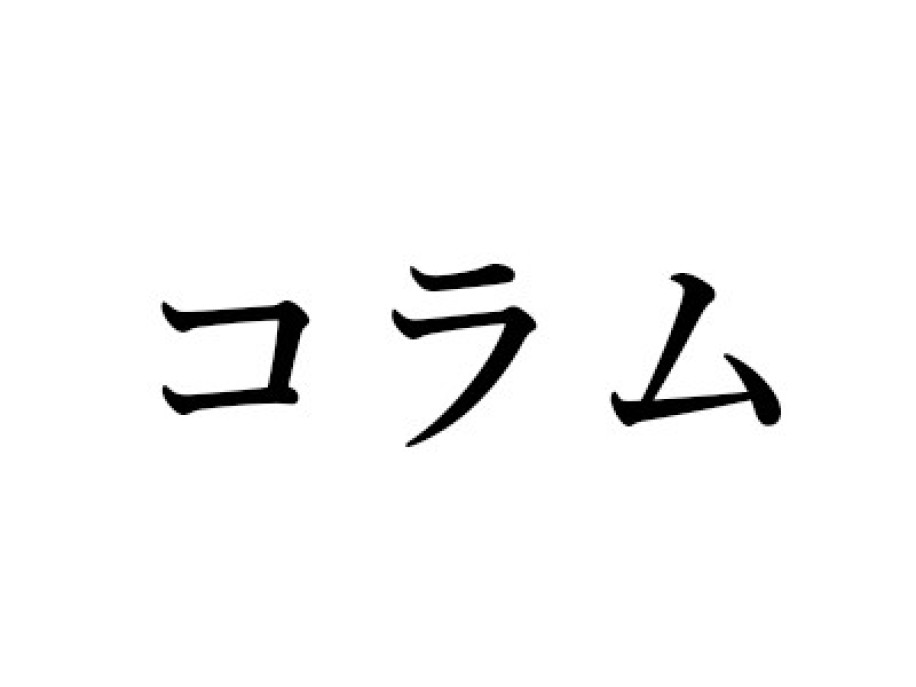前書き
『生きる意味』(毎日新聞出版)
「私たちは今、順風満帆とは到底言えない時代を生きている」と語るのは、東京大学名誉教授で政治学者の姜尚中さん。抜き差しならない人生の困難に直面した時、私たちはどう乗り越えていけばよいのでしょうか。
このような「逆境」の時代の人生案内ともいうべき姜さんの著書『生きる意味』が発売されました。ありふれた日常の光景の中から心を揺さぶる場面をすくい上げ、静かに丹念に描いた名エッセイ28編が収録されています。本書の「はじめに」を特別公開します。
大上段に問われれば、きっと引いてしまうに違いない。それは、余りにも本質的で、しかも日々の糧には役立たないばかりか、むしろ余計な思索に思われるからだ。
そうした問いは、ちょうどジョギングをしながら手足を動かすたびに、その動きを反省し、なぜ自分は今こうして手足を動かしているのかを問うに等しい。そこでは、健康のため、気晴らしのため、汗をかくためにジョギングを楽しんでいると答えれば、それで済むことだ。
しかし、それでも問いは残る。では体を動かしたり、ジョギングを楽しんだりするは何のため?
でも、そんな問いそのものが無意味で、とにかく生きるために自分は体を動かし、一日が終われば寝て、朝起きて学校や職場に出かける。あるいは朝食を準備するのに余念がなく、家族の者が出払えば、後は自分の時間を楽しむだけ。こうした答えが返ってくるのではないだろうか。
私たちの普通の人生とはそうした何の変哲もない日常の繰り返しであり、偶に日常から解放されて、普段は体験できないワクワクするイベントに参加したり、旅に出たり、あるいは演劇や音楽を楽しんだりと、要するに「ケ」に対する「ハレ」を満喫して、また日常の「ケ」に戻る。その繰り返しが私たちの人生というものであり、「人生の意味」などという難しい話に迷い込むのは「心の健康」にもよくないということになるのかもしれない。
ただ、抜き差しならない人生の困難に直面した時、人は問わざるを得なくなるのではないか。「人生の意味」とは何かと。
人生における深刻な困難の一つが、「死に至る病」に取り憑つかれた場合だろう。文豪トルストイの小説『イワン・イリッチの死』から着想を得たとされる黒澤明監督の名作映画『生きる』は、不治の病に慄く平凡な役人が主人公である。彼は「生きる意味」に目覚めるように、死力を尽くして市民から陳情のあった小公園建設に奮迅し、それを見届けるように従容として死を迎えるという作品である。
名優、志村喬がしんしんと雪降る晩、建設されたばかりの公園のブランコに揺られ、「ゴンドラの唄」を口ずさみながら笑みを浮かべているシーンは今でも語り草になっている。映画は、私たちと同じ市井の人の凡庸な人生にずしりと重い存在感を与えてくれたのである。トルストイも、黒澤も、何のドラマもないような平凡な人生であっても生死の深淵を垣間見るような悲劇的な困難に直面した時、自分なりの「人生の意味」を見いだせば、笑みすら浮かべながら、恐ろしい死をも受け入れられると言いたかったのである。
明らかに小説の、そして映画の中で不幸は突然やってきて、主人公に「人生の意味」を模索する「苦行」を強いることになる。それは、安楽さに慣れた凡人には耐えがたい厄災、不幸そのものに違いない。しかし、自分の人生の終わりが避けられなくなった時、人はどうするのか。問いは重たい。
本書は、そうした重たい問いを重たく語るのではなく、私を取り巻く身辺雑記風の描写を通じて考えてみようとした「人生案内」と言ったらいいだろうか。
本文のラストにある「順境と逆境」でも触れているように、人生の困難が個々の問題にとどまらず、むしろ今は時代そのものが困難に喘いでいるのである。その時代を否応なしに生きざるを得ない私たちは、いつ何時、小説や映画の主人公と似たような境遇に直面するかもわからない。戦争や恐慌、生活苦や自然災害、さらに殺伐とした世情など、私たちは今、順風満帆とは到底言えない「逆境」の時代を生きており、だからこそ、「人生の意味」について一度は真剣に考えてみる必要があるのではないだろうか。
本書がその手がかりになれば、望外の喜びである。
[書き手]姜尚中
このような「逆境」の時代の人生案内ともいうべき姜さんの著書『生きる意味』が発売されました。ありふれた日常の光景の中から心を揺さぶる場面をすくい上げ、静かに丹念に描いた名エッセイ28編が収録されています。本書の「はじめに」を特別公開します。
「逆境」の時代を生き抜くヒント
「生きる意味」とは何か?大上段に問われれば、きっと引いてしまうに違いない。それは、余りにも本質的で、しかも日々の糧には役立たないばかりか、むしろ余計な思索に思われるからだ。
そうした問いは、ちょうどジョギングをしながら手足を動かすたびに、その動きを反省し、なぜ自分は今こうして手足を動かしているのかを問うに等しい。そこでは、健康のため、気晴らしのため、汗をかくためにジョギングを楽しんでいると答えれば、それで済むことだ。
しかし、それでも問いは残る。では体を動かしたり、ジョギングを楽しんだりするは何のため?
でも、そんな問いそのものが無意味で、とにかく生きるために自分は体を動かし、一日が終われば寝て、朝起きて学校や職場に出かける。あるいは朝食を準備するのに余念がなく、家族の者が出払えば、後は自分の時間を楽しむだけ。こうした答えが返ってくるのではないだろうか。
私たちの普通の人生とはそうした何の変哲もない日常の繰り返しであり、偶に日常から解放されて、普段は体験できないワクワクするイベントに参加したり、旅に出たり、あるいは演劇や音楽を楽しんだりと、要するに「ケ」に対する「ハレ」を満喫して、また日常の「ケ」に戻る。その繰り返しが私たちの人生というものであり、「人生の意味」などという難しい話に迷い込むのは「心の健康」にもよくないということになるのかもしれない。
ただ、抜き差しならない人生の困難に直面した時、人は問わざるを得なくなるのではないか。「人生の意味」とは何かと。
人生における深刻な困難の一つが、「死に至る病」に取り憑つかれた場合だろう。文豪トルストイの小説『イワン・イリッチの死』から着想を得たとされる黒澤明監督の名作映画『生きる』は、不治の病に慄く平凡な役人が主人公である。彼は「生きる意味」に目覚めるように、死力を尽くして市民から陳情のあった小公園建設に奮迅し、それを見届けるように従容として死を迎えるという作品である。
名優、志村喬がしんしんと雪降る晩、建設されたばかりの公園のブランコに揺られ、「ゴンドラの唄」を口ずさみながら笑みを浮かべているシーンは今でも語り草になっている。映画は、私たちと同じ市井の人の凡庸な人生にずしりと重い存在感を与えてくれたのである。トルストイも、黒澤も、何のドラマもないような平凡な人生であっても生死の深淵を垣間見るような悲劇的な困難に直面した時、自分なりの「人生の意味」を見いだせば、笑みすら浮かべながら、恐ろしい死をも受け入れられると言いたかったのである。
明らかに小説の、そして映画の中で不幸は突然やってきて、主人公に「人生の意味」を模索する「苦行」を強いることになる。それは、安楽さに慣れた凡人には耐えがたい厄災、不幸そのものに違いない。しかし、自分の人生の終わりが避けられなくなった時、人はどうするのか。問いは重たい。
本書は、そうした重たい問いを重たく語るのではなく、私を取り巻く身辺雑記風の描写を通じて考えてみようとした「人生案内」と言ったらいいだろうか。
本文のラストにある「順境と逆境」でも触れているように、人生の困難が個々の問題にとどまらず、むしろ今は時代そのものが困難に喘いでいるのである。その時代を否応なしに生きざるを得ない私たちは、いつ何時、小説や映画の主人公と似たような境遇に直面するかもわからない。戦争や恐慌、生活苦や自然災害、さらに殺伐とした世情など、私たちは今、順風満帆とは到底言えない「逆境」の時代を生きており、だからこそ、「人生の意味」について一度は真剣に考えてみる必要があるのではないだろうか。
本書がその手がかりになれば、望外の喜びである。
[書き手]姜尚中
ALL REVIEWSをフォローする