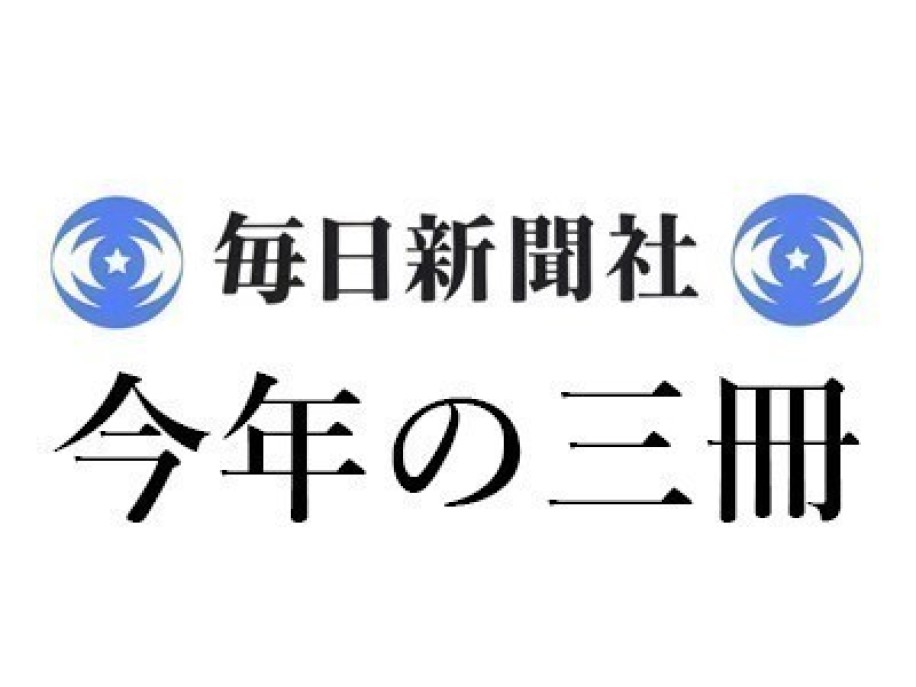後書き
『江戸のキャリアウーマン: 奥女中の仕事・出世・老後』(吉川弘文館)
ドラマ・映画・漫画などで繰り返し題材となり、今なお私たちを引きつけて止まない「大奥」の世界。
色恋沙汰や権力争い、ドロドロとした人間関係がフューチャーされがちだが、実際はどうだったのだろうか。
『江戸のキャリアウーマン』の一部から、武家で働く奥女中(おくじょちゅう)たちの仕事環境やキャリア形成、働きぶりを垣間見よう。
そうした仕事のなかで自身の能力と努力でキャリアを築き、年功を積むことで、役職を昇り、出世する道が開かれたのである。出自の身分や家格が昇進・出世を縛っていた男性家臣とその点で異なっている。キャリアと別に抜擢される場合もあったが、基本はキャリアを重ねて昇進した先に役職筆頭の老女(ろうじょ)の地位にたどり着くのである。
伊達家の場合は、一七世紀前半に老女(「年寄」)が設置されて以降、その配下に若年寄(わかどしより)・表使(おもてづかい)・錠口番(じょうぐちばん)・右筆(ゆうひつ)の役名で、役女系列が階層的に整えられていく経過が確認される。いずれの大名家にも、女中組織を統轄する役職として老女が置かれ、厳格な階梯性を備えて職制が整備されていった。
還暦を超え、古希を超える年齢まで召抱えられる者がいたのは、奥方の日々の仕事に老成円熟した女中の存在が必要とされたからにほかならない。老齢の女中は大名家にとって、貴重な人的資源であった。
では、家元を離れ単身で働く彼女たちが、ここまで働き続けるだけのモチベーションはどこからきていたのだろうか。
奥方は、出自の異なる公家・武家・庶民の女性が協働して主君に奉仕する職場である。世代的には下は一○代から、上は八○代までの者がいる、多世代で構成される組織である。
職務は役女系列・側系列・下女系列に分けられるが、同職間の協力だけでなく、系列のなかでの連携が必要とされ、系列を超えて奉仕する任務もあった。また多くの仕事が、男性家臣や他家の女中も含めた協業により達成される。
毎日の給仕ひとつをとっても、配膳、酒器・食器の扱い、料理の盛りつけなどに上臈(じょうろう)・老女以下、複数の役職の分担があり、協力しあう関係がある。このような役職の上下や同職間の日常的な助力や指導がある人間関係のなかで、奥女中はキャリアを積み重ね、成長していくのである。
奥女中にとって、日々働くことは生活そのものであり、奥女中として生きることを意味したといえよう。
生活=仕事という環境のなかで、生涯現役のプロフェッショナルとして勤め続けた奥女中。
彼女たちの「仕事」への向き合い方から、私たちが学ぶことも少なくないのではないか。
[書き手]柳谷 慶子(やなぎや けいこ・東北学院大学教授)
色恋沙汰や権力争い、ドロドロとした人間関係がフューチャーされがちだが、実際はどうだったのだろうか。
『江戸のキャリアウーマン』の一部から、武家で働く奥女中(おくじょちゅう)たちの仕事環境やキャリア形成、働きぶりを垣間見よう。
勤続60年、齢80!! 現代の常識を超越した働き方
「奥女中のキャリア」
女中たちは、奥方の運営と管理、対外的な折衝、当主とその家族の身辺の世話、衣装・道具の管理など、各々与えられた任務を果たすことで、大名家を支えていた。そうした仕事のなかで自身の能力と努力でキャリアを築き、年功を積むことで、役職を昇り、出世する道が開かれたのである。出自の身分や家格が昇進・出世を縛っていた男性家臣とその点で異なっている。キャリアと別に抜擢される場合もあったが、基本はキャリアを重ねて昇進した先に役職筆頭の老女(ろうじょ)の地位にたどり着くのである。
伊達家の場合は、一七世紀前半に老女(「年寄」)が設置されて以降、その配下に若年寄(わかどしより)・表使(おもてづかい)・錠口番(じょうぐちばん)・右筆(ゆうひつ)の役名で、役女系列が階層的に整えられていく経過が確認される。いずれの大名家にも、女中組織を統轄する役職として老女が置かれ、厳格な階梯性を備えて職制が整備されていった。
「なぜ働き続けることができたか」
奥女中の歴史でとくに驚かされるのは、その勤続年数である。現代社会においても、定年延長など、就労年齢の高齢化がしばしば話題にのぼるが、老女をはじめとした老齢女中は、その比ではない。二〇歳もいかない若年から奉公に上がり、六〇年以上のキャリアを積み、齢七〇~八〇に達し亡くなる直前まで奉公を続けた奥女中がいた。還暦を超え、古希を超える年齢まで召抱えられる者がいたのは、奥方の日々の仕事に老成円熟した女中の存在が必要とされたからにほかならない。老齢の女中は大名家にとって、貴重な人的資源であった。
では、家元を離れ単身で働く彼女たちが、ここまで働き続けるだけのモチベーションはどこからきていたのだろうか。
「チームの一員として」
その要因の一つとして、奥女中たちが日常的に公私の区分がない協業チームのなかにいたことをあげられる。奥女中は単独で仕事をこなすのではなく、組織の一員として協力関係を築きながら与えられた任務を遂行するのである。奥方は、出自の異なる公家・武家・庶民の女性が協働して主君に奉仕する職場である。世代的には下は一○代から、上は八○代までの者がいる、多世代で構成される組織である。
職務は役女系列・側系列・下女系列に分けられるが、同職間の協力だけでなく、系列のなかでの連携が必要とされ、系列を超えて奉仕する任務もあった。また多くの仕事が、男性家臣や他家の女中も含めた協業により達成される。
毎日の給仕ひとつをとっても、配膳、酒器・食器の扱い、料理の盛りつけなどに上臈(じょうろう)・老女以下、複数の役職の分担があり、協力しあう関係がある。このような役職の上下や同職間の日常的な助力や指導がある人間関係のなかで、奥女中はキャリアを積み重ね、成長していくのである。
奥女中にとって、日々働くことは生活そのものであり、奥女中として生きることを意味したといえよう。
生活=仕事という環境のなかで、生涯現役のプロフェッショナルとして勤め続けた奥女中。
彼女たちの「仕事」への向き合い方から、私たちが学ぶことも少なくないのではないか。
[書き手]柳谷 慶子(やなぎや けいこ・東北学院大学教授)
ALL REVIEWSをフォローする