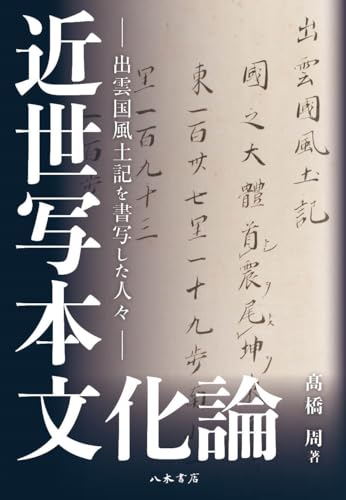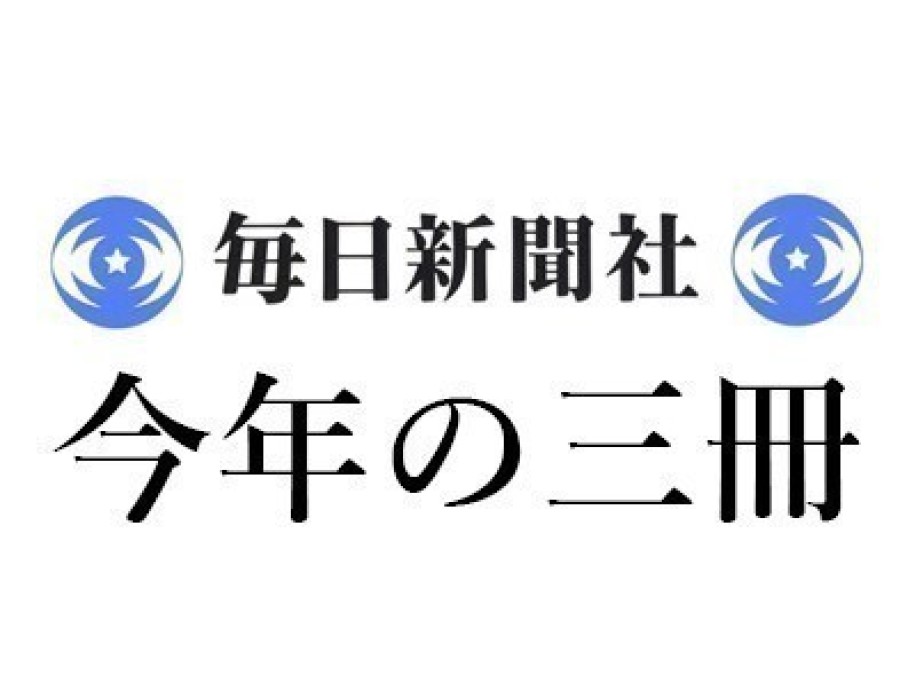書評
『カラカウア王のニッポン仰天旅行記』(小学館)
破天荒な行状、米国人の目で
さらっと本文を読んで楽しく、パラパラ写真や図版をながめて面白く、巻末までじっくり取り組んでためになる、一冊で三度おいしい本。荒俣宏は得意の博物学的手法で、またまた本のエンターティメントを作り上げた。時は一八八一年。主人公はポリネシア人のハワイ国王カラカウア。記すはアメリカ人の国務大臣アームストロング。ハワイの王様の世界漫遊記から、日本・中国・東アジアの部分(三十章のうち十六章分)を訳出。訳文もまたみごとなまでに荒俣調。午餐(ごさん)会の最中に地震がおきた場面はこうだ。
――ひどい揺れかただったが、だれ一人として、地震の「じ」の字もいわない。とうとうカラカウア王が口を開いた。「日本人は、地震を恐ろしいとは思わないのであろうか?」
――英国で教育を受けたという、ユーモア感覚ある日本人が答えた。「ああ、それはですね、地震を罵(ののし)りたくても、日本語にはぴったりした言葉がないからですよ。しかし日本人が英語を学ぶようになれば、英語には強烈な言葉がたくさんありますから、またちがってくるかもしれません」
ハワイのポリネシア化を進めたい王様は、時にアメリカ人の大臣をだしぬき王室外交をたくらむ。なんと天皇家とハワイ王家との縁組の申し入れや「東洋諸邦同盟」の提案がそれだ。この旅行記の面白さは、破天荒なポリネシア人の王様の行状と迎える日本人の対応とを、アメリカ人の目でまったく思い入れなく、それどころか往々にして皮肉と揶揄(やゆ)たっぷりに描き出している点にある。
だが井上馨と火鉢に手をかざしての外交談議のシーンを始め具体的場面での迫力に比べて、日本の近代化への評価などは曖昧(あいまい)で皮相的な嫌いなしとしない。それはなぜか。二十世紀初頭からの一八八一年への回顧である点が一つ。日露戦争の年に刊行された点が一つ。ハワイ併合後のアメリカにとって、近代化をひた走る日本は両義的な存在に他ならなかったからであろう。荒俣宏、樋口あやこ訳。
ALL REVIEWSをフォローする