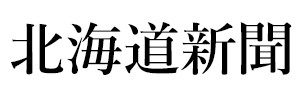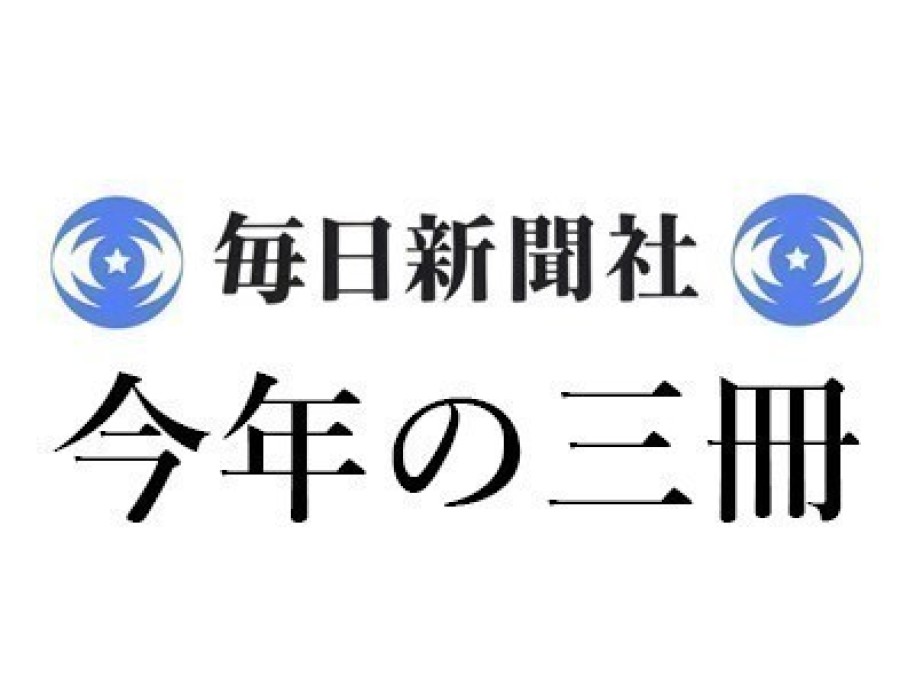書評
『戦国大名の兵粮事情』(吉川弘文館)
モノとカネの「戦争経済」
いつの時代も、戦争は弱者に厳しい。戦国大名は国人(こくじん)・国衆(くにしゅう)や土豪(どごう)、百姓らを戦場に駆り出した。各層に困窮が蔓延(まんえん)し、年貢や公事(くじ)も滞って経済・財政は混乱をきたしていく。そうしたなか、戦国大名は大規模な戦争を行わんがために、率先して大量の兵粮(ひょうろう)確保に乗り出していった。その事情を、さまざまな切り口から見せてくれるのが本書である。重要なアクターの1人が「死の商人」だ。彼らは領主層に米を売り、カネを貸し、武具や馬を用立てる。「戦争は儲(もう)かる」のだ。大口の借り手が戦国大名だとすれば、貸し主たる金融業者への態度も甘くなる。貧困が深刻化しても、そうたやすく「徳政」(借金帳消し)政策など実施できるはずがない。戦争は、社会に遍在する富を強者の側へ引き寄せていく。
こうした戦争と経済の不可分な関係を、著者は〈戦国時代の戦争経済〉とよんだ。確かに、モノとしての兵粮だけではなく、カネとしての兵粮にも目を向けることで、はじめて見えてくる構造的問題であろう。もちろん、二つの兵粮は截然(せつぜん)と分けられるものではない。その錯綜(さくそう)や混乱を解きほぐしてみせる心配りも、著者は忘れていない。
また、本書の提示する豊富な具体例は、実に示唆に富む。たとえば、安保法制をめぐる国会の議論で、兵站(へいたん)が武力行使と不可分かどうかが争われたのは記憶に新しいだろう。兵粮を戦場に運び込む際の困難は、本書に活写される通りである。他方、戦国大名が兵粮米を利殖に回す例も面白い。運用に失敗すれば、目減りを避けられないが。
そして戦争は、権力に対して、「国(御国(おくに))・領国(りょうごく)を守る」という「錦の御旗」を与えてしまう。本書に言う〈「御国」の論理〉・〈兵粮の正当性〉である。さらに、戦争が終わったとしても、権力は戦時経済統制の甘い蜜を吸い続けようとする。
安易な類推は慎むべきかもしれないが、戦前とみまがう今こそ、読まれるべき1冊といえよう。
[書き手] 橋本 雄(はしもと ゆう・北大大学院准教授)
ALL REVIEWSをフォローする