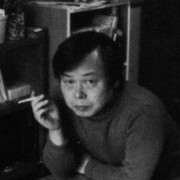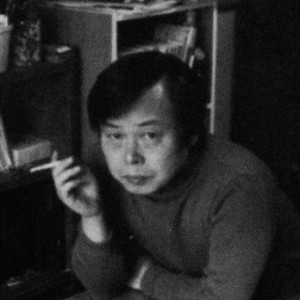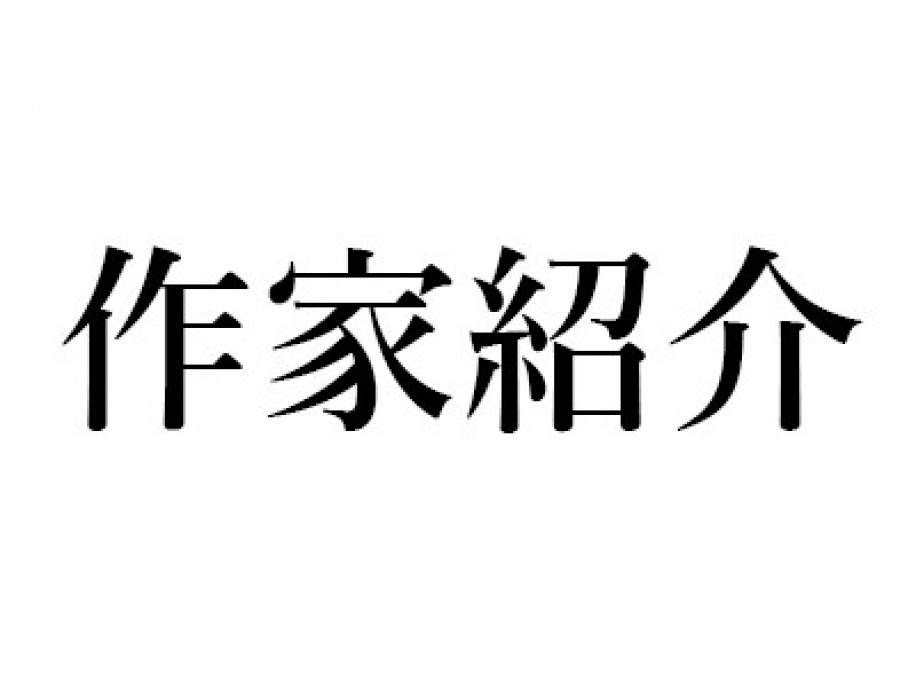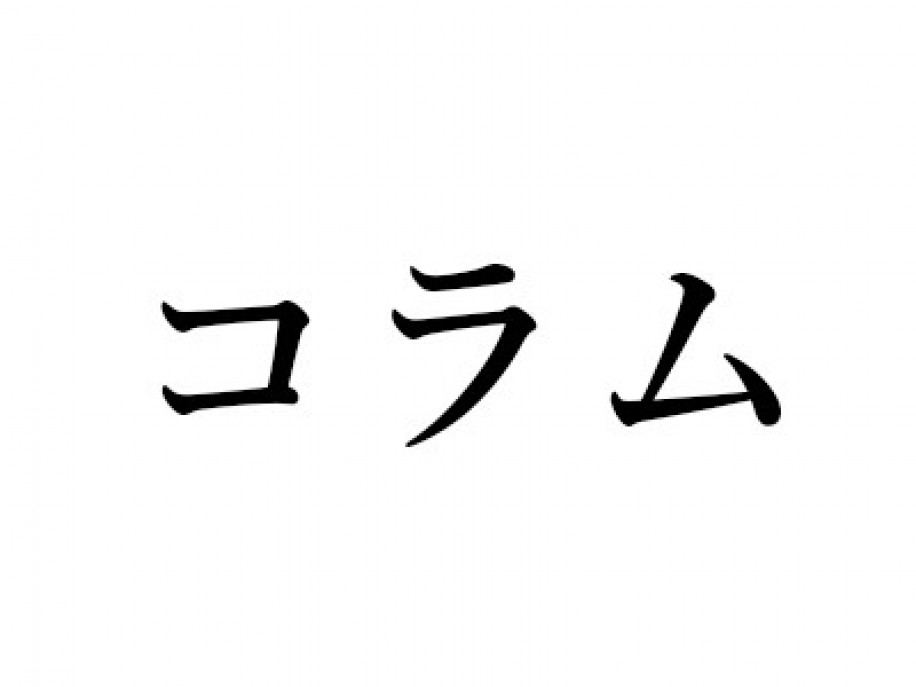書評
『黒鳥館戦後日記―西荻窪の青春』(立風書房)
戦後の戯画
一九四五年八月上旬、中井氏は市谷の大本営航空通信隊にいて腸チフスにかかり、世田谷の第二陸軍病院で昏睡状態のうちに敗戦を迎えた。八月末意識を回復。「二階の病室へ入った筈が、知らぬ間に階下の重病人室へ移されていた。暗い、尿臭に充ちた部屋で、連日誰かが死亡して運び出されていった」。その病後の身体で焼け跡の街へ出て、飢餓と失業と家族や政治状況の激変の大渦に呑み込まれながら、戦後世界を観察した。著者二十四歳の一九四五年九月十六日から一九四六年十二月三十一日までの「戦後日記」である。中井氏にはすでに戦中日記『彼方より』があり、反軍国主義的リベラリズムの精神は戦中から一貫しているので、文化人の戦後転向を喜劇として戯画化し、戦犯知識人の復活の動きにいきどおる「戦後日記」の姿勢には無理がない。
「『敗戦』は日本軍国主義の敗戦であり、即ち同時に民主主義の輝かしき『勝ち戦』である。我々は昨八月十五日に敗れたのではない。勝ったのである」。いくぶん言葉に上ずりながらも、一九四六年二月にそう言い切れる数少ない青年の一人だったのである。それでいて翌日にはもう手ばなしの解放感が孤独な厭人癖へ裏返しになる。「どんな世の中にあっても人間に面を背ける孤独な魂は、未だ未だ私の心に深く巣食っている」
一口にいえば、政治と文学の双頭に分裂した魂の告白である。その分裂のままに、渇えたように小説を読み、歌舞伎、新劇をみ、「赤門文学」発行に奔走するかと思うと、野坂参三歓迎国民大会の徳田球一演説に溜飲を下げたり、一方では新日本文学大講演会の中野重治の「小才子めいた顔付」にシニカルに反応したりもする。これが後年の幻想小説家中井英夫の、と目を疑うほどの極左的言辞が頻出する。だが三十六年後の今日から見れば、それすらも権威主義的な父親への反抗を政治的表現に、その重圧からの避難所となる母親への愛着を文学的表現に託そうとした、戦中世代のかなり一般的な戦後体験ともいえよう。
ただ一つ通常の青年たちと異なるのは、当事者が「パーヴァーション」(性的倒錯)と名づけている暗い衝動を自覚している点だ。その暗い光源が、戦後風俗の描写にも淡いかげりとひややかな距離感を負わせて、戦後のなまなましい混乱とはまた別種の、時代を裏返しに見ているような角度の光景を垣間見させる。戦後日記の上に「黒鳥館」の凶印がしるされているゆえんであろう。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1983年5月9日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする