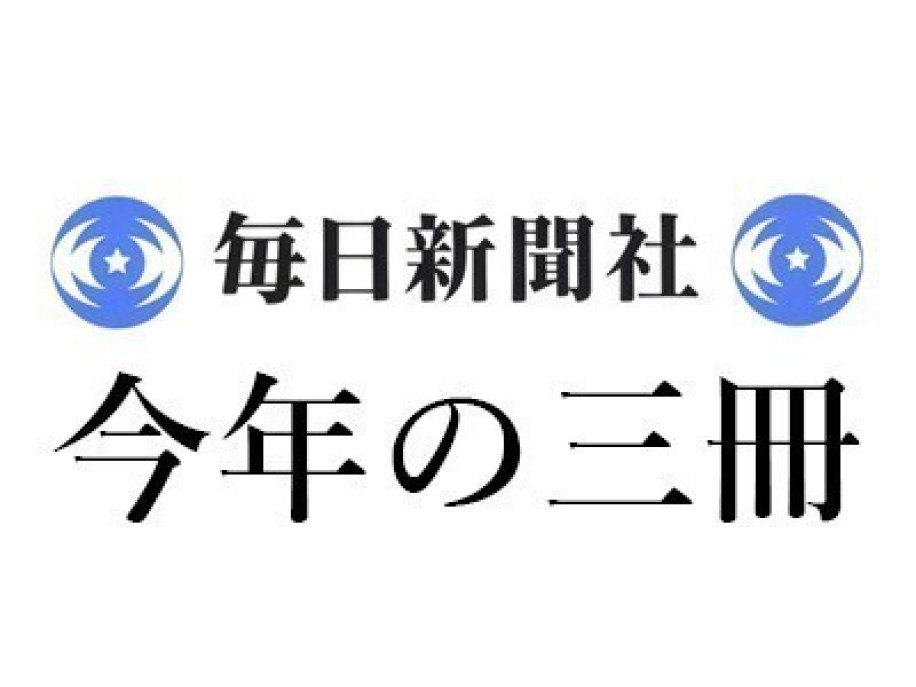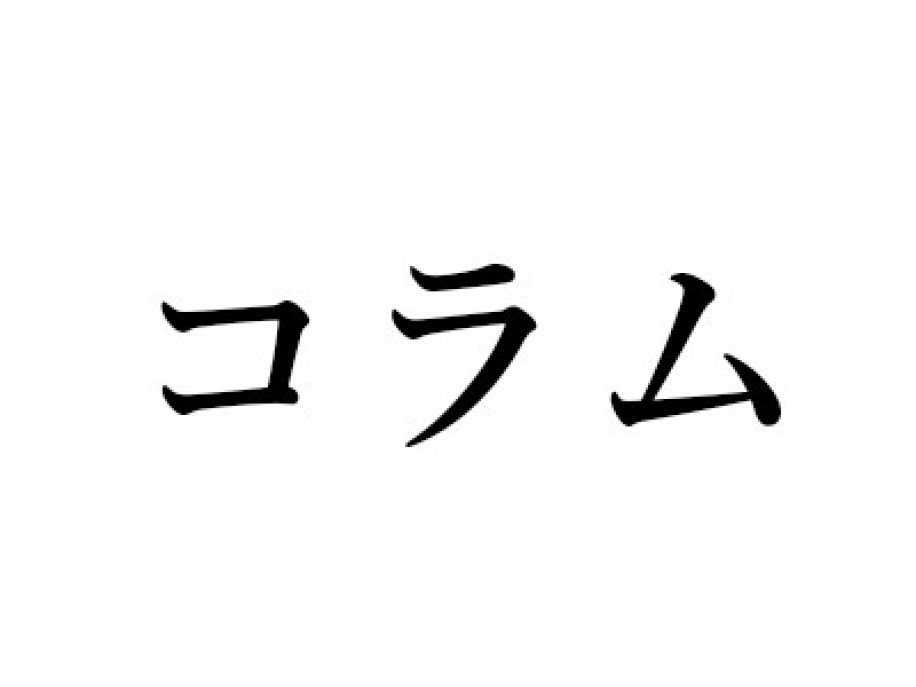書評
『駅前旅館』(新潮社)
腰のすわった語り
世の中の動きがこう激しいと、小説はそれこそ出たとたんに古くなってしまう。で、書くほうとしては危機感をつのらせて人並みにあくせくしだす。最近の小説のめまぐるしさ、落ち着かなさはどうだろう。じっくりと小説の世界にひたっていられないでは読む楽しみは半減してしまう。面白おかしく読めて、しかもじんわりと何かがしみこんでくるような作品はないものか。
とお思いのむきに、『駅前旅館』はどうか。現代小説とはいっても四十年前の作品だから出来たてではない(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆年は1997年頃)。作者の井伏鱒二も亡くなり、小説の舞台である上野駅周辺も首都高速の高架がかかったり新幹線が通ったりで様変わりしたこともあって、ちょっぴり過去のほうに押しやられた。――では発表当時は新しかったかというと、ちょっと違う気がする。作品自体が老けこんでいる。小説全体を老けこませることに作者は腐心している。そうみえる。
私、駅前の柊元(くきもと)旅館の番頭でございます。名前は生野次平と申します。生れは能登の輪島在、早くから在所を離れました。……
という出だしからして作者の腰は決まっている。腰のすわりは語りが終わるまで崩れない。
駅前旅館の番頭、と言われただけで、もみ手をしながら呼びこみをする、へり下っているのか押しが強いのかわからない男の姿が思い浮かばないだろうか。いまは勿論、四十年前だって実際にそんな場面が演じられていたかどうか。だがここに登場するのは、まさにそんな古臭い絵に描かれたような人物だ。
戦前まで呼びこみの風俗はあって、江の島で修業しなくては一人前の番頭とは言われなかったそうだ。善光寺さんの門前町、日光、伊勢の古市、京都の四ヵ所に呼びこみの名人が集まっていて、その中の腕っこきが夏場の出稼ぎに江の島にやってきた。格好の道場というわけだ。生野次平も二十代の末に江の島を卒業している。
呼込みを致しますには糸でお客を引くようなもので、魚を釣りあげるのと似ております。その場で瞬間的に、しかも自然のように調子のいいことを言わなくっちゃ。言い後れたりすると後の祭でございます。魚を釣るとき浮子(うき)が水に引きこまれたら、間髪を入れずに合わせるようないきさつでございます。
卒業生は語り手ひとりではない。同業の番頭が四人もとっかえひっかえのように出てきて、それが揃いもそろって昔気質の業界人間。律義は律義だが、海千山千のちゃらんぽらん。口八丁手八丁に介入して生野次平の語りをにぎやかにする。
四人の番頭仲間にはやされて、昔あらぬ疑いをかけられていた急場を救ってやって以来慕われていた於菊の行方を尋ねて長野までおもむいたことから、何人かの女性をめぐって達引(たてひ)きが生じる。女のことは卒業したとでも言いたげな語りに、ふっと中年男の脂の浮いた顔がうかんで、それはそれで色っぽい。
首尾はどうなるのか、話題があっちこっちと飛ぶので、ひと通りでなく気をもまされる。その辺は釣り師としても知られた作者の免許皆伝の腕の冴えだ。
最近の小説のスリルとサスペンスのエスカレートぶりは大変なものだが、ここでは、気をもたす、もたされるという古型が使われていて、酷な人情もののようなクライマックスまで用意されている。
「生野次平というこの俺は、色道にかけて何という雑な男だろう」と語り手は最後に述懐するにいたる。その顔は意外に、はっとするほど若々しい。あるいはこの小説、年とともに若返る作品かもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする



![喜劇 駅前旅館 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/517V1HKQM0L._SL500_.jpg)