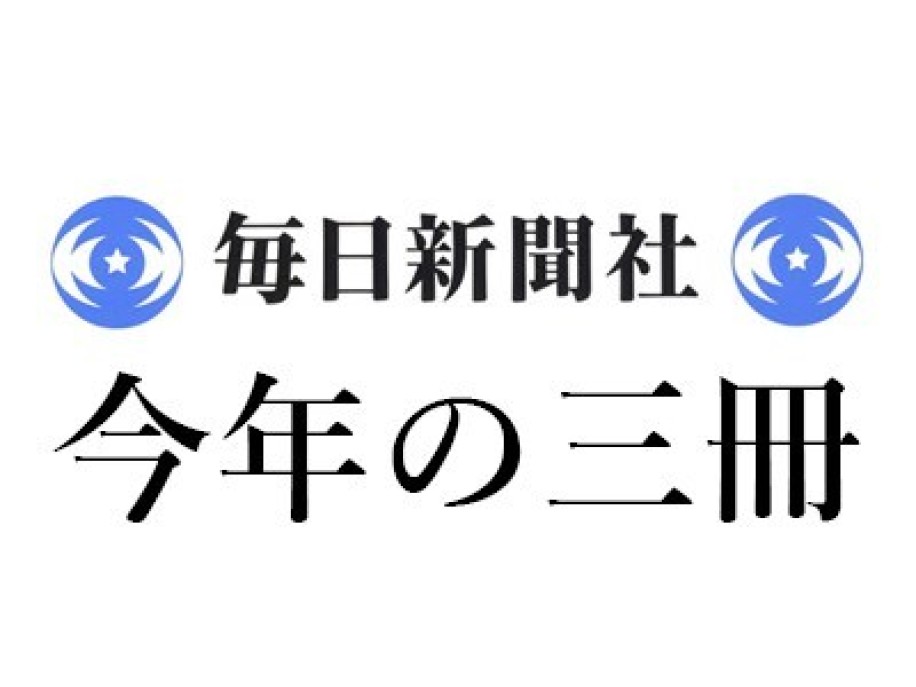後書き
『ヨーロッパとゲルマン部族国家』(白水社)
ローマと蛮族の接触によって、西欧社会はどのように変化していったのでしょうか。最新の研究成果から、流動的な現代ヨーロッパ社会を理解するためにも役に立つ視点を提供します。
他方、そこにはローマ帝国がひとつの文明世界を営んでいたから、一連の現象は「ローマ帝国の崩壊」のストーリーとしても紡がれてきた。ひとつの文明世界が瓦解し、それを養分としながら新しい世界の芽が吹いた、と理解されてきた。
著者のマガリ・クメールとブリューノ・デュメジルは、斯学における現代フランス歴史学界のホープである。古代末期、初期中世のヨーロッパを俯瞰して、それぞれの地点に分け入り、ときに微細に、ときに雄大に考察を積み上げてきた。この両者による共著であるから、本書は、フランス読書界でもひとつの定番テキストとして版を重ねているようだ。
本書は、古くて新しい研究対象に、最新の研究成果を踏まえて切り込んだ注目すべき書物である。
周知のようにカエサルの昔から、アルプスの北側にゲルマン人らがいたことは認識されていた。本書でも、そのとき以来のローマ帝国との関係は言及されている。しかし本書の真骨頂はむしろ、四世紀後半に諸部族が、ローマ帝国内で自らの社会・国家形成の方向に動き出して以降の説明、その明快な叙述にある。彼らの社会は、六世紀になるとまさに王国と呼べる政治社会単位にまで成長した。その間の経緯、新しく立ち上がった国家の性格、その内部組織の特徴などが、それぞれの段階に応じてきわめてクリアに解説されているのである。
「中世的秩序の形成」という問題は、近年熱い視線が注がれている分野である。
この点で本書は、地中海世界の全体を見渡して、東のビザンツ帝国事情をも含めて「諸部族国家の形成」について語っているところに特長がある。たとえば、ビザンツ帝国の東また北の境域における「蛮族」たちの襲撃の方が、皇帝たちにとっては手を焼いた、と正しく指摘されている。また、西帝国の北方境域における諸民族の侵入についても、「三世紀の蛮族の軍隊は、領域を征服しようとも帝国と戦争して勝とうともしていなかった」と興味深い指摘がなされている。端的に、それは襲撃というより略奪だ、というのだ。
この指摘は、四世紀末以降に帝国領内にいくつもの諸部族国家が建設された事実をどう考えるべきか、という点で重要な観点となってくる。
東方戦線では、ササン朝ペルシアが領土的野心を露骨にしていた。この野心のもとに、両帝国のはざまにあったアラブ人各部族が、より有意な交渉を両帝国と繰り広げていた。それが当時の実態であり、深刻な事態を迎えていたのは、西ではなく東だったのである。
東方へのこの顧慮を忘れると、ゲルマン民族の国家形成、つまりヨーロッパの成立論も、ヨーロッパ人による危うい自己賛美になりかねない。
さて、周知のように、二十世紀末以来の東西冷戦構造の瓦解が、各地の民族問題を孕んで今日的世界情勢を生んだことで、新たに発生した難民・移民への視線が熱く語られる現在でもある。近年のこの移民・難民現象が、古代末期~初期中世の現象への一般的関心を高めているようでもある。特にフランスでの移民・難民問題は、ひとつの大きな政治問題ともなっている。この並行現象への関心にも的確に応えようとしているのが、本書といってよい。
[書き手]大月康弘(一橋大学大学院経済学研究科教授・経済史、西洋中世史、ビザンツ学)
移民問題を歴史から見つめ直すために
古代末期から初期中世と呼ばれる二~七世紀。地中海の周辺世界には、いくつもの部族集団が到来し、やがて定住した。「蛮族」や「部族」と呼ばれるそれらの集団を、近代の歴史学、特に十九世紀以来の歴史学は、「民族」集団として捉えて現代ヨーロッパに至る源流とも考えてきた。他方、そこにはローマ帝国がひとつの文明世界を営んでいたから、一連の現象は「ローマ帝国の崩壊」のストーリーとしても紡がれてきた。ひとつの文明世界が瓦解し、それを養分としながら新しい世界の芽が吹いた、と理解されてきた。
著者のマガリ・クメールとブリューノ・デュメジルは、斯学における現代フランス歴史学界のホープである。古代末期、初期中世のヨーロッパを俯瞰して、それぞれの地点に分け入り、ときに微細に、ときに雄大に考察を積み上げてきた。この両者による共著であるから、本書は、フランス読書界でもひとつの定番テキストとして版を重ねているようだ。
本書は、古くて新しい研究対象に、最新の研究成果を踏まえて切り込んだ注目すべき書物である。
周知のようにカエサルの昔から、アルプスの北側にゲルマン人らがいたことは認識されていた。本書でも、そのとき以来のローマ帝国との関係は言及されている。しかし本書の真骨頂はむしろ、四世紀後半に諸部族が、ローマ帝国内で自らの社会・国家形成の方向に動き出して以降の説明、その明快な叙述にある。彼らの社会は、六世紀になるとまさに王国と呼べる政治社会単位にまで成長した。その間の経緯、新しく立ち上がった国家の性格、その内部組織の特徴などが、それぞれの段階に応じてきわめてクリアに解説されているのである。
「中世的秩序の形成」という問題は、近年熱い視線が注がれている分野である。
この点で本書は、地中海世界の全体を見渡して、東のビザンツ帝国事情をも含めて「諸部族国家の形成」について語っているところに特長がある。たとえば、ビザンツ帝国の東また北の境域における「蛮族」たちの襲撃の方が、皇帝たちにとっては手を焼いた、と正しく指摘されている。また、西帝国の北方境域における諸民族の侵入についても、「三世紀の蛮族の軍隊は、領域を征服しようとも帝国と戦争して勝とうともしていなかった」と興味深い指摘がなされている。端的に、それは襲撃というより略奪だ、というのだ。
この指摘は、四世紀末以降に帝国領内にいくつもの諸部族国家が建設された事実をどう考えるべきか、という点で重要な観点となってくる。
東方戦線では、ササン朝ペルシアが領土的野心を露骨にしていた。この野心のもとに、両帝国のはざまにあったアラブ人各部族が、より有意な交渉を両帝国と繰り広げていた。それが当時の実態であり、深刻な事態を迎えていたのは、西ではなく東だったのである。
東方へのこの顧慮を忘れると、ゲルマン民族の国家形成、つまりヨーロッパの成立論も、ヨーロッパ人による危うい自己賛美になりかねない。
さて、周知のように、二十世紀末以来の東西冷戦構造の瓦解が、各地の民族問題を孕んで今日的世界情勢を生んだことで、新たに発生した難民・移民への視線が熱く語られる現在でもある。近年のこの移民・難民現象が、古代末期~初期中世の現象への一般的関心を高めているようでもある。特にフランスでの移民・難民問題は、ひとつの大きな政治問題ともなっている。この並行現象への関心にも的確に応えようとしているのが、本書といってよい。
[書き手]大月康弘(一橋大学大学院経済学研究科教授・経済史、西洋中世史、ビザンツ学)
ALL REVIEWSをフォローする