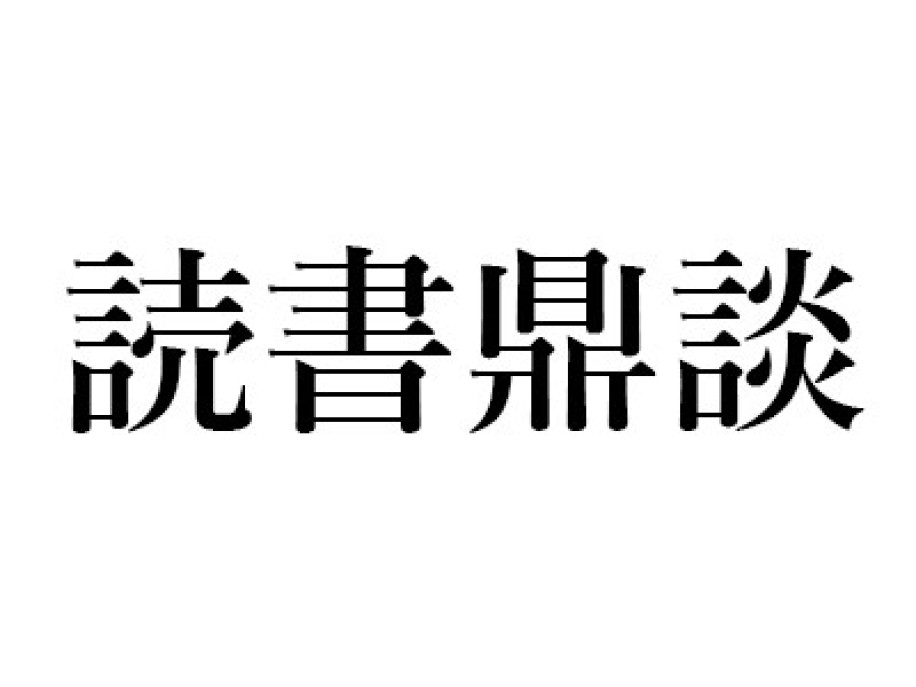書評
『藤村のパリ』(新潮社)
経験が生む芳醇な味、足跡追う探査の執念
島崎藤村は一九一三(大正二)年四月十三日、神戸港を出帆、五月二十日マルセイユに着き、一九一六年初夏までパリに滞在した。かぞえ四十二歳の藤村は姪(めい)のこま子との不倫に悩んだ末、「深い溜息の一つも吐くつもりで」パリに向かったのだが、そのことを知らない文壇では、藤村の洋行を一大壮挙として羨望(せんぼう)する人は少なくなかった。フランス文学者である著者は、藤村に遅れること十五年の同じ季節、同じ航路で渡仏している。本書は藤村の「『エトランゼエ』を鞄に忍ばせ、パリの宿舎でくり返し読み耽った」河盛氏の、若き日へのセンチメンタル・ジャーニーといえよう。
引用はやや長い。しかし「これを書き写しながら、私自身も、その蒸し暑さと、船に荷物や石炭を積み込むさわがしい音に、一晩中眠れなかったシンガポールの夜をまざまざと思い出した」といった体感あふれる文章が、ほかの誰につづれようか。
すでに著者の最初の渡仏からさえ六十数年がたち、月日は経験を磨き、このうえなく芳醇にするのに十分であった。藤村が四十日の船旅を経て到着した都市は、十数時間のフライト、二十万円のパック旅行で行けるパリではない。二千円近い旅費をどう新潮社から引き出したか、朝日新聞への寄稿料五十円で藤村は何を書いたか、経済に及ぶ筆は実証的だ。
藤村の下宿したパリ第十四区ポール・ロワイアル通りなどについて、著者の地理や歴史への知識が活用されて見事である。なお感動的なのは、藤村が四年を過ごした下宿の女主人マダム・シモネエについて、ついに名前や生没年を明らかにしたことだ。その名はマリー、藤村下宿時五十六歳。「この事実からどのような結論を出すかは藤村研究家の自由である……」
ほかに河上肇、石原純、浜田青陵、野口米次郎などが下宿し、山本鼎、郡虎彦らが訪ねた重要な場所であれば、探査の執念は称賛されるべきだろう。
それにしても大正のパリ。ドビュッシーが指揮しニジンスキーが踊り、藤田嗣治が騒ぎ、ジョレスが暗殺され、戒厳令の布(し)かれたパリ。私はこの本を鞄(かばん)にしのばせていつの日か、かの都へ行きたい。
朝日新聞 1997年8月3日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする