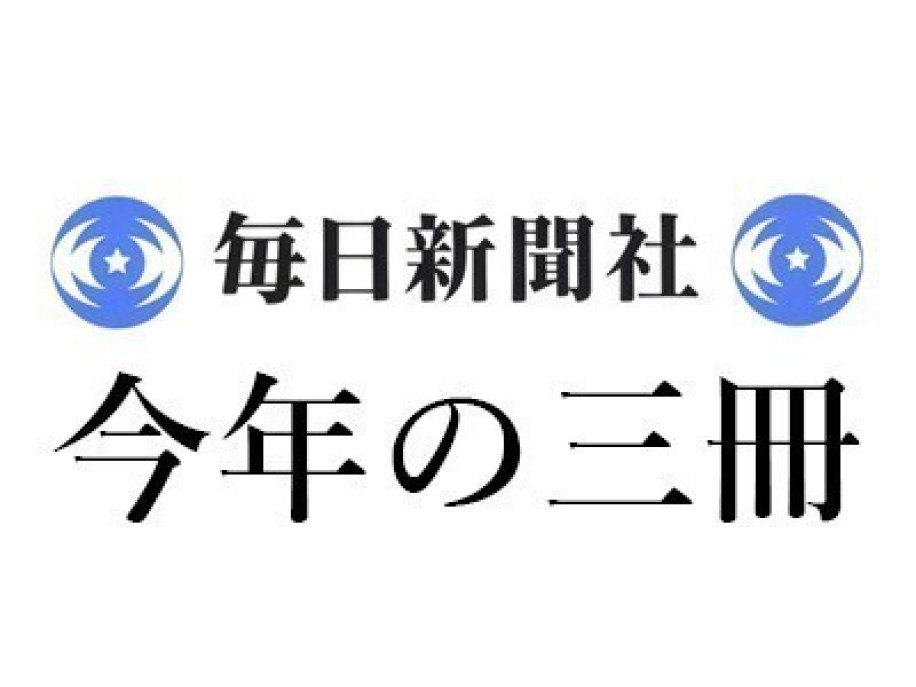書評
『ガチョウの本』(河出書房新社)
二人の少女の絶望と孤独、波瀾万丈
語り手のアニエスは、結婚を機にアメリカに引っ越してきたフランス人。二十代の彼女はニワトリとガチョウを飼育し、庭の菜園で野菜を育てている。そんな彼女のもとに、幼なじみであるファビエンヌが亡くなったという知らせが届く。そして小説は、一九五二年、フランスの片田舎で暮らす二人の少女へと焦点を当てる。ともに十三歳のアニエスとファビエンヌは、日々、独自の遊びを編み出している。主導権を握るのは独創的ではすっぱなファビエンヌで、アニエスはいつも彼女に質問しながら従っている。
あるとき二人は「物語を作る」というあたらしい遊びをはじめる。ファビエンヌが語り、字のうまいアニエスが書き留める。詩を書く郵便局長のもとで、二人は「身の毛がよだつ」話を書き綴(つづ)る。
ファビエンヌが語った物語は、アニエスの著者名で出版され、注目を浴びる。片田舎の農家の子どもが書いた、世にもグロテスクな物語。この本が出版された時点で、彼女たちの遊びは現実に絡め取られるのだが、二人にはやめかたがわからない。アニエスは天才少女作家としてイギリスのフィニッシング・スクールに招かれ、校長の監視のもと暮らし、本を書かされる羽目になる。
小説は徹底してアニエスの目線で描かれるので、十四歳になったばかりの作家と、彼女の小説が、世間的にどのように取り沙汰されているのか断片しかわからない。本当に彼女の筆によるものか疑われているようでもあるし、豚と暮らす農家の子が富裕層向けの学校にいることをあざ笑われているかもしれない。読み手として気になるが、アニエスにしたらそんなことはどうでもいいのである。彼女の関心ごとはただひとつ、ファビエンヌとの手紙のやりとりだけだ。「社会」にひとり放り出されたアニエスは、故郷に戻ればまた二人の世界に戻れると信じ切っている。
アニエスは「偽の神童」というレッテルをはられ、数か月で故郷に帰る。ファビエンヌと再会するが、そこではじめてアニエスは、自分たちがもう以前の時間にも関係にも戻れないことに気づく。とうぜん賢しいファビエンヌはとうに気づいている。その彼女の描写が本当にすごい。私はその部分を読んだとき、片田舎で出会った女の子二人のたましいが、世間によって、あるいは成長によって、あるいはそれぞれの自我によって引き離されたことを、わがことのように思い知らされ、そしてファビエンヌの抱えていた得体の知れないものの正体を垣間見た気がした。私はこのときようやくこのふうがわりな女の子の絶望と孤独を見た。彼女ほど鋭くないアニエスは、村を、国を出ることで、子どもの時間を、ファビエンヌとの別れを、自身の絶望と孤独を、乗り切る。
これほどの波瀾万丈の物語を、作家は、過度な情感をいっさい込めず、美談にもせず、共感すらもはねつけるようにたんたんと描く。少女二人は無力だが、観察眼に富んで聡明で残酷で、ちっともしたしみを感じない。それなのに、読み終えるとこの小説を驚くほど身近に感じる。呼吸をするために、今日一日を生きおおせるために、自分より近しい存在が必要だった幼い時間と、やがてそれと決別しなければならない運命の残酷さが、自分の記憶のように心にはりついている。甘やかな痛みとともに。
ALL REVIEWSをフォローする