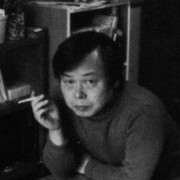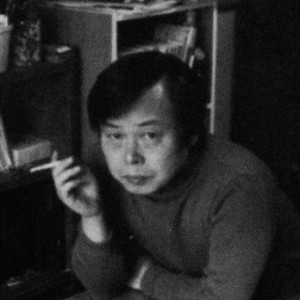書評
『雪野』(文藝春秋)
いかにも遊びの果てに
「いかにも」の語感を一言で説明するのは難しい。いかにも貧乏人、いかにも芸術家……。本物そっくりのコピーでありながら、どこか「いかにも」のズレがのぞいて、いかがわしいのである。たとえば学校で父親の職業をきかれた田舎町の床屋の息子が、ちょっと気取って「理容院」と答える。先生が「何だ、要するにトコヤじゃないか」。教室中がドッと沸く。しかし「要するにトコヤ」ではあっても、「理容院」の脱いだり着たりのズレが面白いのだ。
すくなくともそれを面白いと感じる感受性の持ち主が二人、小学校のクラスで鉢合わせをして意気投合、東京の美術学校でまた一緒になって、「いかにも」ごっこを続けてゆく。題名になっている人物「雪野」と話者の二人組だ。ポーの『ウィリアム・ウィルソン』もどきの、どちらがどちらの「いかにも」とも知れぬ、五〇年代が舞台の分身小説である。
『肌ざわり』以来、肌、皮膚、包装紙のような、かぶりものの現象学を小説化してきた尾辻克彦が、ここでは「いかにも」の皮をかぶる。話者と雪野とは、アルバイトのサンドイッチマンの、「プロレタリア」の、恋愛の、と諸々のいかにもをかぶる。けれども分身同士である以上、お互いに隙あらば相手のいかにもの皮を食い破ろうともする。それに生活の重圧が加担して、いかにもの化けの皮はようやく破れはがれてゆく。
薄っぺらい膜が、それに包まれている得体の知れない物体の暴力に食い破られてゆく過程が、アイロンに釘を生やしたマン・レイのオブジェや、親指の薄皮を裂くナイフや、電柱のようなものが身体に押し込んでくる胃痛のエピソードを畳みかけてメタフォリカルに語られ、するといつしか、目鼻立ちや表情の定かならぬこの小説の人物たちが、じつは皮をかぶった物体であり、人間関係はその物体間の相互運動にほかならないことが、くっきりと浮かび上がってくる。
雪野のほうもいかにも皮は破れるが、こちらは破れると、風となって行方をくらます。それから二十年経って、風は電話口の向こうに帰ってくる。ここで物語全体をもう一度包装するように演じられる、「いかにも」遊びのひねりに一工夫ある。最後に、いかにも小説的でもあるこの小説が、ここに書かれていない六、七〇年代の空白という物体に食い破られる現場を読みたい、という思いがのこった。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1983年8月15日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする