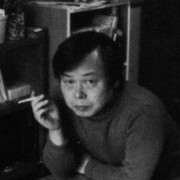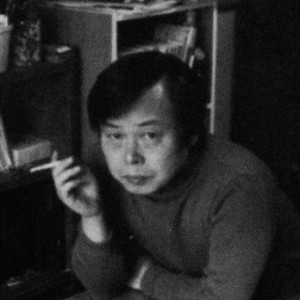書評
『庭のイングランド―風景の記号学と英国近代史』(名古屋大学出版会)
庭のたのしみ
ルネサンス期に、中世の「囲われた庭」から自然を幾何学的に理念化する整形式庭園へと開かれた庭はイギリスにも入り込んで、エリザベス朝の大庭園もおおむねルネサンス式の「歓楽の庭」であった。けれども十七世紀に入ると、この幾何学的、規則的な庭の人工性は、徐々に自然の不規則性の報復に直面して崩壊しはじめる。造園における自然と人工の対立が他のどこでより緊張をはらんで展開された国は、イギリスであった。ここでは多くの詩人や文人がみずから造園家であり、すくなくとも庭園論や風景詩の制作に無縁ではいられなかったからだ。のみならずイギリスでこそ「庭とは政治的なもの」であった。そうしてとりわけ十七世紀に、庭は政治史の記号として徹底した。前著に『マーヴェルの庭』のある英文学者の著者は、スペンサー、ベイコン、ベン・ジョンソン、マーヴェル、ミルトン、ポープ、アディソンのような鋒々たる大家の詩と庭園論を博捜して、十七世紀と英詩と政治史の上に庭が記号としてどのように対応していたかを、明快に説きあかすのである。
イギリスにおいて庭がとりわけ政治的なメタファーとなるのは、清教徒革命期である。主としてルネサンス整形式庭園を範とした、王党派土地貴族たちのあでやかな「歓楽の庭」は、自然を労働と生産の場と考えた清教徒たちの手によって、現実にも理念の上でも、むざんに破壊されてしまう。
これ以来、庭は不規則に、自然にさからわぬ形に設計されるが、同時にこれまで動かなかった森が動き出す。とはつまり、森から伐材した木で造った船団が大西洋の彼方のアメリカへ達し、そこで新たな風景論の展望をくりひろげるのである。
著者は、王党派の庭園観と清教徒の庭園観の分水嶺をマーヴェルの詩『アプルトン屋敷』に、後者の全面的展開をミルトンの『失楽園』に見て、さらにミルトンの後裔としてのロマン主義の風景詩を遠望するところでひとまず筆をおく。
ちなみに本書以後の英国風景詩の内面化してゆく足どりは、ワーズワースからペイター、パウンドにいたるまでを論じた富士川義之の近著『風景の詩学』(白水社)にくわしく、また小冊子ながら、景観工学の側面から、風景がふたたび「政治的なもの」となるにいたった現代の問題性をするどく提起した中村良夫『風景学入門』を併読すれば、今日の庭園=風景論の水準を概観することができる。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1983年9月5日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする