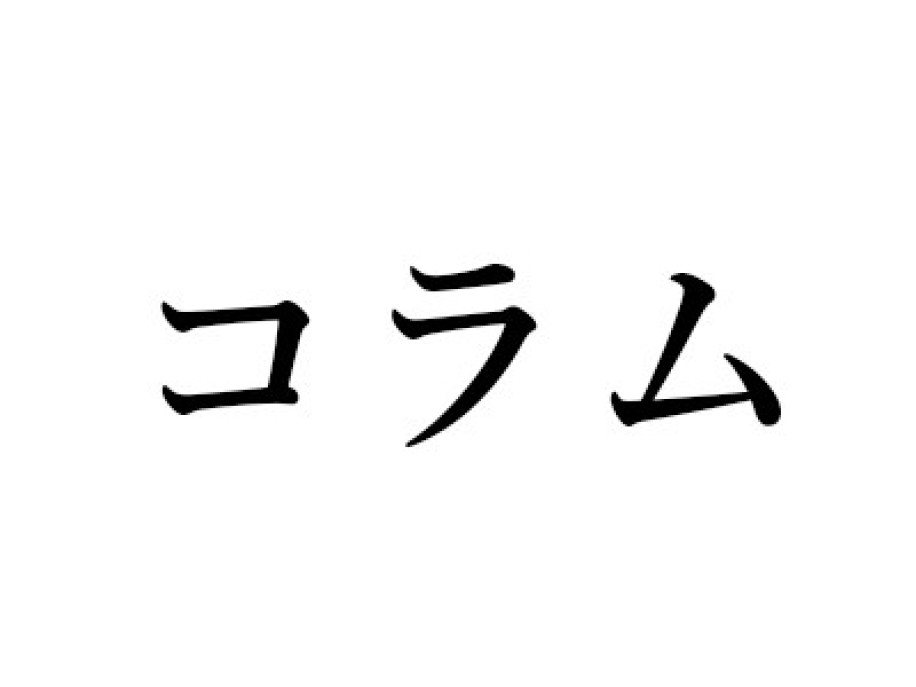書評
『朝と夕』(国書刊行会)
生から死までを静かに鮮烈に捉える
この秋、昨年のノーベル文学賞受賞者ヨン・フォッセによる中篇小説の邦訳が立て続けに刊行された。フォッセの代表的長編ともゆるやかな繋がりをもつ中篇三編を収めた『三部作【トリロギーエン】』(岡本健志、安藤佳子訳、早川書房)と、これから紹介する『朝と夕』である。フォッセは二〇二二年にインタビューでこのように述べている。「私はこの十五年ほど、劇作に集中してきたので、<中略>長いセンテンスを書きたくなったのです。一瞬一瞬をじっくり味わえる、“スロー・プロウズ”(ゆっくりした散文)とわたしが呼んでいるものを……書くというのは、耳を傾ける行為なのです」
「スロー・プロウズ」「書くというのは、耳を傾ける行為」という言葉は、まさにフォッセの文学観をよく表しているだろう。『朝と夕』の訳者伊達朱実によれば、フォッセは「物語はすでに出来上がっていて、自分はただ耳を澄ませて物語を聴きとり、消えてしまう前に急いで書きつけているだけだ」と考えているという。
本作は、ある男性の誕生の瞬間からその生がべつな次元に移行していく――すなわち死――ひとときを静かに、しかし鮮烈に捉えたヨン・フォッセの精髄だ。
漁師の息子ヨハネスの生誕(固有名詞には聖書への暗示が鏤(ちりば)められている)を描く短い第一部の後、第二部でははるかに時が飛んで、愛する妻のアーナを喪い、寡夫となって独居するヨハネスの老境の暮らしが語られる。
ヨハネスはこのように生まれた。「腕が痛い、脚が痛い、どこも痛い、指を固く握 イ ア り オー しめ、絶え間ない エ せせらぎの音 エ ア オ ア<中略>遠くから光が差し込み、ここはどこか別の場所」
こうして生まれたヨハネスは――第二部の回顧によれば――結婚し七人の子とたくさんの孫に恵まれた。妻のアーナと親友のペーテルには先立たれたが、最愛の末娘シグネはすぐ近所に住んでいて頻繁に訪ねてきてくれる。
朝は毎日同じように訪れる。煙草(たばこ)を巻き、コーヒーを沸かし、山羊のチーズをのせたパンを食べる。そして、少し弱音を吐く。そんな朝があるとき様相を変えた。起きても節々が痛くない。体が軽い。海辺を散歩するヨハネスはペーテルに出会い、声をかける。二人は思い出を語りあう。彼らは長年互いの髪を切りあう仲だった。
言葉にしないまま表現する手法がすばらしいと訳者は指摘する。たとえば、ヨハネスが失恋したアンナのその後は不明だ。でも、第二部のある一語によって彼女が独り身のまま過ごしてきたことがわかる。シグネの娘がマグダという名であることにも思いが込められているだろう。ヨハネスの祖父が愛慕した姉の名をその玄孫(やしゃご)につけたことになる。
フォッセ独特のピリオドのない文章。それは人の魂と意識に終わりはなく、ただ、自己と他者の境界のない「別の場所」へと融解していくことを表しているかのようだ。第二部は命尽きる直前の男が見た走馬灯をゆっくりと引き延ばしたものなのかもしれない。
明るい寂寥が降り積もっていく。他者のものとしてしか経験できない死を生者の目で見つめ、最後の最後に他者の視点へ転換する技法もじつに鮮やかである。
ALL REVIEWSをフォローする