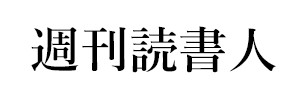書評
『ジェンダーの社会学―女たち/男たちの世界』(新曜社)
ひからびた社会学にうんざりの、全国の学生諸君お待ちかねのテキストの、ついに登場だ。快挙である。これを読めなかった私の学生時代が口惜しい。
《社会学入門でもあり、読物としても面白い本。普通のごくささいな日常生活から、社会とは世界とは何かを考えられたら、きっともっと社会学が面白くなるだろう。……二転三転した議論の末、私たちは大冒険に乗り出した。「ジェンダーだけをモチーフにして、社会学の入門書を書いてみよう」》ー著者を代表して江原由美子さんは、こんなふうにのべているが、その思いは半ば以上達せられていると言えよう。
ジェンダーとは《生物学的な性別……と区別された、社会 ー 文化的性別》のこと。なおかつ、「ジェンダーの社会学」は、女性の視点にこだわるフェミニズムと一線を画す。《本当は、男性も女性も同じくらいにジェンダーに「囚われて」いる》のだから。本書は男女を問わず、自分の足もとから社会と人生を見つめ直すための、格好の水先案内だ。
さて、江原さんはじめ六人の執筆者が分担するのは、日常生活/政治社会/家族/労働/世界社会/感性リアリティ、の各章。社会学を学び始めたばかりの若い学生諸君が、自分の経験の範囲内で無理なく理解できるテーマを、ゆったりとカヴァーしている。文章の語り口も、著者からの個人的メッセージとして、読者に届くよう配慮してある。
この本で出色なのは、これまでの常識をくつがえし、知識は知識にすぎないと、コラムに追いやってしまったことだ。そうしたコラムや、キー・ワード、研究ノートといった囲み記事だけ拾い読みしても、ちゃんといまの社会学の輪郭が掴めるようになっている。そのかわりに本文では、社会学の考え方(リーズニング)を分かりやすく噛んで含めるように紹介してある。それも、集中力の限度を越えないように、数ページずつのブロックに区切って。参考文献、図表のあげ方も神経が行きとどいているうえに、柴門ふみさんのイラストが、若々しい感覚を随所にちりばめて、ページを繰るのがなおのこと楽しい。
――という狙い線が、手にとるようにわかって、それに共鳴した。実際の出来ばえを率直に言うと、各章ごとにばらつきがあり、全体の調整も必ずしもうまくいっていなくて、だいぶ改善の余地がありそうである。まだ工事中、ということだろう。
だが、それはそれとして、著者たちの挑戦の意気ごみは、やはり読者にもひしひしと伝わるはずだ。特に冒頭の数十ページは、映像的な手法が成功して、作品としても優れており一気に読ませる。本書がきっかけとなって社会学を見直す人びとの輪が広がり、やがて中級の読み物、一線の研究書へと、手が伸びていってくれればいいなあと、楽しい夢をみたくなる。
というわけで、教科書として今のところ、本書は他の追随を許さないが、これ一冊ですむかという問題もある。テーマや切り口の点で、社会学全体からみてバランスを欠いているのは確かだ。それが気になる人もいるだろうが、総花的に何でも取り上げ、著者の顔が見えないこれまでの教科書にくらべれば、断然こちらをとるのが正しい、と思う。ただ、本書を補う意味でも、別な方向へのかたよりをもった教科書が、真似でもいいからあと何冊か出てほしいのだが。
【この書評が収録されている書籍】
《社会学入門でもあり、読物としても面白い本。普通のごくささいな日常生活から、社会とは世界とは何かを考えられたら、きっともっと社会学が面白くなるだろう。……二転三転した議論の末、私たちは大冒険に乗り出した。「ジェンダーだけをモチーフにして、社会学の入門書を書いてみよう」》ー著者を代表して江原由美子さんは、こんなふうにのべているが、その思いは半ば以上達せられていると言えよう。
ジェンダーとは《生物学的な性別……と区別された、社会 ー 文化的性別》のこと。なおかつ、「ジェンダーの社会学」は、女性の視点にこだわるフェミニズムと一線を画す。《本当は、男性も女性も同じくらいにジェンダーに「囚われて」いる》のだから。本書は男女を問わず、自分の足もとから社会と人生を見つめ直すための、格好の水先案内だ。
さて、江原さんはじめ六人の執筆者が分担するのは、日常生活/政治社会/家族/労働/世界社会/感性リアリティ、の各章。社会学を学び始めたばかりの若い学生諸君が、自分の経験の範囲内で無理なく理解できるテーマを、ゆったりとカヴァーしている。文章の語り口も、著者からの個人的メッセージとして、読者に届くよう配慮してある。
この本で出色なのは、これまでの常識をくつがえし、知識は知識にすぎないと、コラムに追いやってしまったことだ。そうしたコラムや、キー・ワード、研究ノートといった囲み記事だけ拾い読みしても、ちゃんといまの社会学の輪郭が掴めるようになっている。そのかわりに本文では、社会学の考え方(リーズニング)を分かりやすく噛んで含めるように紹介してある。それも、集中力の限度を越えないように、数ページずつのブロックに区切って。参考文献、図表のあげ方も神経が行きとどいているうえに、柴門ふみさんのイラストが、若々しい感覚を随所にちりばめて、ページを繰るのがなおのこと楽しい。
――という狙い線が、手にとるようにわかって、それに共鳴した。実際の出来ばえを率直に言うと、各章ごとにばらつきがあり、全体の調整も必ずしもうまくいっていなくて、だいぶ改善の余地がありそうである。まだ工事中、ということだろう。
だが、それはそれとして、著者たちの挑戦の意気ごみは、やはり読者にもひしひしと伝わるはずだ。特に冒頭の数十ページは、映像的な手法が成功して、作品としても優れており一気に読ませる。本書がきっかけとなって社会学を見直す人びとの輪が広がり、やがて中級の読み物、一線の研究書へと、手が伸びていってくれればいいなあと、楽しい夢をみたくなる。
というわけで、教科書として今のところ、本書は他の追随を許さないが、これ一冊ですむかという問題もある。テーマや切り口の点で、社会学全体からみてバランスを欠いているのは確かだ。それが気になる人もいるだろうが、総花的に何でも取り上げ、著者の顔が見えないこれまでの教科書にくらべれば、断然こちらをとるのが正しい、と思う。ただ、本書を補う意味でも、別な方向へのかたよりをもった教科書が、真似でもいいからあと何冊か出てほしいのだが。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする