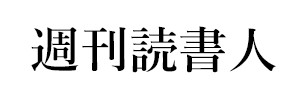書評
『近代家族とフェミニズム』(勁草書房)
読後に充実した余韻を残す一冊。慎重で繊細、なおかつ大胆な著者の思索の足取りが、とりわけ快い。社会学に好著の多かった一九八九年の、だめ押しの収穫が届けられた。
本書は落合恵美子の、最初の著書である。ここ五年来書きためられた大小二十六篇の文章がまとまった。論文集ながら、著者も自負する通り、モチーフがきわめて一貫している。わが国フェミニズムのもっとも良質な成果を、ここにみる思いがする。
「Ⅰ 近代家族の誕生と終焉」、「Ⅱ フェミニズムの歴史社会学」、それに、折々の時評を集めた「Ⅲ 現代を読む」の三部構成。学術論文然としたものも混じっているので、初めての読者は、巻末の「お産と社会学とわたし」から読むことを勧めたい。本書のモチーフが育まれる路程が、著者個人の生活の息吹きとともに、驚くほどの率直さで語られている。
著者の強みは、「出産」という具体的な素材を踏まえていることだ。東北の農村で、明治末から半世紀にわたり産婆を開業した女性をたまたま祖母とする著者は、彼女の聞取り調査を柱に、「産の社会史」を執筆。出産をとりまく女性と家族のネットワークが、わが国では江戸~現代にかけて、大きく三段階に変遷する事実を明らかにした。それを象徴するのが、民俗産婆/近代的産婆/医師、である。続けて、アナール学派の業績にも検討の手を広げ、ヨーロッパでもほぼこれに対応する変遷が見出されるとした。
ここから浮かびあがるのが、近代家族である。著者の整理によれば、近代家族は、①愛情の重視、②子供中心主義、③性別分業、など八つの特徴を有し、二百年ほど前に姿を現した。これを「近代」家族とよぶのは、近代を帰結する大きな社会変動そのものが、それを生み出したからだ。その根本は、家内領域と公共領域が分離し、同時生成したこと。近代家族は《近代市場にその参加者である近代的個人を供給する装置》で、それを近代国家が調整する。《近代社会は……市場、家族、国家の三者の連関として構成されている》
近代家族のあり方は歴史的なものなのに、およそ家族や男女の性別をイメージしようとすると、われわれの無意識の前提になってしまう。それなら、フェミニズム(を含む近代思想)も、たかだかそうした前提に立脚するものだと捉え直す、フェミニズムの歴史社会学(ないし知識社会学)を構想すべきではないか。著者は、そうしたモチーフから、フェミニズムと近代との関係にメスを入れていく。
かつての正統マルクス主義や、オートナー派女性人類学、マルクス主義フェミニズムなど、近代社会を批判するさまざまな立場が、実はみな近代の内部に足場を置いているというのが、著者の指摘である。フェミニズムは、近代とともにある。すべてのフェミニズムは、家内領域と公共領域の分離、つまり近代の成立を前提に、後者(市場)の原則 ―平等主義規範でもって、前者に置かれた女性の被差別状態を告発する、という構図をもたざるをえない。そのため、近代を離脱するプログラムをもつこともできない。
平たく「フェミニズムには展望がない」とも読めるこの結論は、だが、女性の可能性をもっとも貪欲に追い求める道に通じる。「女」に近代が与えたあらゆる意味あいや制約を取り除こうとする、冒険。「女性の社会史」を掲げる著者は、フェミニズムであるかないかのあわいで、反近代でない脱近代の方向に、「なしくずしの解放」を歩み始めた。その前途を祝したい。
【この書評が収録されている書籍】
本書は落合恵美子の、最初の著書である。ここ五年来書きためられた大小二十六篇の文章がまとまった。論文集ながら、著者も自負する通り、モチーフがきわめて一貫している。わが国フェミニズムのもっとも良質な成果を、ここにみる思いがする。
「Ⅰ 近代家族の誕生と終焉」、「Ⅱ フェミニズムの歴史社会学」、それに、折々の時評を集めた「Ⅲ 現代を読む」の三部構成。学術論文然としたものも混じっているので、初めての読者は、巻末の「お産と社会学とわたし」から読むことを勧めたい。本書のモチーフが育まれる路程が、著者個人の生活の息吹きとともに、驚くほどの率直さで語られている。
著者の強みは、「出産」という具体的な素材を踏まえていることだ。東北の農村で、明治末から半世紀にわたり産婆を開業した女性をたまたま祖母とする著者は、彼女の聞取り調査を柱に、「産の社会史」を執筆。出産をとりまく女性と家族のネットワークが、わが国では江戸~現代にかけて、大きく三段階に変遷する事実を明らかにした。それを象徴するのが、民俗産婆/近代的産婆/医師、である。続けて、アナール学派の業績にも検討の手を広げ、ヨーロッパでもほぼこれに対応する変遷が見出されるとした。
ここから浮かびあがるのが、近代家族である。著者の整理によれば、近代家族は、①愛情の重視、②子供中心主義、③性別分業、など八つの特徴を有し、二百年ほど前に姿を現した。これを「近代」家族とよぶのは、近代を帰結する大きな社会変動そのものが、それを生み出したからだ。その根本は、家内領域と公共領域が分離し、同時生成したこと。近代家族は《近代市場にその参加者である近代的個人を供給する装置》で、それを近代国家が調整する。《近代社会は……市場、家族、国家の三者の連関として構成されている》
近代家族のあり方は歴史的なものなのに、およそ家族や男女の性別をイメージしようとすると、われわれの無意識の前提になってしまう。それなら、フェミニズム(を含む近代思想)も、たかだかそうした前提に立脚するものだと捉え直す、フェミニズムの歴史社会学(ないし知識社会学)を構想すべきではないか。著者は、そうしたモチーフから、フェミニズムと近代との関係にメスを入れていく。
かつての正統マルクス主義や、オートナー派女性人類学、マルクス主義フェミニズムなど、近代社会を批判するさまざまな立場が、実はみな近代の内部に足場を置いているというのが、著者の指摘である。フェミニズムは、近代とともにある。すべてのフェミニズムは、家内領域と公共領域の分離、つまり近代の成立を前提に、後者(市場)の原則 ―平等主義規範でもって、前者に置かれた女性の被差別状態を告発する、という構図をもたざるをえない。そのため、近代を離脱するプログラムをもつこともできない。
平たく「フェミニズムには展望がない」とも読めるこの結論は、だが、女性の可能性をもっとも貪欲に追い求める道に通じる。「女」に近代が与えたあらゆる意味あいや制約を取り除こうとする、冒険。「女性の社会史」を掲げる著者は、フェミニズムであるかないかのあわいで、反近代でない脱近代の方向に、「なしくずしの解放」を歩み始めた。その前途を祝したい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする