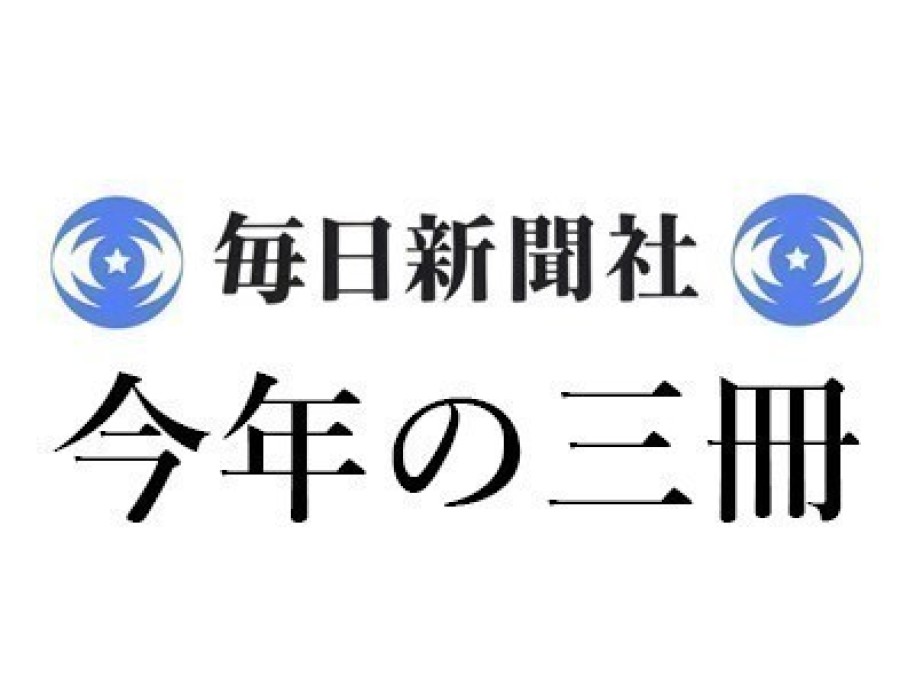書評
『論理的思考とは何か』(岩波書店)
目的で手法を変える、脱固定概念
論理と論理的思考は別ものである。この発見から拡がる世界。前向きにモデルを構築していく。発端は著者のアメリカ留学だ。エッセイを何回書き直しても突き返される。英語のせいではないようだ。思い切って順番を入れ換え結論を先にしてみたら、いきなり高評価になった。そうか、エッセイにはスタイルがあるのだ!
こうして著者は、日米の作文教育の違いに興味をもつ。それをテーマに学位論文もまとめた。何を論理的と考えるかは、文化によって違う。まず結論を書く/それを裏付ける実例や論拠を列挙/最後にもう一度念押し。そんなアメリカ流文章法が世界を席捲しているが、それが絶対ではないのだ。
論理とは何か。アリストテレスの論理学が完璧すぎて、二千年以上も唯一のお手本だった。排中律や三段論法。これが論理で、世界でひとつだけと誰もが思った。
論理学は、「そして/または」「すべて」など用語が独特だ。日常語で論理を語るには工夫しないと。アメリカ流のエッセイのスタイルもそうした工夫の産物である。
でもほかに違ったスタイルもあることに、著者は注目する。フランスやイランや日本の作文だ。そうしたスタイルでものを考えなさいと、社会が要請している。
本書の大事な主張をまとめてみると、次の二点になるだろう。
第一に、世界には少なくとも四通りの違った論理的思考のパターンがある。アメリカのエッセイ/フランスのディセルタシオン(バカロレア=高校卒業試験で出題される哲学の自由作文)/イランのエンシャー(小中高で学ぶ課題作文)/感想文(日本の小中高の作文)、の四つである。それぞれ、結論に向かって一直線/弁証法で正・反・合と揺れ動く/権威ある根拠から正しい結論に収束/時系列に従って体験と感想をのべる、のような構成になっている。
第二に、この作文の四つのパターンが、人間の四つの活動領域にそれぞれ対応している。アメリカのエッセイは経済/フランスのディセルタシオンは政治/イランのエンシャーは法律/日本の感想文は社会、のロジックを体現している。経済は利潤の極大、政治は意見の違う人びとの合意形成、法律は正しい原則の適用、社会は理解と共感の醸成。目的が違うから論理的思考も異なってくるのだ。
≪論理的思考は目的に応じて形を変えて存在する≫。本書の重要な結論である。アメリカ流エッセイだけが論理的なのではない。相手のことを思いやる能力を培う日本の論理的思考にも、国際社会での出番はある。なぜならどんな国も、政治/経済/法律/社会、の組み合わせで動いているから。グローバル化に怖じ気づいてきた日本人が勇気をもらえる結論だ。
著者・渡邉雅子氏のモデルは大胆で、すぐ役に立ちそうだ。あえて言えば、この四つのほかにもまだ論理的思考がありそうに思う。インドの文明。中国の文明。どちらもテキストと格闘してきた分厚い歴史がある。これらの社会でどう作文が教えられ、社会のどんな要請に応えているのかわかれば、グローバル世界の多様性を真正面から組み止められそうだ。
論理的に考えているつもりで、決まったパターンを使い回して作文しているだけのあなた、ちょっとは反省しなさい。きついお灸をすえる痛快至極な書物である。
ALL REVIEWSをフォローする