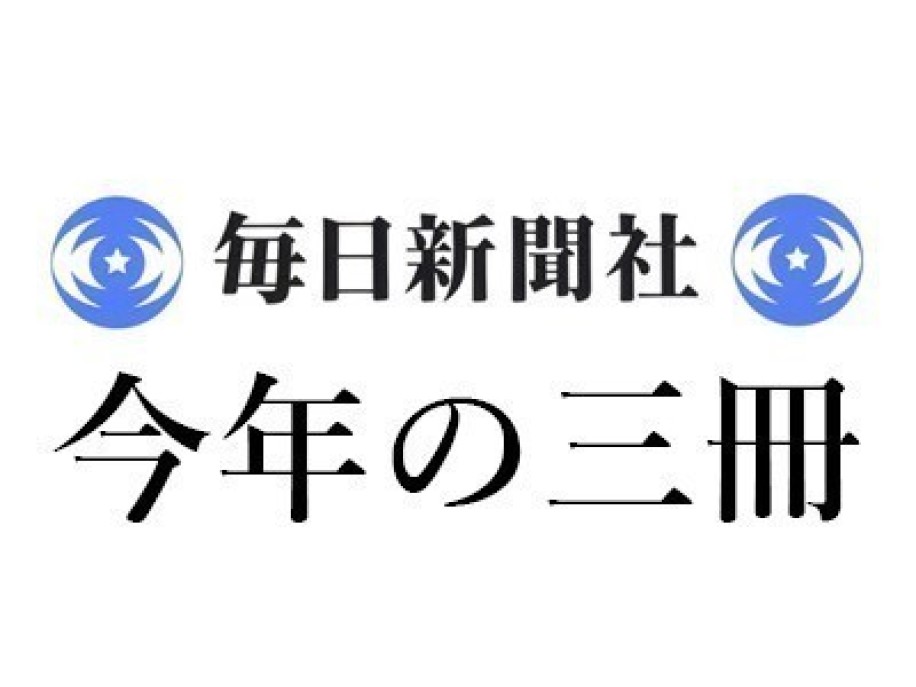書評
『本の雑誌血風録』(朝日新聞出版)
珍しい零細企業小説、反会社人への福音書
これはもう書評しなくても読まれる本だろう。でもやっぱり面白い。初々しい。私は「本の雑誌」の七、八号目からの読者である。一九七七年、セクハラと深夜残業の多い会社の灰色の事務機器の陰でこっそりよむこの雑誌が生き延びる糧であった。「文芸春秋全頁読破」「感動的ホンバコの作り方」といった企画に驚きもしたが、じつは書評よりも彼ら自身を「読んで」いたのだった。
ケンカっぱやい業界誌編集長椎名、晴読雨読のために会社をやめる目黒、あどけないイラストレーター沢野、三ケ月章「民事訴訟法」が生涯の感動本という弁護士木村。ごくフツーの四人がごくフツーに知り合い「本好き共和国」をつくり、雑誌創刊を企てる。
ようやくできた創刊号は五百部。“なんと”というか“たった”というか。作るより売る方が大変である。納品書なるものは知らないし、原価計算をしてないため売れば売るほど赤字になる。レジの前で客の切れるのを待って委託の交渉をする。毎日が発見だ。
これは高校文芸部的近代自我煩悶(はんもん)的文人墨客的小説ではない。その対極のところに立って、目を輝かせて生きる気分が伝わってくる。雑誌作りだけでなく「三びきのやぎのがらがらどん」を幼い娘に読んでやり、外国取材の前に水さかずきならぬ、狭山湖に家族ハイキングに出かける若い家族のかわいらしさ。ポケットから蛇を出す元上司とか、どーんと行きましょうが口癖のガニマタ編集者とかワキ役も多彩である。訳の分からない雑誌に創刊号から広告を出し続けたネクタイ問屋「三松商事」さんもえらい。
不満は二つある。あの群ようこ氏が不機嫌なお姉さんという印象なのは残念だ。やはり女の入りこむスキのないユートピアだったのだろうか。後半、注文が舞い込み著者が作家として成功していくくだりはなんだかつまんない。夢を共有する仲間が見えないからか。
ではあるが、これはめったにない零細企業小説。ドブネズミスーツ、ラッシュアワー、つきあい酒、上司の悪口、要するに“会社色”に染まりたくないひとには福音の書。そしてこの社会に小さな自由の風穴を開ける方法を詳しく描いた、実録かつ「実用」小説である。
【文庫版】
朝日新聞 1997年6月22日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする