書評
『ゲーデル、エッシャー、バッハ―あるいは不思議の環 20周年記念版』(白揚社)
ついでに疑問手をひとつ指摘しておこう。「音程拡大によるカノン」において、アキレスと亀が俳句を論じる次のくだり。
Tortoise: Such compressed poems with seventeen syllables can't have much meaning...
亀 そんなに圧縮された十七音節の詩なんて、あまり意味をもちえないんじゃないか……。
Achilles: Meaning lies as much in the mind of reader as in the haiku.
アキレス 意味は読者の心のなかにあるんだよ。ハイクのなかだけじゃなく。
トリックは、poems--with; syllables--can't; much--in; reader--as の四組で、それぞれの単語の間にあるスペースが通常より少し広いところに隠されている。すなわち、この二つの台詞はそのスペースで区切ればどちらも五・七・五音節のかたまりとなり、英語で書かれた俳句に変化する。従ってここは俳句で訳す一手であった。柳瀬名人にしては珍しい見落としの失着ではなかろうか。
翻訳談義はこのへんで終わって、『金、銀、銅』における奇妙な一事実について付記しておく。それは、巻末に付けられた詳細な参考文献の中の一項目(Hofstadter, Douglas R. Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. New York: Basic Books. 1979)なる書物についてである。邦訳があるとのことで、訳出されている解説を引用しよう。
ダクラス・R・ホフスタッター『ゲーテル、エッシャー、バッハ――あるいは不思議の環』(野崎昭弘・はやしはじめ・柳瀬尚紀訳、白揚社一九八五)とてつもないごたまぜで、長たらしくゴチャゴチャしているが、私の書物にきわめてよく似ている。間接的自己言及の好例を含む。特におもしろいのは、行き届いた注釈つきの参考文献の中に、『ゲーテル……』と同型だが実在しない一冊の本が載っている点である。
すでにお気づきとは思うが、白揚社などという出版社は存在せず、ホフスタッターとはゲブスタッターのもじりであり、Gödel, Escher, Bach という書名のアクロスティックGEBはゲブスタッターその人を指しているから、これは彼が創作した架空の著者による架空の書物であることは誰にでもわかる。しかし、最後の部分で言及されている、『ゲーデル、エッシャー、バッハ』なる書物の参考文献に載っている「一冊の本」とは『金、銀、銅』に他ならず、これは「実在しない」と述べられているではないか。つまり実在する書物『金、銀、銅』が自らを実在しないと主張しているわけで、これこそクレタ島の嘘つきの逆説、自己言及がはらむ矛盾である。自らの亀頭を口にくわえた伝説上の亀(うろおぼえでその名前が思い出せない。ウロオボエスだったか、それともウロボルヘス?)に似て、これは亀ならずとも大いに亀頭を悩ます問題だ。
【事務局注:本書評対象は20周年版ではなく初版の『GEB』】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア

翻訳の世界 1985年8月
ALL REVIEWSをフォローする







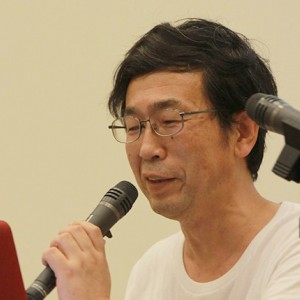


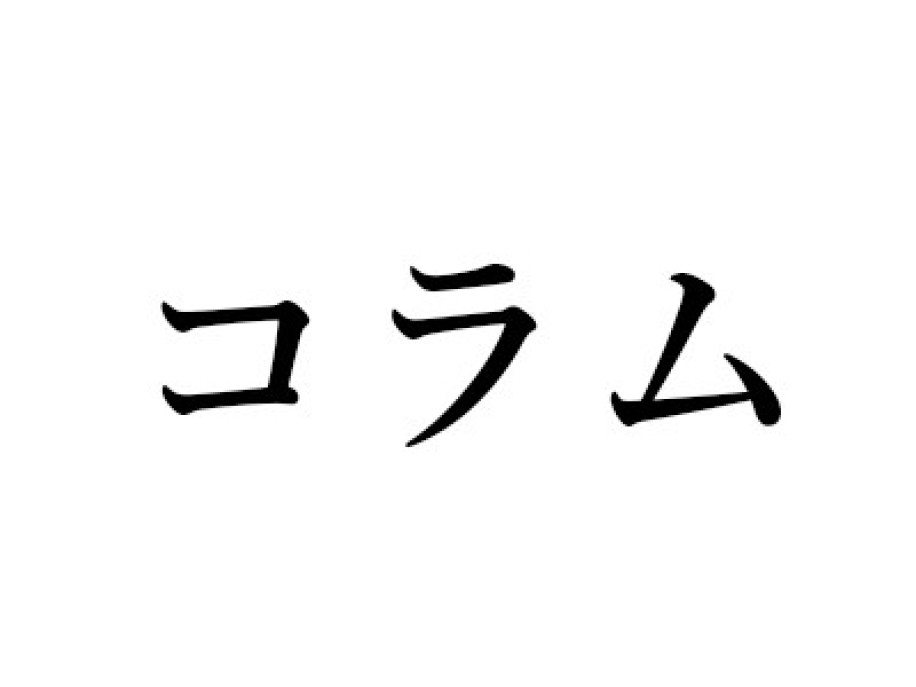





![中村桂子「2023年 この3冊」毎日新聞|<1>西田洋平『人間非機械論 サイバネティクスが開く未来』(講談社選書メチエ)、<2>中沢新一『カイエ・ソバージュ[完全版]』(講談社選書メチエ)、<3>ロビン・ダンバー『宗教の起源 私たちにはなぜ<神>が必要だったのか(白揚社)](/api/image/crop/916x687/images/upload/2025/03/e172f187e73582fd5102cba2655da740.jpg)

























