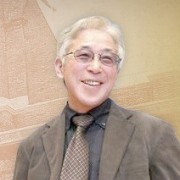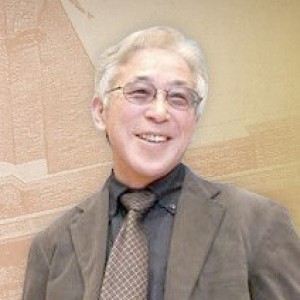書評
『ビザンツ文人伝:言葉で戦った男たちの矜持と憂愁』(白水社)
古典古代の精神息づく人間模様の機微
どんなに正確にバットをふっても、球から大きく離れていたら様にならない。同様に、問いかけが適切でなければ、筋の通った応答でも味気ない。五世紀後半に解体した西ローマ帝国にならって、その後千年もつづいた東ローマ帝国(ビザンツ帝国)はいかにして衰退したか、それを問うのはいかがなものだろうか。領土が縮小し国力が弱体化しても、「なぜ存続できたのか」こそふさわしい問いかけではないだろうか(ジョナサン・ハリス『ビザンツ帝国 生存戦略の一千年』参照)。古代帝国の衰弱にともない、西欧では知識人の多くは教会関係者に偏っていた感がある。だが、ビザンツ帝国の君臨する東欧では世俗の文人層が分厚かったらしい。しかも、伝統ある古典の教養にふれながら、歴史、詩歌、書簡などを語るのだ。
これらの教養人は、皇帝および周辺の権力者に仕えながら、しばしば賛辞を声高らかに述べて式典をもりあげる文人たちであった。絶大な権力者や武勲で飾られた将軍のごとく同時代の史書でとりあげられることはないが、脇役として喜怒哀楽にあふれる生身の人間がいた。本書はこれら等身大の文人たちを追う評伝であり、思いがけないビザンツ史の裏面が浮き上がってくる。
九世紀半ば、俗人のフォティオスがコンスタンティノープル総主教の地位に就いた。権謀術数の世界に放り込まれた学者肌の総主教がどれほど当惑したか、想像にかたくない。圧倒的な学識にあふれても、敵意ある教会人には異教かぶれにすぎなかった。しかも、教会会議で教皇ニコラウス一世を非難したことから、ローマ教会との対立が決定的になり、やがて解任される。十年にわたる捲土(けんど)重来の日々が過ぎ、総主教の座に復帰するが、なにぶんにも老齢であった。
十一世紀前半、ビザンツ帝国は、空前の平和と繁栄を迎えようとしていた。そのころ古典文学の深い教養をもち、多種多様な文章をやりとりしながら交流する知的エリート集団が幅をきかせていた。クリストフォロスなる詩人は、さまざまな韻律を駆使して、多様な題材の世俗詩を残している。盛大なパレードの沿道は見物人の人波で埋めつくされ、喧騒(けんそう)のなかで目撃した出来事や人物などが描き出される。
ビザンツの文人を語るとすれば、一〇一八年生まれの多芸多才なプセルロスにふれないわけにはいかないだろう。権謀術数の宮廷社会で相次ぐ帝位交代にもまれながらも巧みに政権を渡り歩いた知識人であるが、その著作『年代記』は宮廷に集う人々の人間模様の機微に立ち入り、心理状態まで掘り下げる。この文人の虚栄心、権勢欲、俗物ぶりを嫌う輩(やから)もいるが、それは広大無辺な人格の一面にすぎないという。
十二世紀後半の偉大な古典学者にして、テサロニケ府主教にもなったエウスタティオスは、貧相な風貌ながらも「内に光輝を抱く教育者、かつ多くの業績を挙げた先駆的な人物」であったという。だが、ノルマン軍の侵略で多大な被害を蒙(こうむ)ったテサロニケ市民を悪辣(あくらつ)な金銭欲に対する断罪と説いたのは、あまりにもデリカシーに欠けた。府主教とテサロニケ市民の不仲という不幸な晩年だったが、後世には聖人としてあがめられている。
十四世紀のコーラ修道院聖堂の壁面には、黄金の華麗なモザイクがあり、玉座のキリストに聖堂を捧げる創建者テオドロス・メトキテスの姿がある。彼は国政の権力闘争に身を削りながら、学業も怠らず、膨大な著作を残している。だが、やがて皇帝の権力闘争にまきこまれて、地方都市で流人として暮らすしかなかった。地上の富も権力も一切を失ったメトキテスの最後の望みは、自分の著作が忘却されず、将来にわたって人々に読み継がれることだった。
十五世紀に入るころ、すでにオスマン朝の軍勢に脅かされていたビザンツ帝国に、ひときわ奇矯(ききょう)な文人がいた。その変わり者ゲミストス・プレトンは、太古の賢人ゾロアスターにさかのぼる知を探究し、新プラトン主義の奥義を究め、古代ギリシアの神々をあがめる異教信仰の復興を図るなどという途方もない視野をもっていた。あまりにも多様であるために不可解きわまりない点が多いが、とりわけ、生前、教会から目立ったお咎(とが)めも受けなかったことは特筆される。
これらの文人たちの足跡をたどると、東欧世界にあっては、古代帝国の後退後も、古典古代の精神が息づいていたことが読みとられる。それが、唯一神のみに傾倒して排他的になった西欧世界と異なり、他者を同化して、その精神・技術を活用する生き方を身につけさせたと言えるのかもしれない。異質の他者を拒まずなじませる精神が多芸多才の文人たちに宿りつづけたところに、ビザンツ帝国が千年にわたって存続したことの一因があったのだろうか。
ともあれ、新しい境地を切り開くかのごとき歴史書が、日本のビザンツ史研究者のなかから現れたことは素直に喜ばしい快挙である。
ALL REVIEWSをフォローする