書評
『古都』(国書刊行会)
アナログ的な重ね塗り
一九四九年、国民党政府に従って台湾に渡った人々を外省人、戦前から台湾に住んでいた人々を本省人と呼ぶ。朱天心は、外省人の父と本省人の母の間に生まれ育ったいわゆる「外省人第二世代」に属し、血縁上の祖国である大陸をつねに架空の「故郷」として受けとめ、自己の拠って立つ場所をたえず探し求めなければならない「はざま」の世代の書き手である。本書には、表題作を含めて五篇の中短篇が収められている。香水の香りに自身の記憶とアイデンティティを重ねる男の彷徨を描いた「ハンガリー水」、ダイヤモンドを買うまでの主人公の心の動きと台北の歴史をかすかに同調させていく「ティファニーで朝食を」、自分が死ぬための準備をユーモラスに語る「ラ・マンチャの騎士」、執筆現場における作家の虚実を、諧謔(かいぎゃく)をこめて語る「ヴェニスに死す」。どの短篇にも、歴史を背負った現在との直接対決を軽やかに回避する上質のユーモアがある。最も完成度が高いのは、やはり「古都」だろう。この作品が書かれたのは九六年。本省人李登輝が選挙で総統に再選され、台湾の本土化すなわちナショナリズムの動きが台頭してきたころである。台湾語の復権、そして台湾の正史という「共同の記憶」の創設。
物語はそうした背景を取り込みながら、自己同一性を微妙にゆさぶる二人称単数による語りかけを用いて時空を混乱させていく。「あなた」と呼ばれる女性は、限りなく著者自身に近いようだ。
台北で過ごした彼女の記憶に娘の成長が、親友だったAとの双子のように親密なつきあいとあっけない別れが本歌ともいえる川端康成の「古都」の主人公たちと融合し、彼女にとって大切な台北の地図が日本占領下時代のそれに読み改められる。
記憶の消去でも入れ替えでもなく、羊皮紙を思わせるアナログ的な重ね塗りの痕跡を残すこと。本書が美しいだけの二都物語に収束しなかった理由は、そこにこそある。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
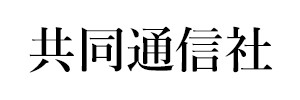
共同通信社 2000年8月
ALL REVIEWSをフォローする






































