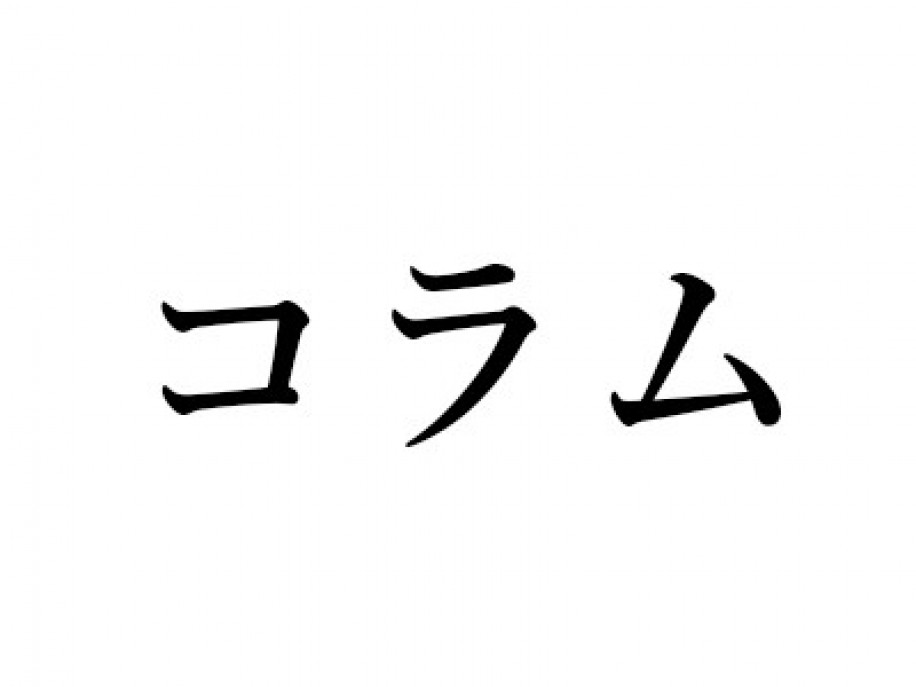書評
『花野』(講談社)
卵が尽きるとき
「ねえ、あなた人間の卵みたことある?」
「人間の卵?」
「排卵のときのタマゴよ」
「そんなもの、あるはずないでしょう」
「わたしはあるわ。排卵日のあと気をつけてみてると、柔らかくて白っぼくて小さな粒のようなものが、コロンと落ちてる」……
(村田喜代子『花野』講談社)
私はびっくりして、そのコロンとした粒がついていはしないか、下着をしらべたくなった。
遠山暁子は五十三歳、新興団地で暮らす何不自由ない専業主婦である。髪の半分は白くなった。鼻は高く目の大きい古典的な顔だち。品のいい、おっとりして、少々野暮な中年女性が、他の女たちのやや意地悪な目で語られていく。
のろくさくて仕事に向かない、またその必要もない暁子が、なぜ駅前のパートバンクへ現われ肉体労働をするのか、バーのお手伝いに応募してなったのか、不可解だからである。
海千山千のバーの経営者、白木多恵子は、世間知らずの童女のような暁子が、意外に決断が早く、さめた目を持っているのに気づき、得体の知れない女だ、と思う。人手が足りないので、暁子を即席ホステスに仕立てるため、白髪を染めるシーンが圧巻だ。
なんと太い真黒い毛だろうとわたしはおもった。掌の中でギシギシと、なにか強い生きもののような手応えをさせる……こんなにふてぶてしくて鋭い毛をはやしながら、人間は齢をとっていくのだろうか。
「花野」は秋の季語である。うららかな春の野ではない。人生の秋の茫々と風の吹く萩や薄の野を指す。更年期に入り、そして閉経する。個人差はあるにしても、そのとき女の体も心も激しく変わるらしい。その様相を、作者ならではの特異な感覚で描いた小説である。
閉経とは、「体の中で、遠くひろがる野面の果てに一つの都の崩れ落ちていく」ような感覚らしい。そのとき、夫や娘のために家をととのえ、充足していた主婦の心に、パアッと狼煙(のろし)が上がる。
その頃わたしはどこかへ行ききりになってしまいたいという、ふしぎな気持をつのらせていたのである。
家族を捨ててまで出奔しえない主人公は、昼間だけの「遠い世界」に旅立つ。それがパート放浪だったのである。
パート仲間の三十八歳の下園邦子は暁子に聞く。
「若さってどんなふうなものかしら」
「日射し、ににているとおもうわ・・・・・・だんだん遠ざかって行くの」
私も三十八歳(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1993年)。働きつづけて、ことし目と歯にガタが来た。変調の予感がある。
卵が尽きるとき、こんな喪失感があるものか。私は自分の「子宮という繁栄していた都」の落日もそう遠くないのを思ってギクリとした。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする