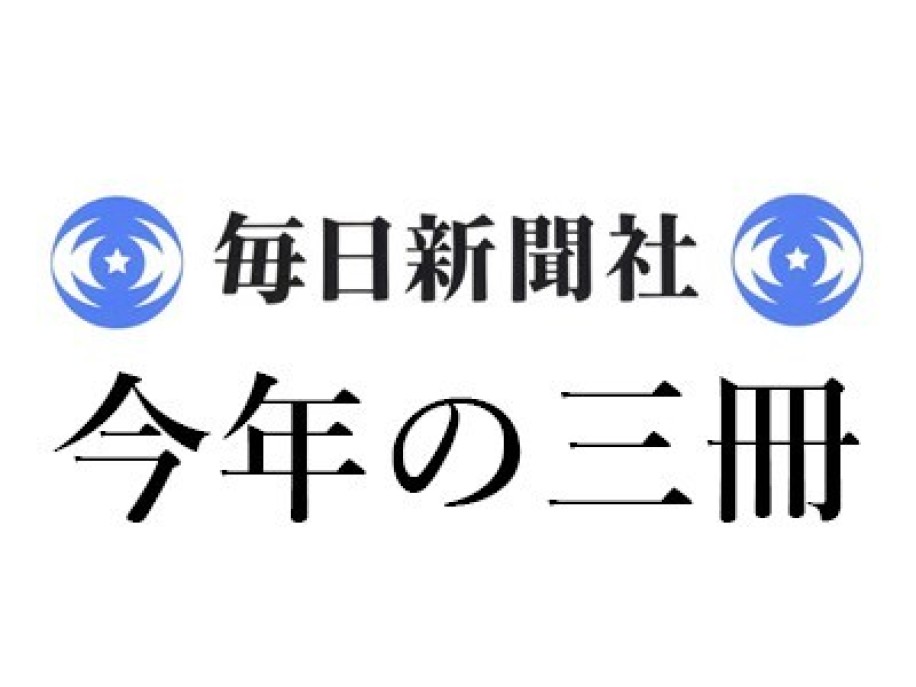書評
『初恋温泉』(集英社)
文学の力技と職人芸、そして効能あり
ああ温泉に行きたい。最後の頁を閉じてカレンダーの空き日を探した。本能が刺激されていた。記憶の中から、温泉での様々な場面がたち現われてきて、自分がオンナであったことを、はたと思い出した。そうなのだ、温泉とは自分が男であり女であることを気づかせてくれる、つきつけてくる、ついでにしみじみと日本人であることも確認させてくれる場所なのである。
本書の中では五組の男女が、日本各地の温泉に行き一夜を過ごす。熱海であったり青森の青荷温泉であったり、はたまた九州の黒川温泉であったり。その男女も、全く違う状況にある。
熱海の二人は、別れ話をしながらやってくる。決定的に別れなくてはならない理由は、見つからない。しかし、何かがズレているし、欠けている。
女は言う。
「幸せなときだけをいくらつないでも、幸せとは限らないのよ」。男には理解できない。パネルを上下左右にひとつずつずらして揃えるパズルのように、どうしても一箇所だけ隙間が出来る。隙間があるからパネルを動かすことが出来るのに、隙間があっては完成しない。
男女の会話も、だからいつも少しずつ的が外れている。え?と相手の言葉を問い返す、それがまた噛み合わないでズレる。相手に触れてはいるものの、微妙に方向がズレていくやりとりに、何とも言えない味がある。
ズレに乗じて別の意識が滑り込んでくる。嫉妬や怒りや愛惜などという色の濃い意識ではなく、淡く透明な隙間風がするりと入り込んできて、実は小説の主人公は、男や女ではなく、この透明な隙間風ではないかと思えてくる、これこそ吉田修一の“角度十八度の職人芸”なのである。
十八度について、もう少し説明が必要かもしれない。
たとえばお互い向き合っているはずの男女が、角度十八度分、どちらかがどちらかに対して体の向きを違えていれば、意識や言葉は、決してそのまま相手に投げ返されることはない。相手の体を擦って、あらぬ方向に逃げていく。同じ方向に向かって手を繋いで立っているカップルであっても、視線は微妙に――三十度分も大きくはないが十度以下でもない、つまり十八度程度――ズレている。
この十八度が、あざとくならず、品性ある文学を生み出すギリギリの角度で、読者が違和を感じることなく男女の心の行き違いを追体験できる限度なのかもしれない。
この角度を保つために費されている作者のエネルギーはかなりのものだろうし、“温泉に行く五組の男女の話”などという、そもそも“文学にならない確率九九%”の枠組の中で、力技で文学を作り出す体力気力も、これまた並大抵のものではないだろう。
よく喋る夫婦が白雪の舞うランプの灯りだけの温泉に行く。夫は、雪景色の中に入った瞬間に、すべての音が消えたような奇妙な感覚を味わう。
この夫婦、自分たちのことを“脇役夫婦”だと思っている。ドラマの中で脇役は、主役を盛り上げるために賑やかに振るまう役割りだからだ。それが何かの拍子で雪深いランプの宿に来てしまった。離れの部屋は襖一枚隔てて別のカップルが泊っている。隣のカップルは物静かだ。話し声ひとつ聞こえてこない。
することもなく早々と寝入ってしまったおかげで、早朝目が覚めてしまった夫は、露天風呂に行く。先客がいて、それは隣の部屋の男だった。彼は思わず話しかけるが、相手の反応がおかしい。隣のカップルは耳が聴えないのだと判り、動揺する。唯一、どんでん返しに近い仕組みか。
ガイドブック風に言えば、出会いと発見だろうが、この脇役夫婦が発見したものは、声を持たなくても静かに微笑み合っている男女の情愛ではなく、無音の暖かさだった。夫は部屋に戻ると、寝ぼけた声で喋り出そうとする妻の唇をやさしく押さえる。
夫婦はこの夜、饒舌な脇役カップルから、ひとつ上のランクに脱皮したのである。
温泉宿にはワケアリの男女が似合う。その通俗性をものともせず越えて行った作者は、最後に高校生の純情カップルを登場させる。いまどきは高校生が男女で温泉に一泊するのか、という大人たちの溜息はひとまず措いておいて、社会の仕組みにおずおずと手をのばし、何とかして欲望を叶えようとする若いカップルが初々しい。
バイトして貯めたお金で、彼女を温泉に連れ出し、一緒に家族風呂に入りたい。必死の背伸びと切実な肉体の願望が、まっすぐな微笑をさそう。この一作には“角度十八度”がない。作中人物たち同士もそうだが、読者もまたこの作品に対して、ズレなく向き合うことが出来る。心地良くて懐しい。
五つの温泉に五つの効能あり。どの湯も、読むだけで心身に浸透します。
ALL REVIEWSをフォローする