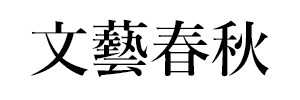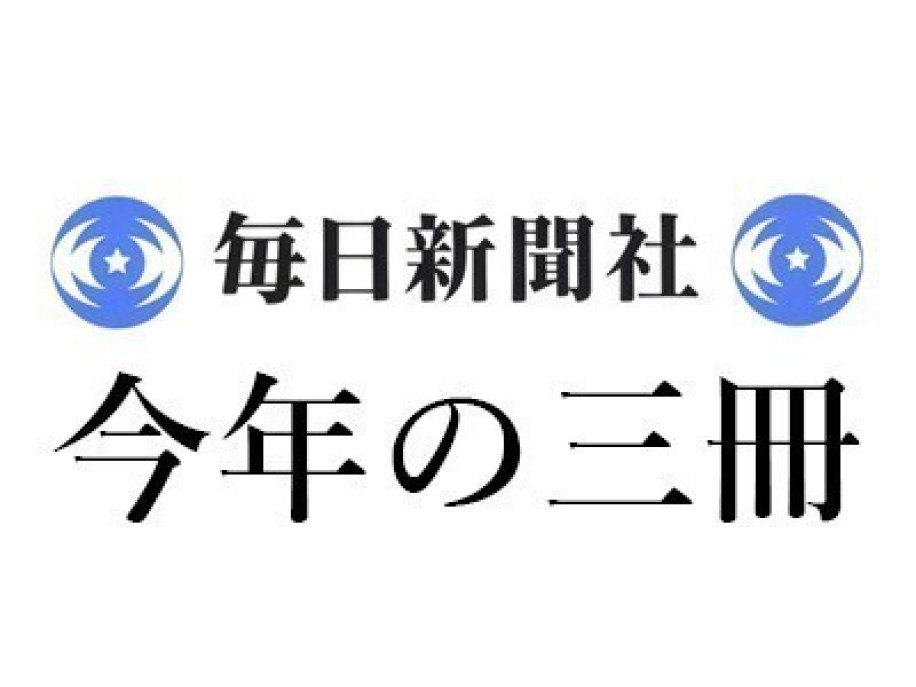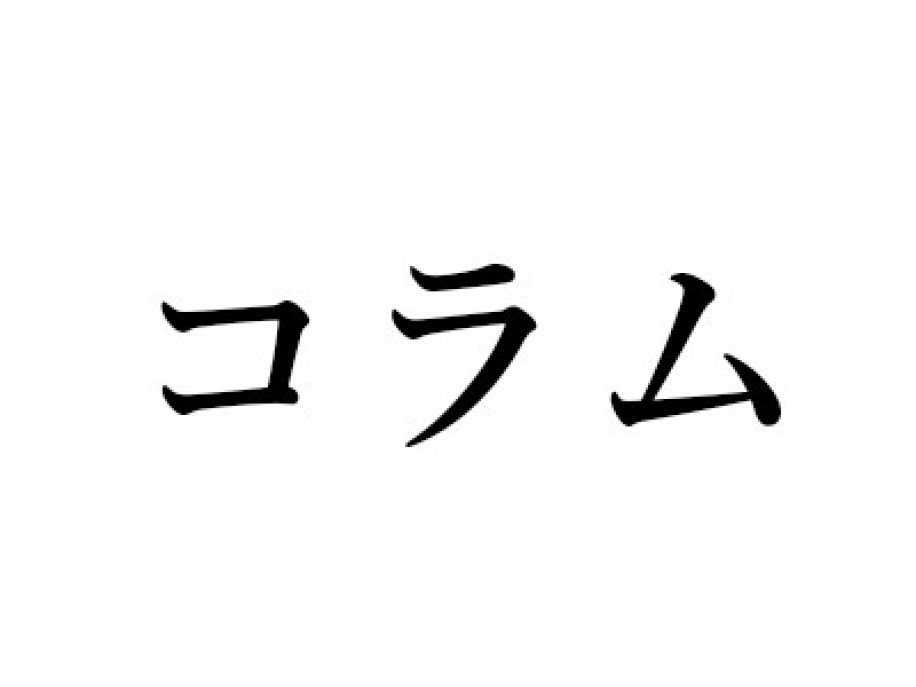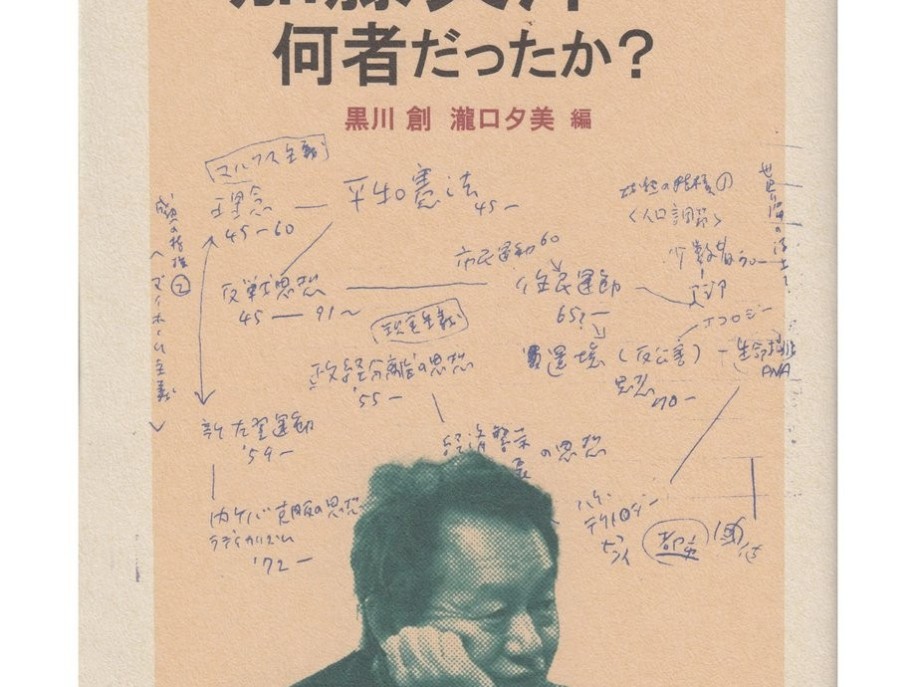対談・鼎談
森銑三『一代男新考』(冨山房)|丸谷才一+木村尚三郎+山崎正和の読書鼎談
木村 『一代男』は知られざる別人の作品で『諸艶大鑑』以下の、大衆受けした作品のほうこそが西鶴のものだということだって、いえるのではないかと思うんですね。
その点を究めるためには、団水の作品とわかっているものと、ここで森さんが団水の作とされているものとの、比較対照がなされる必要がありますね。この本にはその点が見られず、残念に思います。
これをやって、西鶴の作品とされているものが、たとえば団水の作品とまったく同じか、酷似しているかが論証されれば、著者の主張は説得力をもつと思う。
丸谷 普通、美術評論家は、絵に接したときに、いつも、これは本物か、偽物かということを問われるわけですね。ところが文学の批評家は、本物か、偽物かを問われることがないんですよ。
山崎 一体、美術の世界において、本物か、偽物かがなぜ話題になるのであろうかということを考えますと……。
丸谷 それは金銭に関係あるから。
山崎 そう。まったくそういうことでしょう。そこですぐ思い出すのがひと頃、大いに騒がれたシェークスピア非実在説です。シェークスピアのような、あまり学問のない男が、あんな傑作をたくさん書くわけがない。いや、これはマーローが手伝ったのであろうとか、あるいは一部がほかの人の作品であろうとか、さんざん議論した結果、出てきた結論は、つまり「それがどうした」ということなんですね。仮りに、シェークスピアという男の作品であろうが、そうでなかろうが、ここには一つの作品の世界がある。それをシェークスピアと名づけておいてどうして悪いか、というわけです。
丸谷 そうです。
山崎 文学の研究には基本的に二つの立場があると思うんです。一つは、ここに一人の人間がいて、ある歴史的現実の中に生きていて、その人間がこういうものを書いた、という人間研究として見ていく立場。もう一つは、狭義の文学史的、あるいは芸術史的な観点で、しかじかの作品が生まれたという事実だけを認めて、それがわれわれにとって何を意味するかを考えるという立場ですね。
そう考えると、森さんはつねにいわゆる内在的批評の立場に立とうとされているわけですね。けっして西鶴の伝記を調べて、西鶴がその頃いくら金をかせいだとか、どういう服装をして、どういう女と遊んでいたかというようなことは調べておられない。そういう立場を初めから問題にしないで、作品の文体的分析からスタートして作者の追求をなさっているわけですね。
そうすると、ここに『一代男』とその他の作品がありさえすれば、それが西鶴であろうとなかろうと、どっちでもいいじゃないかということにもなるわけですね。いわゆる「名前のない芸術史」でなぜいけないのか。
丸谷 西鶴の伝記はほとんどわからないわけです。それで一向差し支えなかった。本があれば、それでかまわなかった。江戸時代の文学の場合には、作者がだれかというようなことは問題じゃなかった。作者はしばしば不明であったし、個人の作よりは合作のほうが多かった。
ところが十九世紀の西欧では、文学は、個人主義的なものになった。それが日本に輸入されて、日本文学というものをも、個人主義的文学の目で見ようとした。そのときに、西鶴という一人の天才がつくられちゃったと、ぼくは思うんですよ。
山崎 なるほど。
丸谷 西鶴の作品は、明治何年かに帝国文庫で『西鶴集』が出たのが活字体の最初であって、それ以後新しい版が出るごとに、作品数がグングンふえているんですね。なぜふえたかというと、西鶴という文学的天才をつくりたい、ことに小説の面でつくりたい。なぜ小説の面でつくりたいかというと、西洋には大小説家がいるからですよ。
山崎 あ、それはおもしろいなあ。
丸谷 だから、バルザックのような小説家をつくりたいわけです。「人間喜劇」に対応する西鶴物の人間喜劇をつくりたいわけです。だからつくったんだ。
で、やはり、これはおかしいじゃないか、つまり、西欧風の文学の杓子定規のあてはめ方でやるのはおかしいじゃないかというのが、森銑三氏のいちばんの本音じゃないかと思うんです。
山崎 それはよくわかる。
丸谷 そういう日本文学史批判、それが森さんの仕事のいわば無意識的な主題でしょうね。で、ぼくの考えをいいますと、西鶴っていう人はいたでしょう。しかし、一人じゃなくって、二代目西鶴、三代目西鶴、四代目西鶴、いっぱいいたんじゃないか。しかもそれは、初代西鶴が生きているうちにどんどん出てきたんじゃないか。彼らの書いたものがみんな西鶴物だったんじゃないか。
木村 そうすると、個人西鶴は明治の創作ですか。
丸谷 これはもう、明らかに明治ですよ。
明治時代が、ディケンズとか、バルザックに対応するだけの大小説家を発見しようとして苦心惨憺した結果、出てきたのが西鶴だったんじゃないでしょうか。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
その点を究めるためには、団水の作品とわかっているものと、ここで森さんが団水の作とされているものとの、比較対照がなされる必要がありますね。この本にはその点が見られず、残念に思います。
これをやって、西鶴の作品とされているものが、たとえば団水の作品とまったく同じか、酷似しているかが論証されれば、著者の主張は説得力をもつと思う。
丸谷 普通、美術評論家は、絵に接したときに、いつも、これは本物か、偽物かということを問われるわけですね。ところが文学の批評家は、本物か、偽物かを問われることがないんですよ。
山崎 一体、美術の世界において、本物か、偽物かがなぜ話題になるのであろうかということを考えますと……。
丸谷 それは金銭に関係あるから。
山崎 そう。まったくそういうことでしょう。そこですぐ思い出すのがひと頃、大いに騒がれたシェークスピア非実在説です。シェークスピアのような、あまり学問のない男が、あんな傑作をたくさん書くわけがない。いや、これはマーローが手伝ったのであろうとか、あるいは一部がほかの人の作品であろうとか、さんざん議論した結果、出てきた結論は、つまり「それがどうした」ということなんですね。仮りに、シェークスピアという男の作品であろうが、そうでなかろうが、ここには一つの作品の世界がある。それをシェークスピアと名づけておいてどうして悪いか、というわけです。
丸谷 そうです。
山崎 文学の研究には基本的に二つの立場があると思うんです。一つは、ここに一人の人間がいて、ある歴史的現実の中に生きていて、その人間がこういうものを書いた、という人間研究として見ていく立場。もう一つは、狭義の文学史的、あるいは芸術史的な観点で、しかじかの作品が生まれたという事実だけを認めて、それがわれわれにとって何を意味するかを考えるという立場ですね。
そう考えると、森さんはつねにいわゆる内在的批評の立場に立とうとされているわけですね。けっして西鶴の伝記を調べて、西鶴がその頃いくら金をかせいだとか、どういう服装をして、どういう女と遊んでいたかというようなことは調べておられない。そういう立場を初めから問題にしないで、作品の文体的分析からスタートして作者の追求をなさっているわけですね。
そうすると、ここに『一代男』とその他の作品がありさえすれば、それが西鶴であろうとなかろうと、どっちでもいいじゃないかということにもなるわけですね。いわゆる「名前のない芸術史」でなぜいけないのか。
丸谷 西鶴の伝記はほとんどわからないわけです。それで一向差し支えなかった。本があれば、それでかまわなかった。江戸時代の文学の場合には、作者がだれかというようなことは問題じゃなかった。作者はしばしば不明であったし、個人の作よりは合作のほうが多かった。
ところが十九世紀の西欧では、文学は、個人主義的なものになった。それが日本に輸入されて、日本文学というものをも、個人主義的文学の目で見ようとした。そのときに、西鶴という一人の天才がつくられちゃったと、ぼくは思うんですよ。
山崎 なるほど。
丸谷 西鶴の作品は、明治何年かに帝国文庫で『西鶴集』が出たのが活字体の最初であって、それ以後新しい版が出るごとに、作品数がグングンふえているんですね。なぜふえたかというと、西鶴という文学的天才をつくりたい、ことに小説の面でつくりたい。なぜ小説の面でつくりたいかというと、西洋には大小説家がいるからですよ。
山崎 あ、それはおもしろいなあ。
丸谷 だから、バルザックのような小説家をつくりたいわけです。「人間喜劇」に対応する西鶴物の人間喜劇をつくりたいわけです。だからつくったんだ。
で、やはり、これはおかしいじゃないか、つまり、西欧風の文学の杓子定規のあてはめ方でやるのはおかしいじゃないかというのが、森銑三氏のいちばんの本音じゃないかと思うんです。
山崎 それはよくわかる。
丸谷 そういう日本文学史批判、それが森さんの仕事のいわば無意識的な主題でしょうね。で、ぼくの考えをいいますと、西鶴っていう人はいたでしょう。しかし、一人じゃなくって、二代目西鶴、三代目西鶴、四代目西鶴、いっぱいいたんじゃないか。しかもそれは、初代西鶴が生きているうちにどんどん出てきたんじゃないか。彼らの書いたものがみんな西鶴物だったんじゃないか。
木村 そうすると、個人西鶴は明治の創作ですか。
丸谷 これはもう、明らかに明治ですよ。
明治時代が、ディケンズとか、バルザックに対応するだけの大小説家を発見しようとして苦心惨憺した結果、出てきたのが西鶴だったんじゃないでしょうか。
【この対談・鼎談が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする