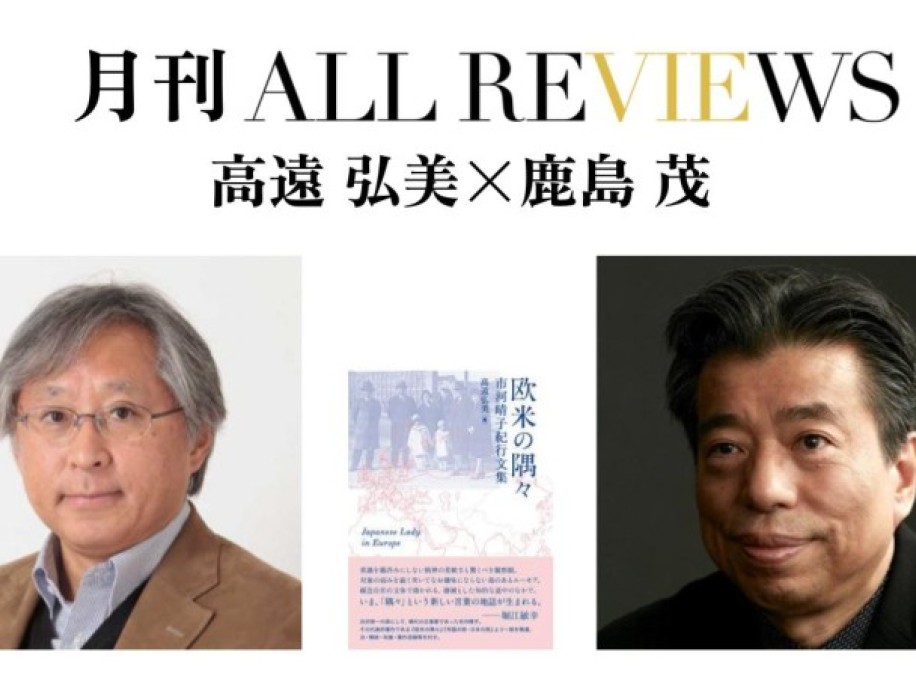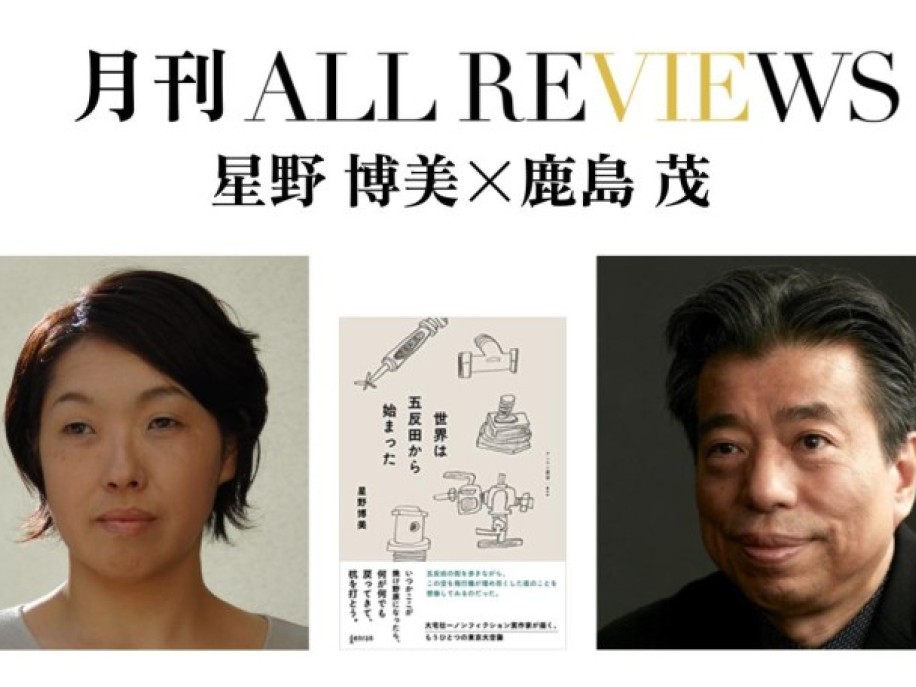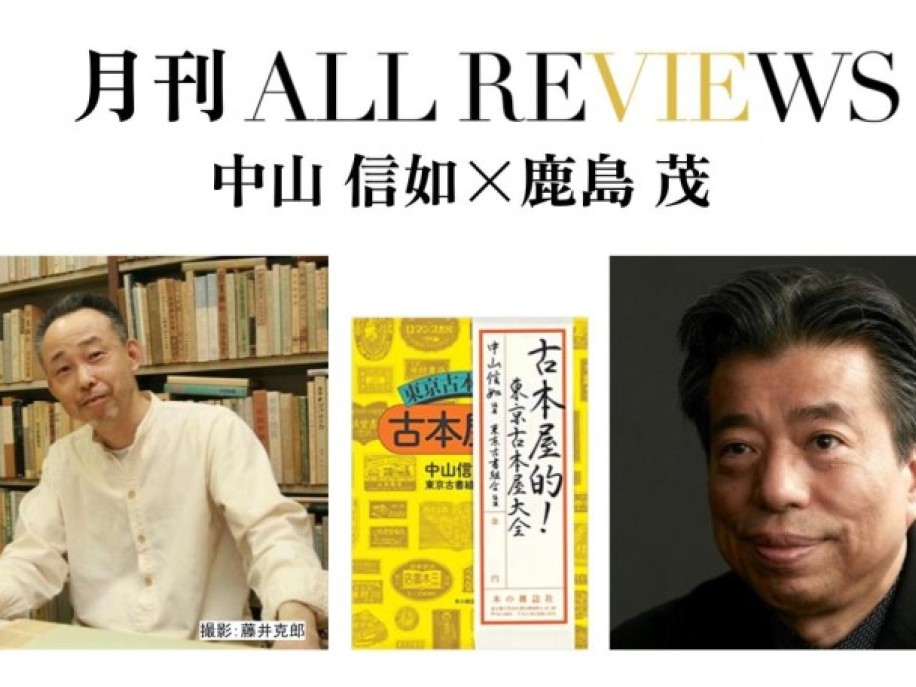書評
『明日は舞踏会』(中央公論新社)
貴婦人の謎解明、面白く悲しい結末
題を見ただけでワクワク、収録ファッション画カラー多数を眺めればゾクゾク。男のパリ出世すごろくである前著『馬車が買いたい!』では勤務先の女子大生の「舞踏会への渇望」にこたえられない。サービス熱心なカシマ先生は淑女版に着手する。手がかりはバルザック「二人の若妻の手記」。修道院を出てパリ社交界にデビューしたルイーズが、田舎で堅実な家庭を築いた友人ルネと手紙を交わす。
無邪気に語りつづけ、決してひけらかしにならないのが著者の徳だ。フロベール、ゾラ、バルザック、スタンダールなど十九世紀小説の謎(なぞ)が数々とける。
なぜ貴族の親は娘を修道院に入れたがるのか。答、ナポレオン法典によって女子も男子と同等の相続権を得たので、財産を散らしたくなければ、娘を結婚させないよう修道院にぶち込むしかなかったのである。
なぜ貴婦人は靴に凝ったのか。なぜチュイルリ公園に散歩に行く必要があったのか。なぜ自宅で堂々と愛人と逢引(あいびき)できたのか、は読んでのお楽しみ。 なぜ持参金にあんなにこだわるのだろう。これも結婚に関するカシマの定理〈ルックス×財産=1〉で説明される。すなわち美貌(びぼう)でないほど持参金が必要となるのだそうだ。
そして美貌の乙女は金持ち老人と結婚し、彼が死ぬまで数年がまんする。ばくだいな遺産と男爵夫人の称号を手に入れたら、つぎは若く美貌の愛人と結婚し、彼女が死ぬと老人となった男は財産を受け継いで……。
この循環式人生二回結婚説にせよ、「一種の乱交パーティー」だったオペラ座の仮面舞踏会にせよ、おお、なんとミもフタもなく、アラレもない時代だったのであろう。
コルセット着用者百人のうち二十五人は結核にかかり、十五人は最初の出産で死に、十五人は病気がち、残り十五人は奇形となる、という恐ろしい資料が上がるに及び、私は「面白うてやがてかなしき舞踏会」にしゅんとしてしまった。
「結婚というものを情熱の上に築き上げることは不可能で恋愛の上に打ち立てることさえ許されません」。女主人公ルイーズのいまわの言葉だけは万古不易と思うけど、いかが。
朝日新聞 1997年5月11日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする