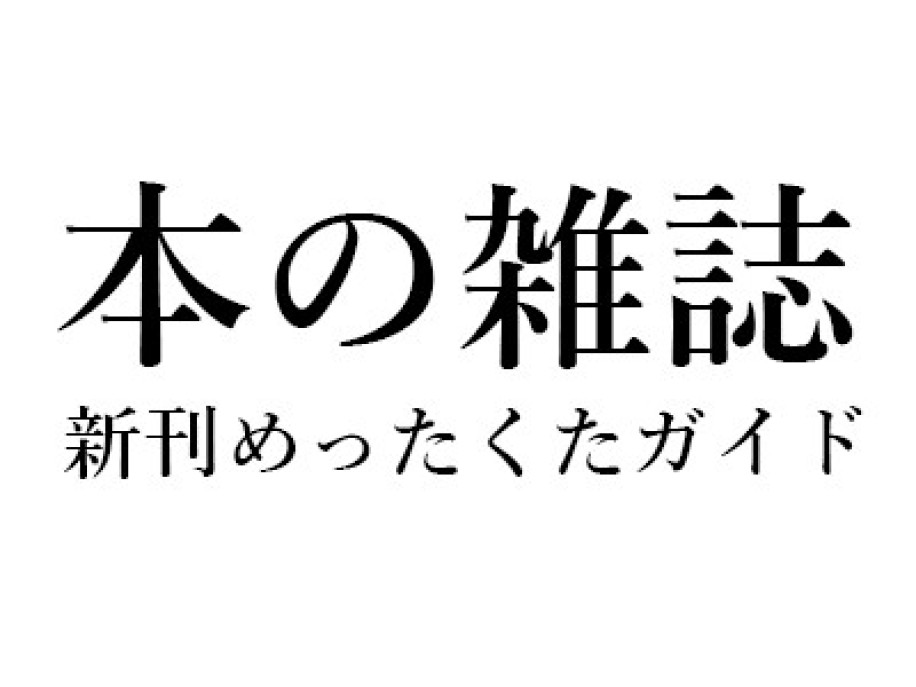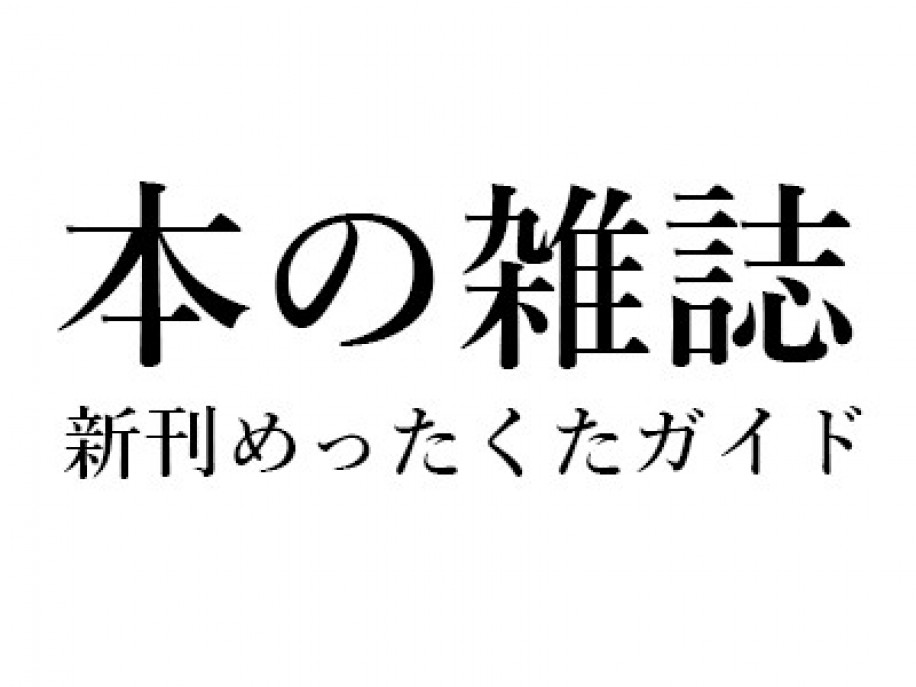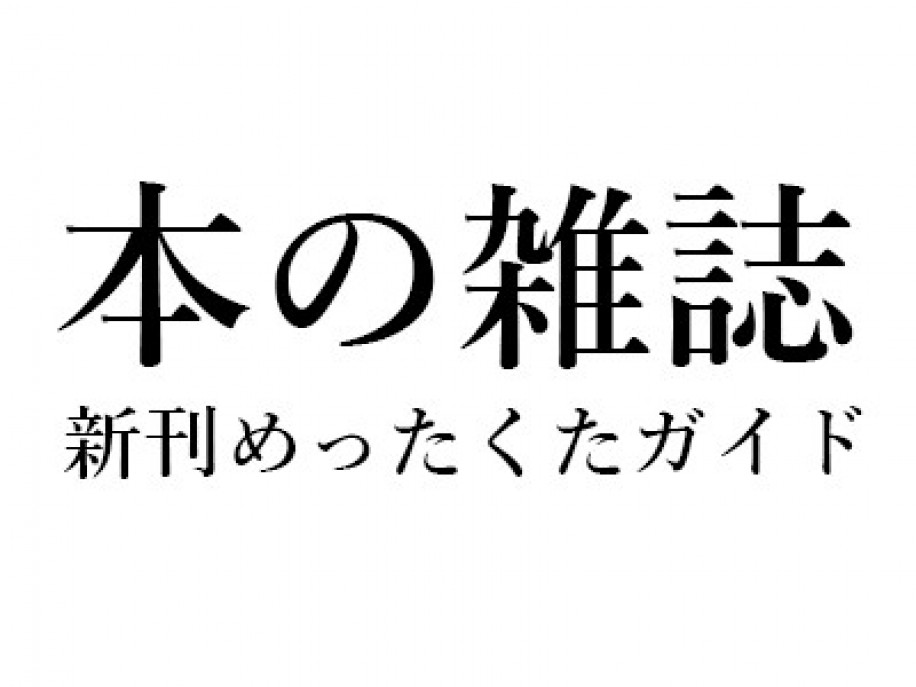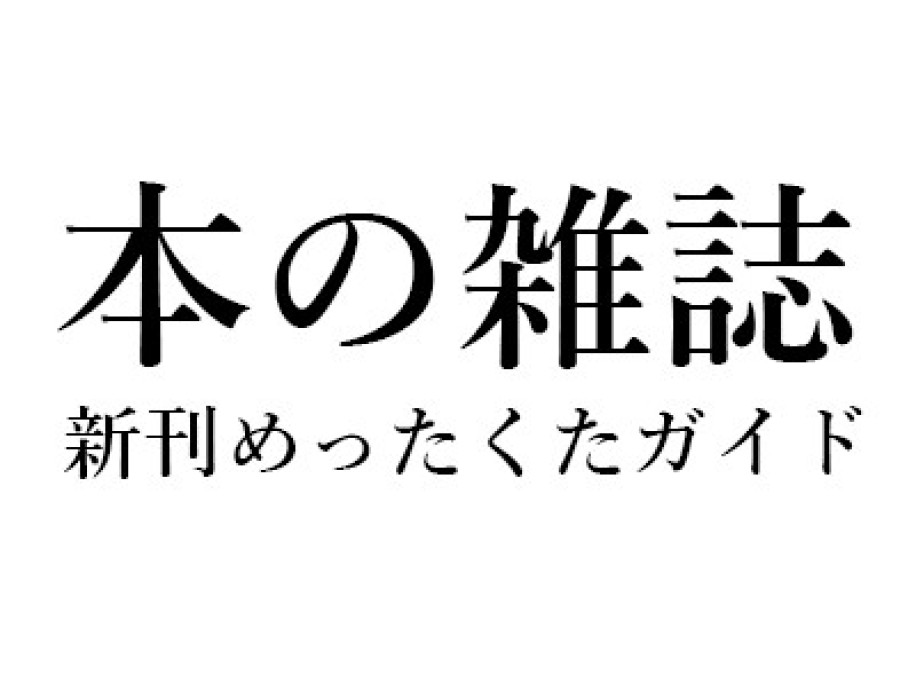読書日記
町井登志夫『今池電波聖ゴミマリア』(角川春樹事務所)、神林長平『永久帰還装置』(早川書房)、宮部みゆき『ドリームバスター』(徳間書店)ほか
異色すぎる小松左京賞受賞作『今池電波聖ゴミマリア』
今月は第2回小松左京賞受賞の町井登志夫『今池電波聖ゴミマリア』(角川春樹事務所)★★★★から(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2002年2月)。著者は第3回ホワイトハート大賞優秀賞の仮想現実SF『電脳のイヴ』で九七年にデビューした人。〝少女向け〟の制約が消えた今回は、高校生を主人公にしつつも、血と精液と汚穢(おわい)に満ちた暗黒の近未来を力強く構築する。実際、これがミステリ系の賞なら、〝戦慄の近未来ノワール〟みたいな惹句がついただろう。時は二〇二五年。日本の出生率は低下の一途をたどり、人口の三分の一が六十歳以上。国家財政は完全に破綻し、健康保険も公共サービスも崩壊、街には回収されないゴミが山積みになっている。主人公の森本聖畝(せいほ)は、中部地方の街、今池の高校に通う十七歳。暴力教室と化した学園にはフラタニテと呼ばれる学生グループが群雄割拠し、組織に属さない聖畝は、恐ろしく凶暴な大男の白石にくっついて、金(ベラ)稼ぎの仕事(トラボー)の手配役を勤めることで、なんとか苛酷な日々を生き抜いている……。
馳星周の歌舞伎町が引っ越してきたようなこの破滅的近未来描写が抜群にいい。ただ陰々滅々なわけではなく、いきなり風俗嬢のマリアにハマって暴走する白石に聖畝が振り回される前半には(たとえば黒川博行『疫病神』のような)乾いたユーモアも漂う。ただし、欠点も少なくない。特権階級に属するJCD(ジュニア・サイバー・ディーラ=マネーゲームの尖兵として政府の肝煎りで働く少年少女)の家に強盗に入ったことをきっかけに、出生率問題にからむ国家的陰謀に巻き込まれるという本筋にはあんまり説得力がないし、暴力教室の描写も後半は(まるで『男組』みたいな)古臭い方向に傾く。だが、そういう欠点を差し引いても、徹底的にダークで救いのないこの猥雑な近未来は魅力的だ。ノワール系の読者にもおすすめ。
続けて四六判の日本SF注目作を二冊。神林長平『永久帰還装置』(朝日ソノラマ→ハヤカワ文庫JA)★★★☆は、未来の火星に忽然と出現した〝永久追跡刑事〟と名乗る男を軸に描く、著者十八番のディック的な現実変容SF。ただし、つねに強固な日常的リアリティを築いた上でその崩壊を描くディックに対し、本書では物語の基盤となる現実が人工的なものであることが最初から宣言される。その結果、読者はよりどころを失い、小説は、たとえばエリック・アンブラーのエスピオナージュにも似た仮面劇の性格を帯びる。現実を自由に改変できる登場人物が存在する不確定世界での活劇。それを一気通読の娯楽作に仕立て、ついでにラブストーリーまで語ってしまう技術力はさすが神林長平。
宮部みゆきの新シリーズ第一弾『ドリームバスター』(徳間書店)★★★も、神林作品と同じく、〝凶悪犯を追って別世界から捜査官がやってくる〟という、「ヒドゥン」型の構造を持つが、方向性は正反対。肉体を持たない意識だけの逃亡犯は、人間の心にとりつくため、映画「ザ・セル」のように、夢の中が闘いの舞台になる。ただしここでは、非日常性は夢の中だけに限定され、現代日本の日常も、テーラと呼ばれる異世界も、強固な現実感を失わない。だからこそ一般読者もすんなり物語に入れるわけだが、SF読者には多少の物足りなさが残る。もっとも、物語は始まったばかり。続巻の展開を見守りたい。
坂東眞砂子『曼荼羅道』(文藝春秋→集英社文庫)★★★★は、戦時中マレー半島に赴いた富山の薬売り・蓮太郎とその孫の麻史(あさふみ)を軸に、過去と現在、雪国と南方を交錯させる魔術的幻想小説の秀作。蓮太郎を追ってマレーから日本に来た森の部族の娘サヤの苛烈な半生が圧倒的。後半、立山の山道に突如出現する〝異界〟の迫力もこの著者ならでは。
〝近未来SFミステリホラー長篇〟と銘打つ倉阪鬼一郎『BAD』(エニックス)★★は、モラルの逆転した極度に人工的な学園都市を舞台に〝世界の成り立ちの謎〟を探るタイプのSF。構造的にはわりと古めかしく、邪悪版『大きな壁の中と外』(新井素子)みたいな読み方も可能。ただしSF的な論理よりイメージや雰囲気が重視されるため、解決の説得力・衝撃力はいまいち。
菅浩江『夜陰譚』(光文社)★★★は、《異形コレクション》などに発表された〝和物〟中心の恐怖小説集。「和服継承」「桜湯道成寺」など、超自然的要素を排して、女の怖さを語りの芸で見せる短篇が秀逸。
田中啓文『ベルゼブブ』(トクマ・ノベルズ→角川ホラー文庫『蠅の王』)★★★★は、強烈なエログロスプラッタ描写もさることながら、〝蠅の王〟をはるか極東まで召喚すべく構築される伝奇SF的な屁理屈体系が傑作。隠れ切支丹が口承で伝えてきた『ヨハネの黙示録』の別バージョンとして捏造される「さんじわん先生の黙示のふみ」のもっともらしさには感服しました。いわく、「其時、天狗きたりて、この世をハライゾにせんと言葉巧みに言ひて、それを信じたる人は天狗の手したとなりて、みな、犬ヘルノといふベンボウに落るといふ事」とか。御使いの角笛の音は、「しななくの、でまどりの、いっちぱいちゆく……」みたいな調子でえんえんと綴られ、それが現代の怪事件を予言したものとしてまことしやかに解釈される。クトゥルー神話を仏教経典に〝翻訳〟してみせた殊能将之『黒い仏』に匹敵する大技でしょう。
ヒロインは、男性アイドル・トリオ(ジャニーズ系)の追っかけに燃える十六歳の少女(親衛隊所属)。亡き両親はともに世界的な昆虫学者で(マッドサイエンティスト系)、しかも恋人の男性アイドルはなぜかオカルトおたく。さる考古学者がベツレヘムの発掘現場で掘り出した怪しい壺を日本に持ち帰ったのを契機に怪事件が連発、ヒロインがそれに巻き込まれる──という展開こそ伝奇ホラーの王道だが、のっけから血と精液と糞尿が炸裂。現代日本に復活した〝蠅の王〟が大暴れするクライマックスがまた凄い。生まれたばかりなので当然まだ幼虫。どう見てもこれは例の怪獣のダークサイド版なわけで、それを自衛隊が歌舞伎町で迎え撃つのだから呆れるしかない。筆が走り出すとB級お笑い路線に流れ、結果的に傑作になり損ねているが、その悪い癖まで含めて田中啓文の集大成。
徳間デュアル文庫の中篇書き下ろし《デュアルノヴェラ》の新刊から二冊。『ドッグファイト』で第2回日本SF新人賞を受賞した谷口裕貴の第二作『遺産の方舟』★★は、「文明崩壊後の世界を空母で巡回して文化財を回収する学芸員」という設定が魅力。ただしプロットがそれとうまく噛み合っていない。三雲岳斗『ワイヤレスハートチャイルド』★★は、ヒト型ロボットが実用化された社会を背景に、喫茶店でバイトする大学生が遭遇した事件を描く、SF設定の〝日常の謎〟派ミステリ。試みとしては面白いが、SF/ミステリ/キャラの各要素がどれも中途半端に見える。
森岡浩之『月と闇の戦記一 退魔師はがけっぷち。』(角川スニーカー文庫)★★☆は、『月と炎の戦記』に続く新シリーズの開幕篇。前作のトリオ(ウサギ一羽含む)が楽しく暮らす幽霊アパートに極貧の体育会系退魔師が転がり込んでくる──というのが発端で、長篇ではこの著者初の現代もの。話はまだろくに始まらないが、滑り出しはまずまず快調。
最後に、エリック・ガルシアの私立探偵ハードボイルド『さらば、愛しき鉤爪』(酒井昭伸訳/ヴィレッジブックス)★★★☆は、一種のバカSFとしても読める珍品。恐竜がヒトの皮をかぶって人間社会に同居しているという無理やりな設定にある程度の説得力を持たせようと導入された理屈が(整合性はともかく)やたらにおかしい。
ALL REVIEWSをフォローする