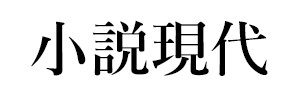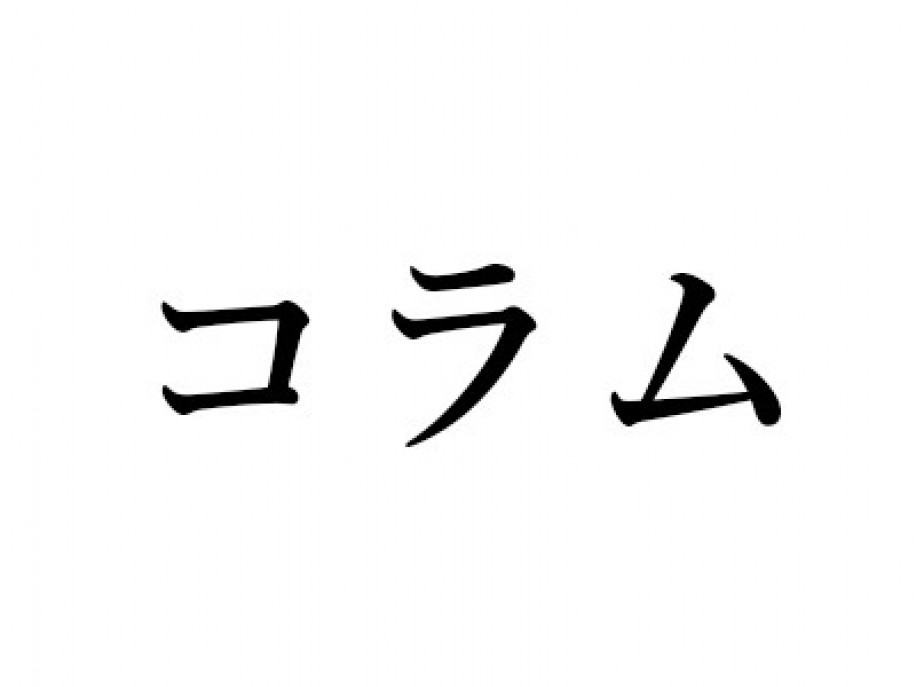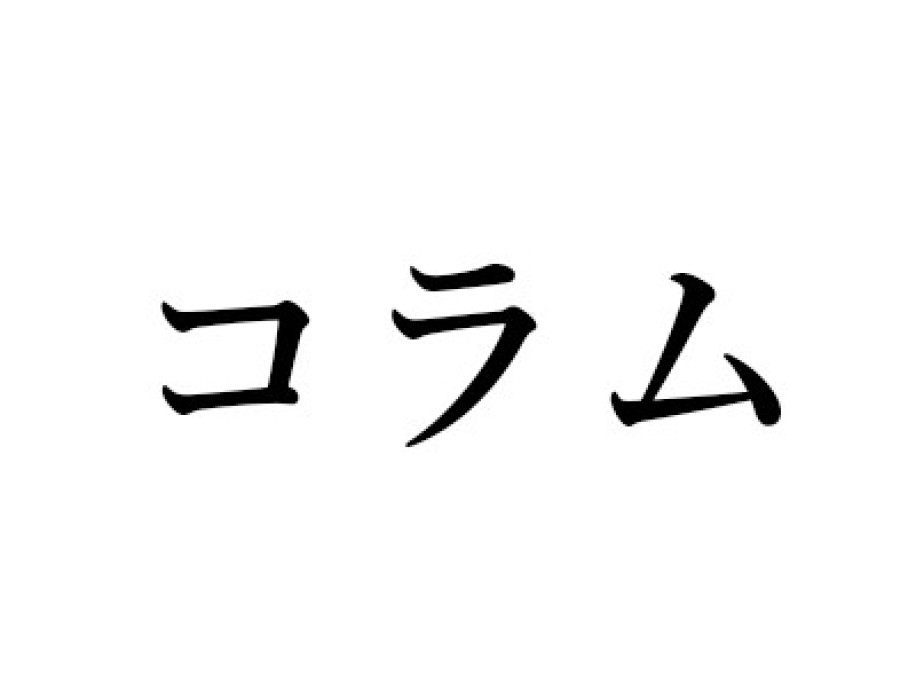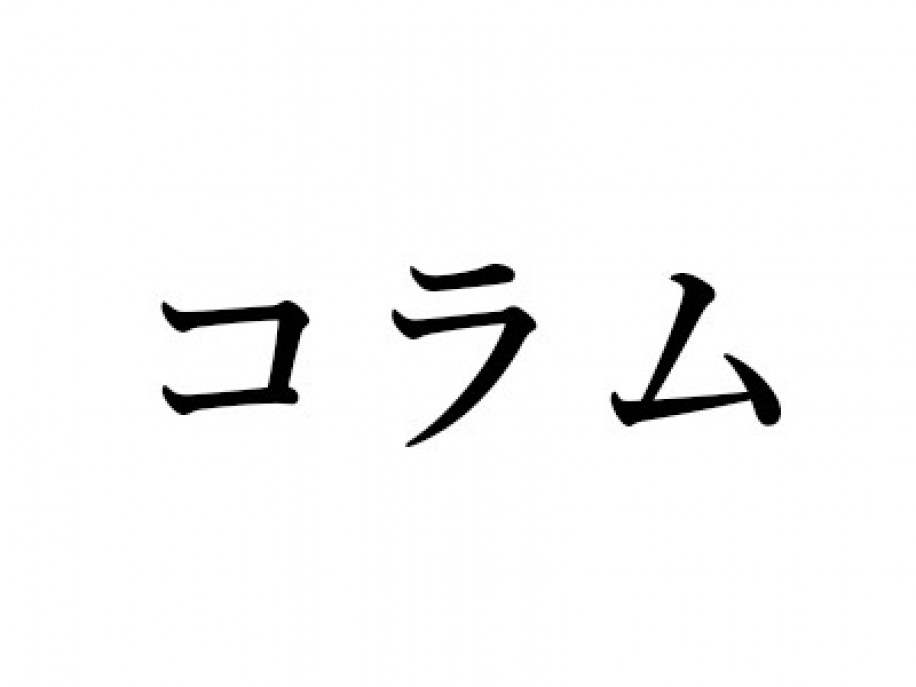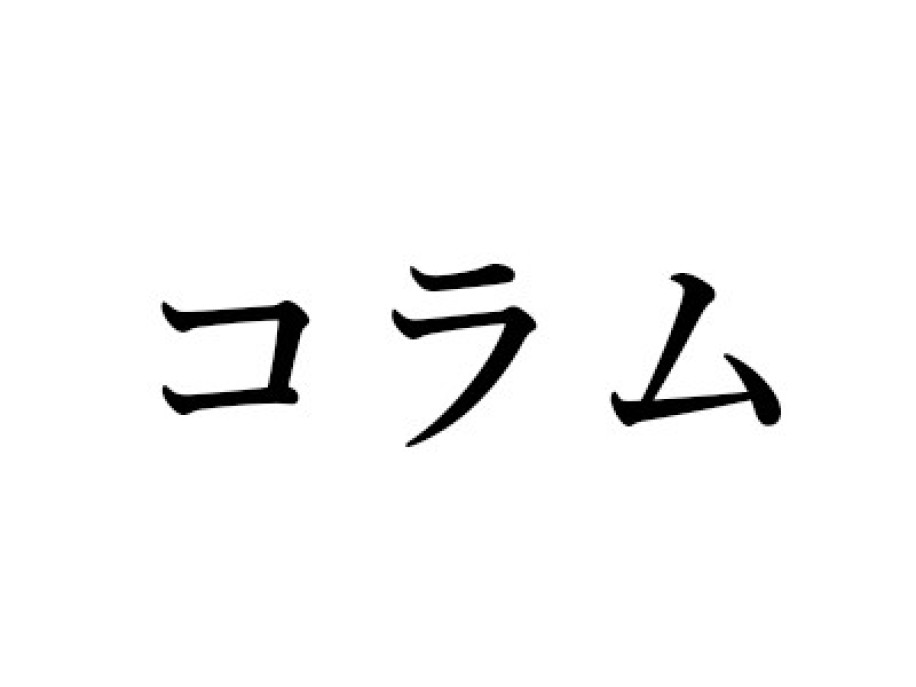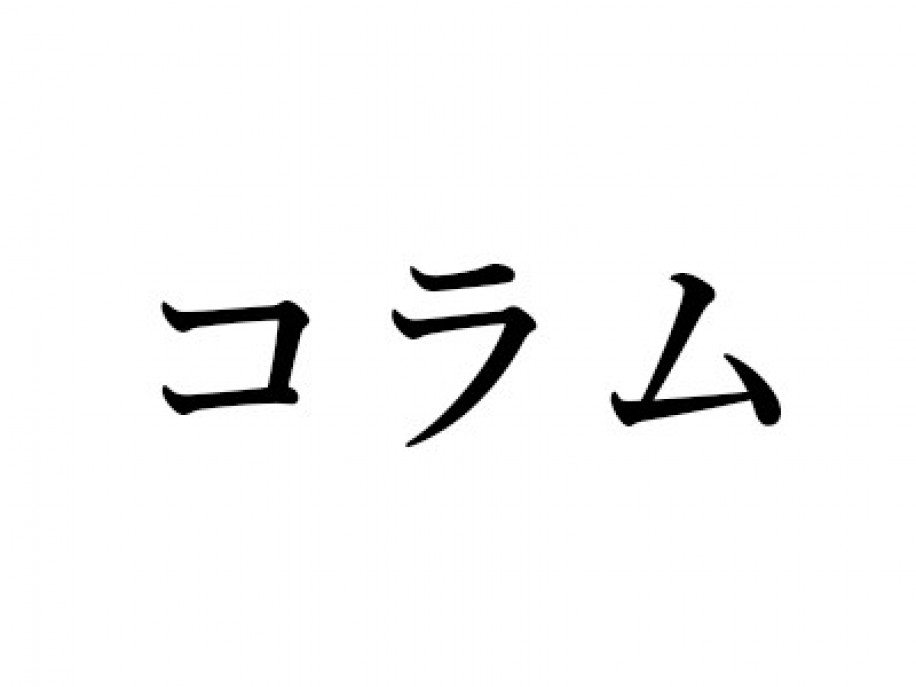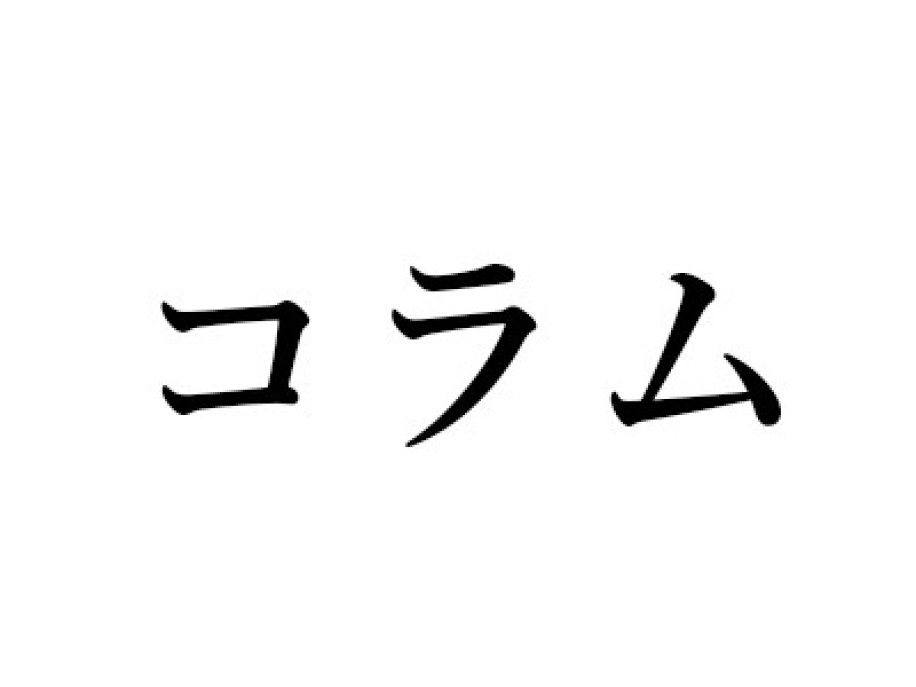コラム
吉本由美『かっこよく年をとりたい』(筑摩書房)、佐藤洋子『六十代を生きる』(マガジンハウス)、小倉寛子『小倉遊亀 天地の恵みを生きる』(文化出版局)、神沢利子『おばあさんになるなんて』(晶文社)
おばあさんになるなんて
前は老後に関する想像といえば、「このまま夫も子どももいないと、ずっとひとりか」
「アパートを追い出されたらどうする」
といったものだったが、マンションに越してからは、心配がもっと細かくかつ具体的になってきた.家の中のちょっとした段差にも、
「こういうところに、将来の私はつまずくわけね」
脚立に乗ってする電球の取り替えも、老後は誰かに頼まなければならない。これからは、そういうちょっとしたことの出張サービスが、ビジネスとしてさかんになるのではないか。
新聞の投稿欄にも、ズボン下やパンツのゴムが高齢者にはきつくて困るといった声が寄せられていた。そう、もっとシルバー市場にさまざまな業界が目を向ければ、やがておばあさんとなる私としては、心強い。
元スタイリストの吉本由美も、四十過ぎてから俄然、老いに関して興味が出てきたと、『かっこよく年をとりたい』(ちくま文庫)に書いている。この人もそのテの記事をたんねんに読んでいるようで、ベレー帽愛用者という七十歳の男性の投稿を引用したり、沖縄で百四歳のおばあさんが杖とハエ叩きで退治したハブの体長にまで詳しかったり、
「しっかりチェックしてますなあ」
と、同好の士をみつけた思いであった。
元スタイリストだけあり「準備が好きな」著者は、来るべき老後に備え、福祉生活コーディネイター講座に通い、老人ホームも見学した。気になるのは、設備がすばらしくても、町から遠く、気軽に外出できないこと。個室ではないので、プライバシーなど全然保てなさそうなこと。
シングル女性で、高齢になったときの住まいに求める条件として、個室を挙げる人は多い。なぜって彼女らは、自分のライフスタイルにかなりこだわり、維持してきた人たち。
この本の帯にも書いてある「好きなファッション、好きなインテリア、そして好きな暮らし方。いつまでも手離したくない!」。
私の願いも、結局はそうだ。目と鼻の先とまではいかないが、頑張って十分歩けば、喫茶店や雑貨屋があり、若い人や子どもづれが行き交うロケーション。気が向けばときには外でランチをとるくらいはできる、経済的ゆとり。そうした今の延長で、できるだけ続けたいのだが、現実は、どうか。それでも著者は、おばあさんになっていくのが「新鮮」という。
「だって初めての経験じゃない? 若い状態は一度経験したからもういいの。それがどんなに良くったって同じこと繰り返すより、違うことをやるほうが楽しいもん」と。
同じ老いを扱うのでも、六十代の著者だと、トーンがこうも違ってくるのかと驚くのが、佐藤洋子著『六十代を生きる』(マガジンハウス)。死というテーマがぐっとリアルに現れる。「手の内から時間がこぼれ落ちていくような実感がある。時がたつのが速すぎる」。
生の有限性をいやおうなしに認識する。それこそが年を重ねるということか、あるいは個人差によるものか。
元新聞記者の著者は、さまざまな人に取材する。私がいちばん印象的だったのは、七十歳で老人ホームに入ったものの、食事がどうしても口に合わず、ひとり暮らしを選んだ女性だ。パリで出会った、アパルトマンで暮らす高齢の婦人は、二本の杖にすがってまで市場に買い物に来る。そうまでして、自分の味を守るのだ。
その姿に刺激を受けた彼女は、ホームを出て、再びひとりに戻り、月一回は銀座に出かけ、四丁目の喫茶店でお茶を飲むのが楽しみという。ぜいたくなようだが「その人らしさ」を支えるのは、そんな生活のディテールなのだ。
その女性いわく、ホームに入ったときは「自分が老人になりきっていなかったと思います」。息子の足手まといにならないようにとか、ホームに入れただけでもありがたいのだから我慢しなければとか、周囲の状況ばかり考え、自分にどっていいことかどうかの確信を持てぬまま、決めてしまった、と。
換言すれば「老人になりきる」とは、まわりがどうあろうと思いどおりの生き方を貫くことなのか。
小倉寛子著『小倉遊亀天地の恵みを生きる』(文化出版局)を読むと、小倉遊亀が百歳過ぎても現役の画家でいられたのは、ある意味で我を通してきたからではないかと感じる。介護に中心的役割を果たす、孫娘による評伝プラス介護日誌だ。
九十七歳で息子(著者の父)を亡くしたショックから床に就き、絵をいっさい描かなくなった。それから、百一歳で再び絵筆をとるまでの日々が綴られているが、正直、
「これは当人もさることながら、まわりがいかにたいへんか」
と溜め息が出た。
二時間おきのおむつ交換だけでも、たいへんなのに、著者はさらに「上」をめざした。
介護とは、単に永らえさせることではない、「残された身体能力と生命の力を生かしきった、こころ豊かで、祖母らしい暮らし」を実現することだ、と。
その方針に合わない人は、家政婦歴三十年のベテランも、プロの介護福祉士もやめてもらう。「小倉遊亀にとっての完全なる介護」でなければならない、としたのだ。
そのかいあって、祖母は制作を再開するわけだが、題材のマンゴーの実を、四時間かけて著者に配置させた。頭の中にある図柄と、少しでも違ってはならなかったのだ。うーむ。揃って、妥協を許さない性格。
世代も違うし、芸術家でもない著者だけれど、祖母と妙に共通するところがある。この本も、しっかりした構成と芯の通った文章で、人となりを物語るようだ。
少女の私がおばさんになる間に、この人もおばあさんになっていた。神沢利子著『おばあさんになるなんて』(晶文社)は、『ちびっこカムのぼうけん』『くまの子ウーフ』などで知られる児童文学作家が来し方を語った聞き書き。
童話の読者だった私には、
「この人、こんな人生を歩んできたの」
と驚くことばかりだった。夫の裏切り、病気と貧困、食べるためにはじめた投稿。
人を信じられず、恨みや憎しみのうちに年を重ねても、おかしくはない道のりだったのに、ところどころさしはさまれる著者の写真はどれもなんと、きれいなんだろう。少女がそのまま、おばあさんになったような。
「わたし、女盛りが苦手なのよね」
とのひとことが、すごくリアル。そういう人もいるよね。はたから見れば、もったいないようでもね。
あとがきによれば、童話作家につきまとう「清く美しい」イメージから自由になって、ほっとしているとか。でも、「清く美しくない」部分を知って、私はより著者が好きになった。
「おばあさんになるなんて」七十代半ばに入った著者は言う。「なあんてことはなかったわね……」
「べつに気張らなくたって」、歳月さえ重ねれば、自然になってしまうのだ、と。
併録された三篇の小説が、明るく広々として官能的で、この上なくすてき。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする