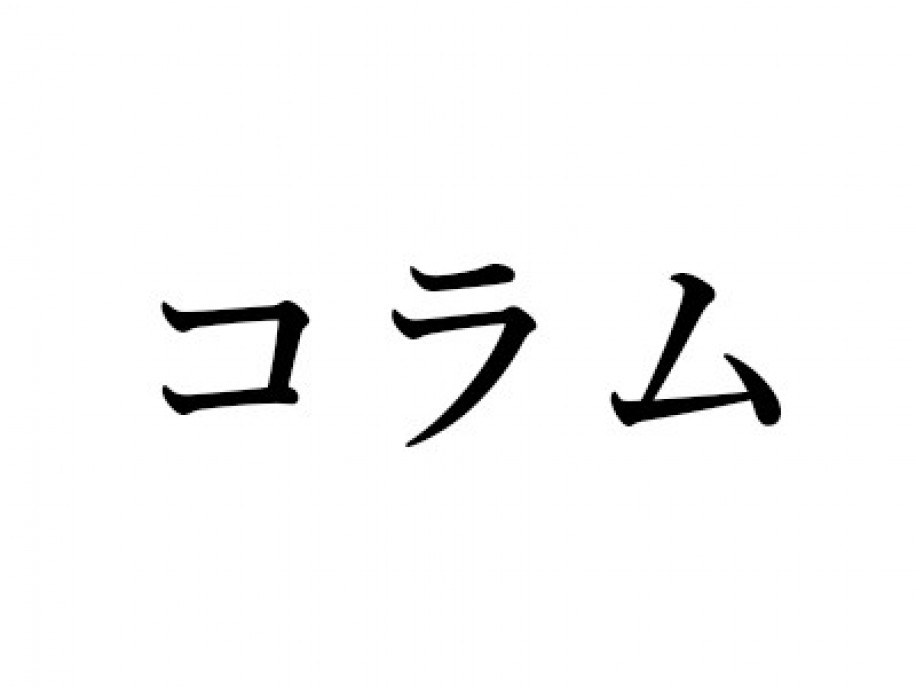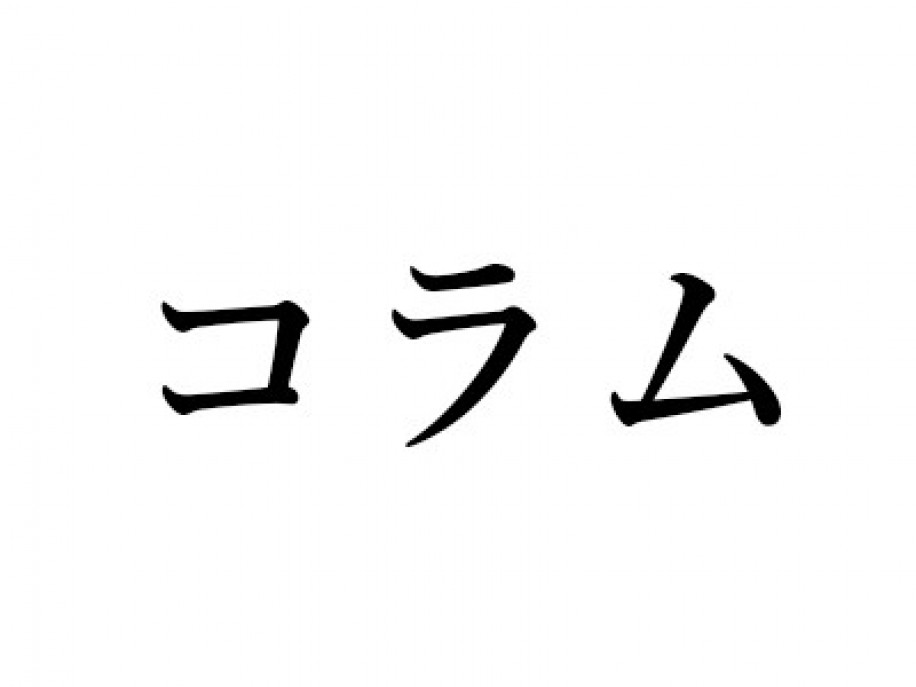コラム
内田 百閒『新・大貧帳』(福武書店)、赤瀬川 原平選『全日本貧乏物語』(同左)
貧乏も悪くない
貧乏をされたのですね。もしもあの世でお見かけしたら、そうねぎらいの言葉をかけたい。明治二十二年生まれ、昭和四十六年に鬼籍に入られた、内田百閒先生である。
むろん、いつもの不機嫌そうな顔で、ギョロリと睨まれるだけだろうが。
古い造り酒屋の坊ぼん育ち。東京帝国大学を卒業し、ドイツ語の教官として、人並み以上の給料を得ながら、高利貸しとの縁は死ぬまで切れなかった。
自動車を雇い、シートで煙草をふかしながら、金策に回る。家を捨て、下宿屋にひそむはめとなっても、外出時のいでたちは、ステッキに山高帽子。貧乏がいまひとつ板につかなかった感がある。
「錬金術」と称する、独自のマネー哲学は『新・大貧帳』(福武文庫)に詳しい。いわく、金とは常に受け取る前か、使った後かの観念だ。未来は一瞬のうちに過去となる。それはちょうど、時の認識と相似する。タイム・イズ・マネー。金は時の現在のごときものである。
みじめなはずの貧乏話が、なぜ面白いか。アンソロジー『全日本貧乏物語』(福武文庫)において、選にあたった赤瀬川原平はこう説明する。貧乏の文章化を成し遂げるには、金持ちと貧乏との二階級を制覇することが条件だ。この場合、貧乏→金持ちのベクトルだと、チャンスをつかんで努力するという、割合単純な話となる。逆の方こそウンチクが深く、ふくよかな味わいが生まれると。
生家は没落、みずからも夜逃げするはめとなった百閒は、この条件を満たして余りある。
いかなるときも我関せず焉(えん)ふうの文章は「飄々(ひょうひょう)とした」「とらえどころのない」と評される。が、彼もやっぱり近代のインテリの例にもれなかった。
青年期の手紙を読むと、自意識が過剰で息苦しいほどだし、処女作『冥途』(福武文庫)など、この緻密な感覚世界をつき詰めていったらどうなることかと、はらはらさせる。
それからすると『新・大貧帳』は、ひと皮もふた皮も剝けたものだ。錬金術は百閒を、いい感じに磨き上げた。
借金をあれだけ重ねながら、八十一歳の大往生の際、債務をほとんど残していなかったのは、ごりっぱ。
冥途でお目にかかった折りには、そのひとこともぜひつけ加えたい。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする