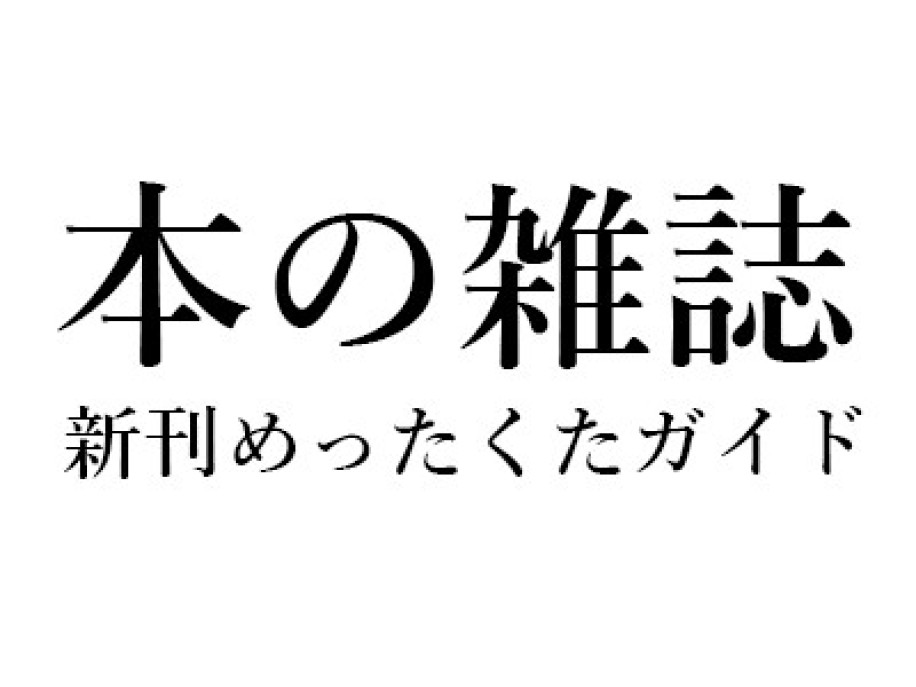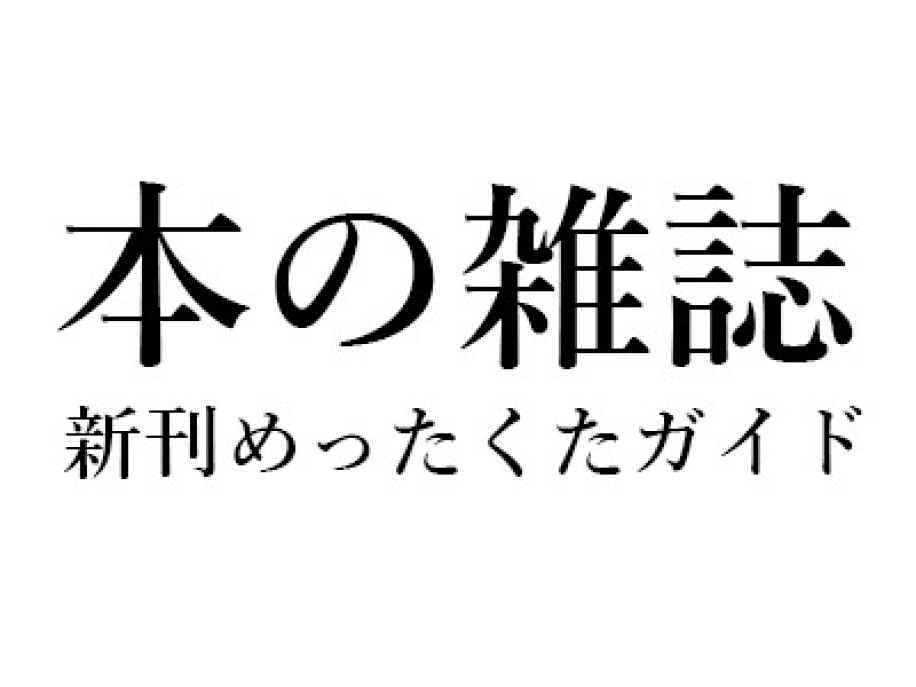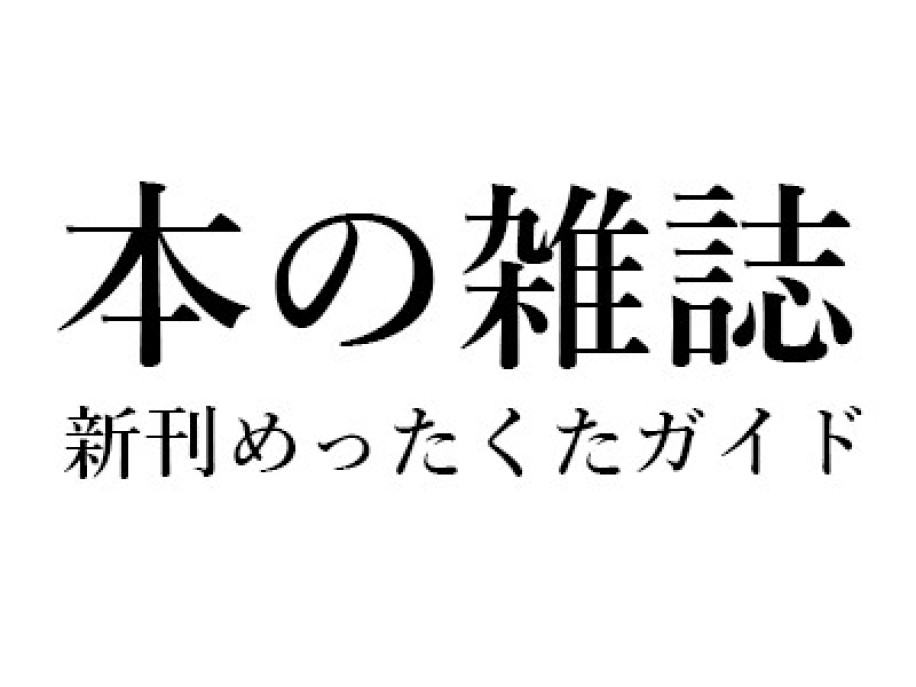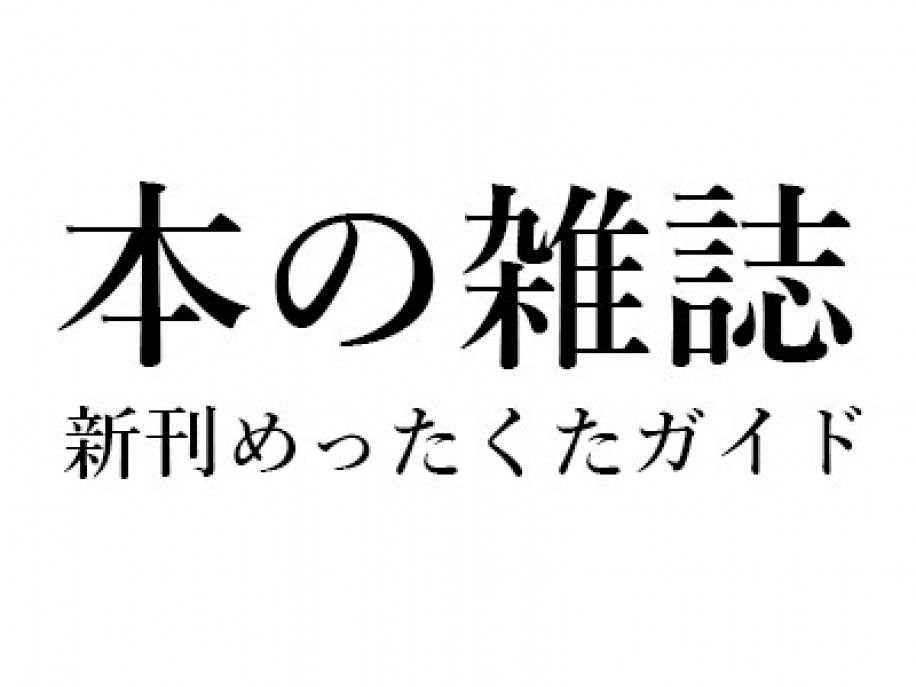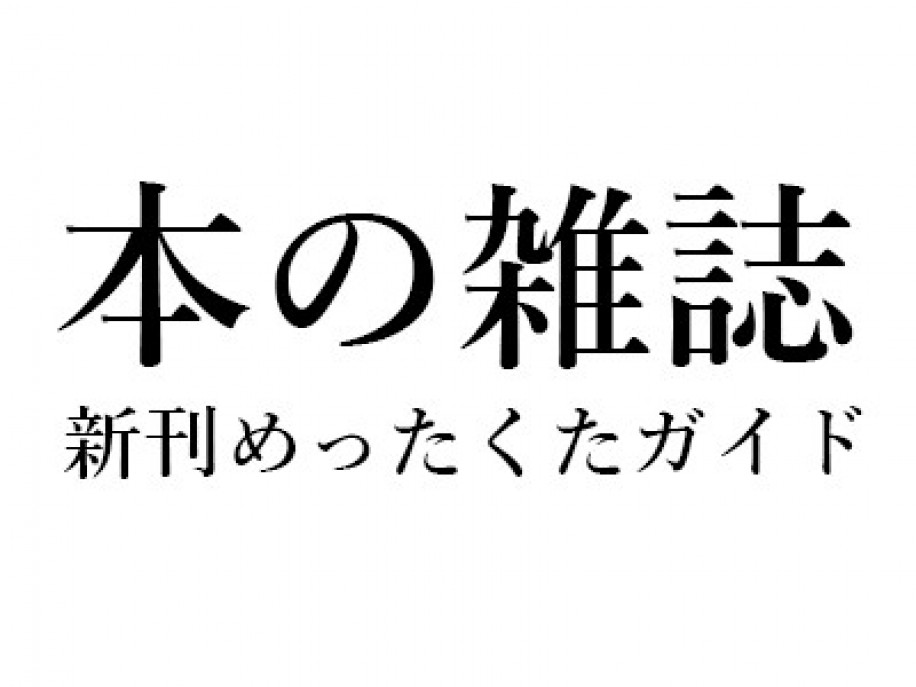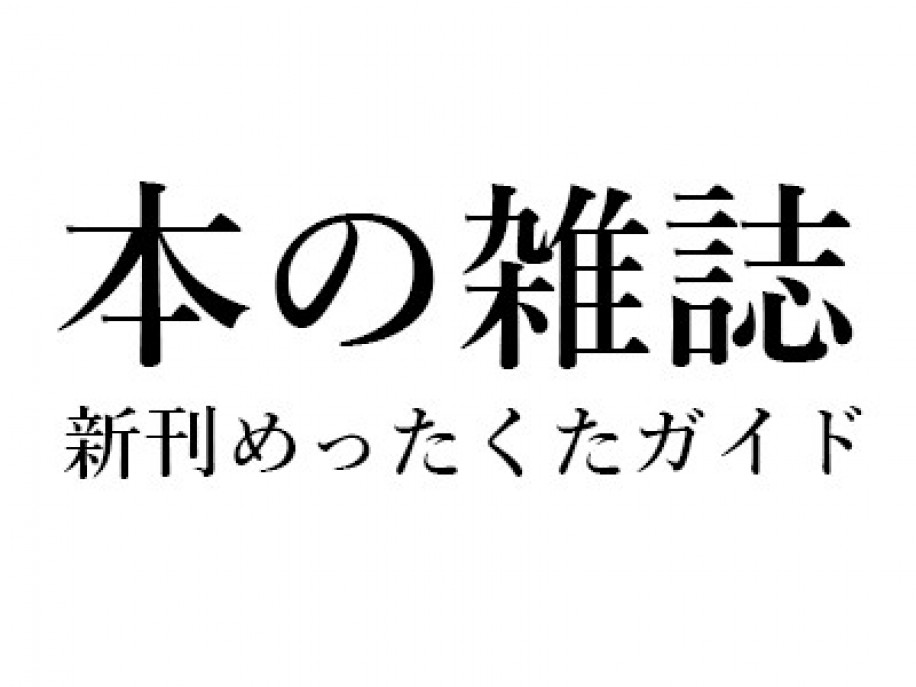読書日記
庚芳夫『虚人魁人 康芳夫 国際暗黒プロデューサーの自伝』(学研)、日垣隆『売文生活』(筑摩書房)、柳治男『〈学級〉の歴史学 自明視された空間を疑う』(講談社)他
どわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああーーーーッ!
(あたりをくるくる走り回りながら絶叫)すげぇぇぇ、すげぇぇですよ。度肝を抜かれました。気宇壮大!
『虚人魁人 康芳夫 国際暗黒プロデューサーの自伝』(庚芳夫/学研一七〇〇円)は、プロデューサー・庚芳夫の自伝。とんでもない男。
高校の文芸部時代には、原稿料なしで武者小路実篤から原稿をもらうなんてエピソードから始まって、あとは怒涛の雪だるま式に巨大化するすげぇすげぇープロデュース話の連発。
日本初のボクシングヘビー級公式試合「モハメド・アリ戦」の興行も、金なしコネなしの状態から、ぎりぎりの手練手管で成功させちゃう。人間とサルの間の生物オリバーくんを日本に連れてきたのも、この男。オリバーくんの子供を生みたいという女の子が現れ、オリバーくんとセックス!? なんて騒ぎも起きるほどの大フィーバー。五十パーセント近い視聴率もたたき出した。
総隊長は石原慎太郎のネス湖怪獣国際探検隊、人食い大統領アミンVS猪木、アラビア大魔法団興行、インディ500、人食いトラVS空手、ノアの方舟探索プロジェクト、奇書『家畜人ヤプー』プロデュース。
漫画じゃない。法螺(ほら)じゃない。全部、実際に彼が仕掛けた異形の興行の数々なのだ。
この男、奇天烈で、豪快で、命知らず。人生が、大ロマン、大冒険活劇、コン・ゲームなんである。
こんな本を読んでしまうと、気がでかくなって、もうさ、なんだっていいぜぇぇぇぇ、どわぁあああああああああああーーーという気分である。今回の原稿、一/五ぐらいどわぁあああああああああああああああーにしても大丈夫どわぁぁああああああああああー!ってぐらいデカイ気持ちになっている(せこい)。
と、億単位で銭が動く世界をのぞき見た後に、日垣隆『売文生活』(ちくま新書/七八〇円)を読むと涙がポロリ。帯は〝業界のタブー「原稿料」の真実〟って、この程度のことがタブーになってる業界……とまたも涙がポロリぴっころ。夏目漱石、筒井康隆、立花隆など作家の記述や発言に、著者自らの経験を照らし合わせ、時に噛み付き、時に分析する原稿料エッセイで、丁寧に頭を下げながら、ボディーブローをガツンガツン食らわせるような毒舌に萌え。ケラケラ笑いながら読みました。
柳治男『〈学級〉の歴史学 自明視された空間を疑う』(講談社/一五〇〇円)も、おもしろかった。学級とパックツアーが同じだって指摘には驚愕。対象が子どもか大人かの違いはあるけれど、どちらも〝十九世紀の産業革命が進行するさなか、イギリスにおいて大量に生み出された貧民を救済し、より善き生活へ導こうとする〟キリスト教の慈善活動から生まれてきたのだそうだ。
近代の発明である学級の歴史を検証し(マクドナルドのチェーンシステムとも比較される)、自明視され意識されなくなった学級というパッケージの弱点と欺瞞(ぎまん)を暴き、わいわい激論されている教育論争の見当外れをズバリと突く。教育システムに関する本でもあるけど、歴史を振り返ることでいかに物事を深く考えられるかという具体例としても、刺激的な一冊。
永浜敬子『ビバ☆いなかもん!』(講談社/九五二円)は、いわゆる郷土ネタの本なのだが、生ぬるいネタがゼロ、ディープなネタがぎっしり。そのせいで出身地以外のネタはぜんぜんわからない罠。呑み会用の一冊としてオススメ。
たとえば、ぼくの出身地、広島だと、こんなのが。
・電車通りで、路面電車と車が衝突した場面を一度は見たことがある。
・「合同産業」という会社の名前は聞いたことがあるが、どんな会社か知らない。
・中国飯店のサービスライスは罰ゲームかと思った。
ね。広島の人だけ「あぁあぁ」うなずいてください。もしくは、本書の自分の出身地を見て、爆笑するが吉。
新刊めったくたガイドで、ぼくの担当は、「小説以外」なのだが、スティーブ・ジャクソン&イアン・リビングストン『火吹山の魔法使い』(扶桑社/八〇〇円)は、俺担当でいいのか。約二○年ぶりに復活したゲームブック。シリーズ累計二○〇万冊を突破し、ブームを巻き起こしたので、当時熱狂した人も多いだろう。ゲームブックというのは、番号がつけられた物語を、選択肢にしたがってインタラクティブに進めるゲームスタイルの本。ひさしぶりに遊んだけど、当時やった時より面白かった。初期ゲームブックなので、物語性よりもゲーム性が高く、戦闘中心なのが新鮮。
廣野由美子『批評理論入門 「フランケンシュタイン」解剖講義』(中公新書/七八〇円)。第一部が小説技法篇、第二部が批評理論篇。ストーリーとプロットの明確な違い、「視点」という概念の曖昧さと「焦点人物」という用語など、マジで勉強になります。由美子っ、サンキュー。
村上宣寛『「心理テスト」はウソでした。受けたみんなが馬鹿を見た』(日経BP社/一五〇〇円)は、血液型性格診断から、ロールシャッハテスト、内田クレペリン検査、YGテストなど、心理テストがいかにいいかげんかを暴いた本。痛快! ちょっと論証が荒いんだけど、どの心理テストも、みんな、だめーーッだって。それが、就職試験や診察室で、まだ使われてるのも怖いっすな。
今月の漫画一冊! いや、ものすごい数の漫画が出てるので、毎月一冊、どう選ぼうか悩みに悩むのですが、すでに売れまくってるものや、有名漫画家さんの作品よりも、もっと売れてほしいッ、もしくは、この新人さんの作品に注目ッってのをセレクトするようにしています。
ということで、びっけ『真空融接』(ビブロス/五六二円)は、メジャーデビュー作。「補給者」は「供給者」の力を定期的にもらわなければ生きていけず、「供給者」は「補給者」に体内で生成した力を吸い取ってもらわなければ生きていけない。そして、力の受け渡しは、唇、つまりキス。というテーマに忠実な、というか、欲望に忠実な設定が素晴らしいボーイズラブ漫画。っても、良質な連作ラブストーリーで、キス以上の肉体描写はないので、そういうのが苦手って人にもオススメです。
【この読書日記が収録されている書籍】
(あたりをくるくる走り回りながら絶叫)すげぇぇぇ、すげぇぇですよ。度肝を抜かれました。気宇壮大!
『虚人魁人 康芳夫 国際暗黒プロデューサーの自伝』(庚芳夫/学研一七〇〇円)は、プロデューサー・庚芳夫の自伝。とんでもない男。
高校の文芸部時代には、原稿料なしで武者小路実篤から原稿をもらうなんてエピソードから始まって、あとは怒涛の雪だるま式に巨大化するすげぇすげぇープロデュース話の連発。
日本初のボクシングヘビー級公式試合「モハメド・アリ戦」の興行も、金なしコネなしの状態から、ぎりぎりの手練手管で成功させちゃう。人間とサルの間の生物オリバーくんを日本に連れてきたのも、この男。オリバーくんの子供を生みたいという女の子が現れ、オリバーくんとセックス!? なんて騒ぎも起きるほどの大フィーバー。五十パーセント近い視聴率もたたき出した。
総隊長は石原慎太郎のネス湖怪獣国際探検隊、人食い大統領アミンVS猪木、アラビア大魔法団興行、インディ500、人食いトラVS空手、ノアの方舟探索プロジェクト、奇書『家畜人ヤプー』プロデュース。
漫画じゃない。法螺(ほら)じゃない。全部、実際に彼が仕掛けた異形の興行の数々なのだ。
この男、奇天烈で、豪快で、命知らず。人生が、大ロマン、大冒険活劇、コン・ゲームなんである。
こんな本を読んでしまうと、気がでかくなって、もうさ、なんだっていいぜぇぇぇぇ、どわぁあああああああああああーーーという気分である。今回の原稿、一/五ぐらいどわぁあああああああああああああああーにしても大丈夫どわぁぁああああああああああー!ってぐらいデカイ気持ちになっている(せこい)。
と、億単位で銭が動く世界をのぞき見た後に、日垣隆『売文生活』(ちくま新書/七八〇円)を読むと涙がポロリ。帯は〝業界のタブー「原稿料」の真実〟って、この程度のことがタブーになってる業界……とまたも涙がポロリぴっころ。夏目漱石、筒井康隆、立花隆など作家の記述や発言に、著者自らの経験を照らし合わせ、時に噛み付き、時に分析する原稿料エッセイで、丁寧に頭を下げながら、ボディーブローをガツンガツン食らわせるような毒舌に萌え。ケラケラ笑いながら読みました。
柳治男『〈学級〉の歴史学 自明視された空間を疑う』(講談社/一五〇〇円)も、おもしろかった。学級とパックツアーが同じだって指摘には驚愕。対象が子どもか大人かの違いはあるけれど、どちらも〝十九世紀の産業革命が進行するさなか、イギリスにおいて大量に生み出された貧民を救済し、より善き生活へ導こうとする〟キリスト教の慈善活動から生まれてきたのだそうだ。
近代の発明である学級の歴史を検証し(マクドナルドのチェーンシステムとも比較される)、自明視され意識されなくなった学級というパッケージの弱点と欺瞞(ぎまん)を暴き、わいわい激論されている教育論争の見当外れをズバリと突く。教育システムに関する本でもあるけど、歴史を振り返ることでいかに物事を深く考えられるかという具体例としても、刺激的な一冊。
永浜敬子『ビバ☆いなかもん!』(講談社/九五二円)は、いわゆる郷土ネタの本なのだが、生ぬるいネタがゼロ、ディープなネタがぎっしり。そのせいで出身地以外のネタはぜんぜんわからない罠。呑み会用の一冊としてオススメ。
たとえば、ぼくの出身地、広島だと、こんなのが。
・電車通りで、路面電車と車が衝突した場面を一度は見たことがある。
・「合同産業」という会社の名前は聞いたことがあるが、どんな会社か知らない。
・中国飯店のサービスライスは罰ゲームかと思った。
ね。広島の人だけ「あぁあぁ」うなずいてください。もしくは、本書の自分の出身地を見て、爆笑するが吉。
新刊めったくたガイドで、ぼくの担当は、「小説以外」なのだが、スティーブ・ジャクソン&イアン・リビングストン『火吹山の魔法使い』(扶桑社/八〇〇円)は、俺担当でいいのか。約二○年ぶりに復活したゲームブック。シリーズ累計二○〇万冊を突破し、ブームを巻き起こしたので、当時熱狂した人も多いだろう。ゲームブックというのは、番号がつけられた物語を、選択肢にしたがってインタラクティブに進めるゲームスタイルの本。ひさしぶりに遊んだけど、当時やった時より面白かった。初期ゲームブックなので、物語性よりもゲーム性が高く、戦闘中心なのが新鮮。
廣野由美子『批評理論入門 「フランケンシュタイン」解剖講義』(中公新書/七八〇円)。第一部が小説技法篇、第二部が批評理論篇。ストーリーとプロットの明確な違い、「視点」という概念の曖昧さと「焦点人物」という用語など、マジで勉強になります。由美子っ、サンキュー。
村上宣寛『「心理テスト」はウソでした。受けたみんなが馬鹿を見た』(日経BP社/一五〇〇円)は、血液型性格診断から、ロールシャッハテスト、内田クレペリン検査、YGテストなど、心理テストがいかにいいかげんかを暴いた本。痛快! ちょっと論証が荒いんだけど、どの心理テストも、みんな、だめーーッだって。それが、就職試験や診察室で、まだ使われてるのも怖いっすな。
今月の漫画一冊! いや、ものすごい数の漫画が出てるので、毎月一冊、どう選ぼうか悩みに悩むのですが、すでに売れまくってるものや、有名漫画家さんの作品よりも、もっと売れてほしいッ、もしくは、この新人さんの作品に注目ッってのをセレクトするようにしています。
ということで、びっけ『真空融接』(ビブロス/五六二円)は、メジャーデビュー作。「補給者」は「供給者」の力を定期的にもらわなければ生きていけず、「供給者」は「補給者」に体内で生成した力を吸い取ってもらわなければ生きていけない。そして、力の受け渡しは、唇、つまりキス。というテーマに忠実な、というか、欲望に忠実な設定が素晴らしいボーイズラブ漫画。っても、良質な連作ラブストーリーで、キス以上の肉体描写はないので、そういうのが苦手って人にもオススメです。
【この読書日記が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする