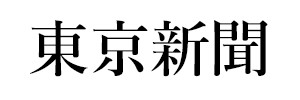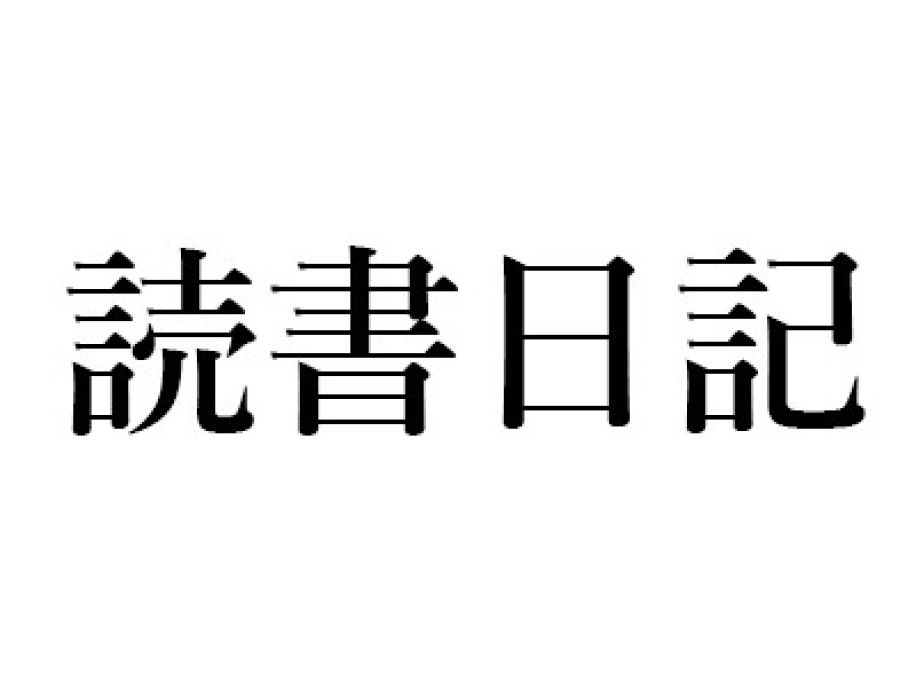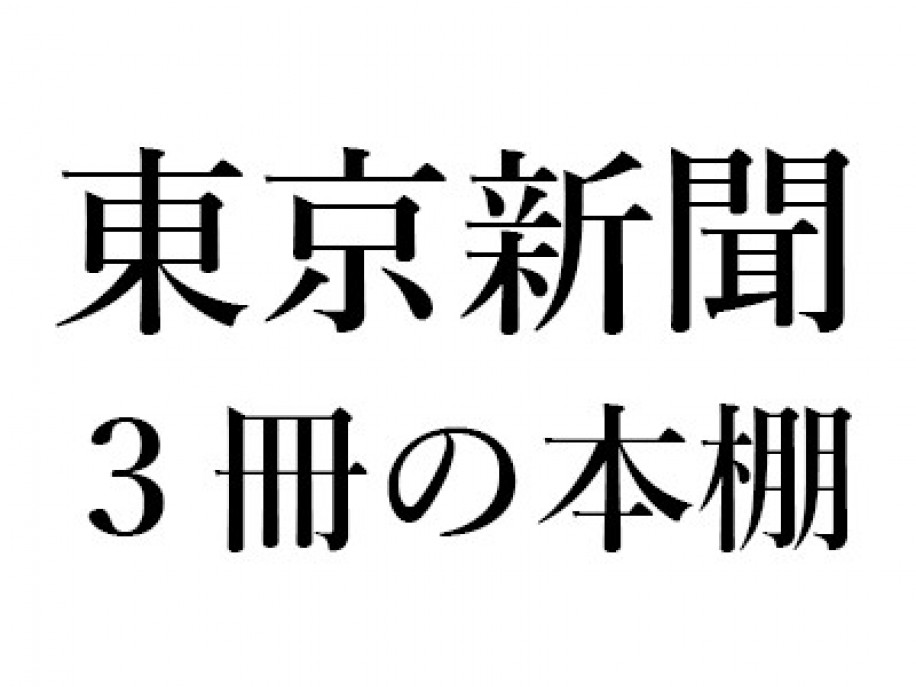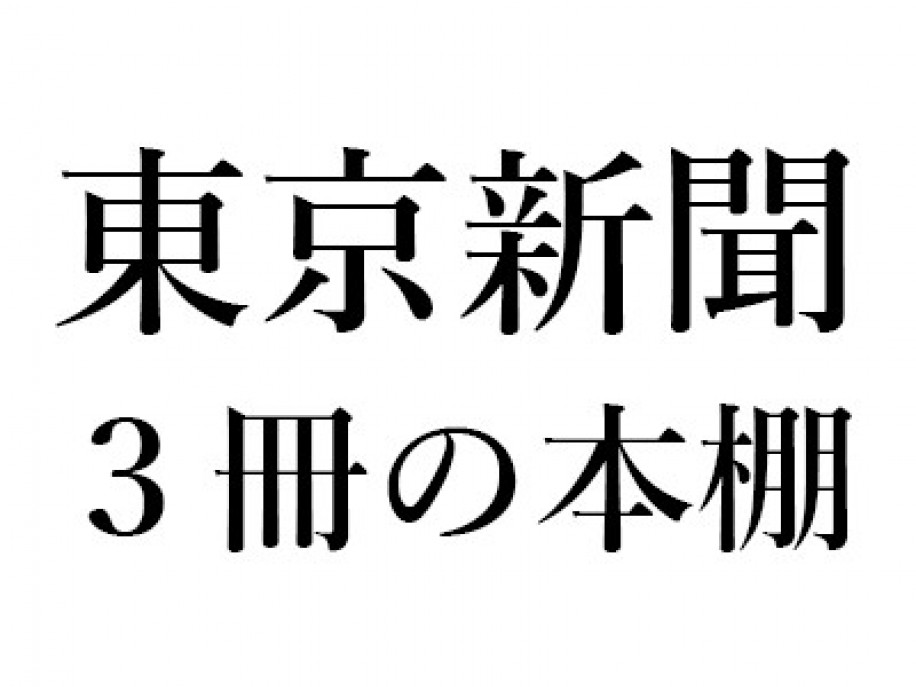読書日記
とみさわ昭仁『無限の本棚 増殖版』(筑摩書房)、デルフィーヌ・ミヌーイ『シリアの秘密図書館』(東京創元社)、ミキータ・ブロットマン『刑務所の読書クラブ』(原書房)
なぜ本を集めるのか
人間は集めてしまう生き物である。「病膏肓(やまいこうこう)に入(い)る」という言葉があるが、コレクターというのはこの症状に陥った人々だ。病を極め尽くせば尊敬や名声を得られたりもしようが、大抵は途中で力尽きる。カネも場所も有限なのだ。だが、〔1〕とみさわ昭仁『無限の本棚 増殖版-手放す時代の蒐集(しゅうしゅう)論』(ちくま文庫・929円)はその先へ行くことを考え抜き、行ってしまう。「蒐集原人」を自称するとみさわは、なぜ自分は集めるのか、そもそも集めるとは何か、果たして自分はモノを集めているのかと、集める行為と集められるモノについて自省と分析をひたすら深めていく。これはもはや思想書である。そして到達した答えは…エアコレクション!
同業者と話をしていると、知る人はみな彼をリスペクトしているのがわかる。理由の一端は本書を読むと見えるはずだ。
同じ「集める」でも、〔2〕デルフィーヌ・ミヌーイ『シリアの秘密図書館-瓦礫(がれき)から取り出した本で図書館を作った人々』(藤田真利子訳、東京創元社・1,728円)は悲痛だ。「アラブの春」後、シリアは内戦状態に陥った。アサド政権に抵抗する人々は首都ダマスカス付近の町ダラヤに籠城したが、政府軍はダラヤを封鎖し殲滅(せんめつ)攻撃を仕掛けた。絶望的な状況の中、若者たちは書物に自由と希望を見いだす。破壊された町や家屋から本を掘り起こし、地下に粗末な図書館を造ったのだ。IS(「イスラム国」)も乗り込んで三つ巴(どもえ)になったところに、各国勢力の思惑までが絡んだシリア内乱。どちらに義があるのか断言できる自信はない。ただ、つまらない自己啓発書にさえ希望を見つけ出し抵抗の糧にした彼らの姿には真実を感じる。
〔3〕ミキータ・ブロットマン『刑務所の読書クラブ-教授が囚人たちと10の古典文学を読んだら』(川添節子訳、原書房・2,160円)は反対に、書物(文学)の無力さを露(あら)わにした珍しい本だ。四十代半ばの女性で精神分析学者・文学研究者のミキータが、強盗や殺人などの凶悪犯罪で死刑や無期懲役の判決を受けた囚人十数名を相手に開催した読書会の記録なのだが、彼女の思惑はことごとく外れる。
これはと選んだバロウズ『ジャンキー』はそっぽを向かれ、ナボコフ『ロリータ』は質の悪い変態野郎と一蹴される。読書に熱心に見えた囚人も、奇跡的に出所すると本など見向きもしなくなってしまう。読書が暇つぶしですらなかった彼らの現実に、ミキータは最後「私が差し出せるものは文学しかない」と絶望気味に漏らすのである。
ALL REVIEWSをフォローする