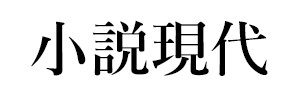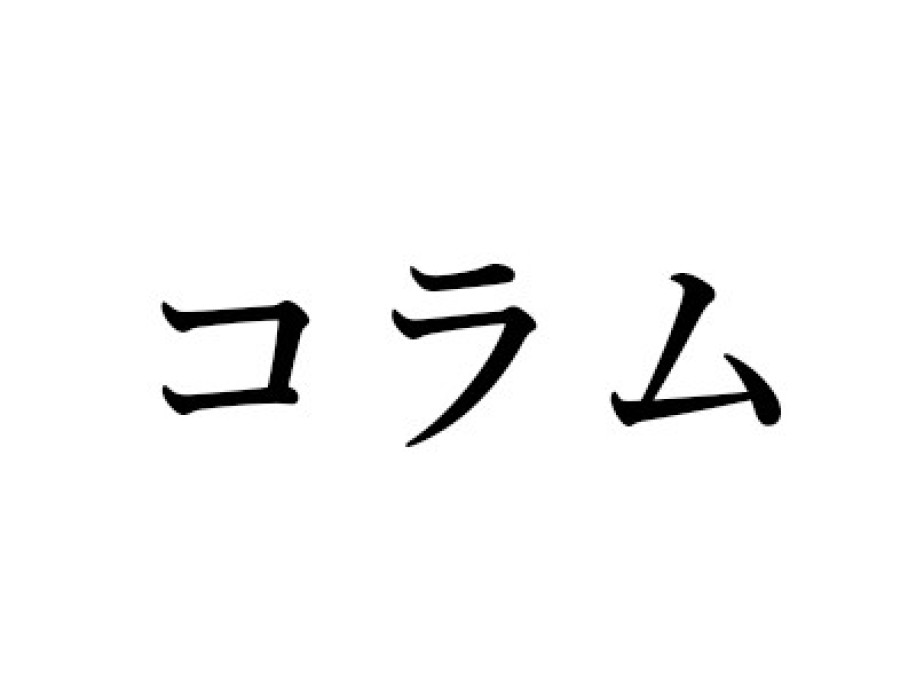コラム
サイモン・シン『フェルマーの最終定理』(新潮社)、神谷 敏郎『あるミイラの履歴書』(中央公論新社)、アイリック・ニュート『世界のたね』(KADOKAWA/角川学芸出版)
科学は世紀を超えて
もの書きという文系ぽいことをしている私だが、高校の二年くらいまでは、理数系にも興味があった。「物理」なる科目を習いはじめたときは、ふだん偶然としか思っていない物の運動に、ちゃんと法則があって、複雑な現実を、単純な式で表せるのが、面白いと思った。むろん、高校生の物理だから「真空状態においては」とか「摩擦はないものとする」といった、式をやさしくするための条件付きではあったけれど。理数系に挫折を感じたのは、「化学」において。ちまちまとした暗記ができない私は、元素表を覚えなければならない時点で、
(面倒だなあ)
と思っていたが、決定的となったのは、二学期の中間テストだ。
詳細は忘れたが、何かに含まれる物質の量を求めよ、というもの。返されてみると、思考のすじみちとしては合っているようだが、何行も並べた式の最後の最後で間違っていた。
設問中「純度は九九・八パーセントとする」とあり、おおざっぱな私は、
「だから、ほぼ百と思っていいってことか」
と解釈した。が、そうではなく、百分の九九・八を掛けなければならなかったのだ。したがって、大きなバッテンが。
(こんな細かいことまで、考えに入れなきゃならないなんて!)
化学とはソリが合わない、というのが高二での結論。〇・一グラムのラジウムを取り出すのに、八トンものタール状のものをかき混ぜ続け分離させたという、キュリー夫人の根気にはつくづく頭が下がる。
挫折のもうひとつは、数学の微分、積分。そのあたりになると、つまるところ何をしたいものなのか、感覚的にとらえきれなくなり、授業についていく気力が、糸が切れたように失われた。自分の数学的思考力の限界に突き当たったと、はっきりと感じた。
自分にないものにあこがれる、人間の性か、今もときどき理数系のテーマの本が読みたくなる。サイモン・シン著、青木薫訳『フェルマーの最終定理』(新潮社)は、それでもちょっと難し過ぎるかもと、躊躇(ちゅうちょ)していたが、書店で訳者あとがきを読んでひかれた。
訳者が、かつて大学の理学部に進むことになったとき、高校の恩師が、将来を思いやり、クギを刺したそうだ。きみの頭は、数論をやるには粗雑すぎる――。理学部に入ってみれば、なるほど数学科をめざす人は「脳味噌の配線」が自分とは違う、と思ったとか。
レベルは違うが、おおざっぱさにおいてはひけをとらない私なので、親近感を抱いたのである。フェルマーの最終定理とは、何ぞや。「xn + yn = zn nが2より大きい場合、この方程式は整数解を持たない」。
形としてはシンプルきわまりないこの定理が、実に三世紀半にわたり、数学者を悩ませてきた。証明ができないのだ。その間科学は、人間を月に送り、遺伝子を組み替えるまでに進歩した。が、この定理に関しては、十七世紀から時が止まったまま。
一九九五年、イギリス人アンドリュー・ワイルズが八年間の格闘の末、ついに決着をつけた。その成功には、核分裂やDNAの発見に匹敵するほどの意義があるという。
このノンフィクションでは、ワイルズを中心に、過去にも次々と証明に挑んでは敗れ去った数学界の英雄たちにも光をあてる。フェルマーの最終定理には「まるで小説のような歴史があるのです」とワイルズ。「偉大な数学者たちが失敗していればいるほど、この問題は挑戦に値する大きな謎となるのです」。
最終定理の含むテーマを、完全に理解できる者は、世界でも五、六人しかいないらしい。
私も数学的にはちんぷんかんぷんだったが、十七世紀以来の難問が、二十世紀に提示された別の問題と結びつき、決着への道すじが開けたところでは、興奮をしかと追体験できた。
数学を前進させるものは何か、数学者を奮い立たせるものは何かについてが描かれた「魅力あふれる冒険物語」との著者の言葉に偽りはない。ちなみに、決着への跳躍板となった「別の問題」とは、「谷山=志村予想」と呼ばれる、日本人によるもの。ワイルズ報道においては大きく扱われなかった彼らの業績に、きちんと筆を及ぼしているところに、科学者である著者の良心を感じる。
【単行本】
こちらは、数奇な運命をたどったミイラのお話。神谷敏郎著『あるミイラの履歴書』(中公新書)。二千八百年前の古代エジプトで、生を終えたひとりの女性神官が、永遠の命を願う人々により、ミイラにされた上、葬られた。ナポレオンのエジプト遠征を機に発掘調査が進められ、明治期にフランスの一外交官により、東京大学医学部に譲り渡されたというのが、伝えられる履歴。
眠りを覚ましたのは、東大紛争だ。資料保全のため、医学部本館大講堂前ロビーから標本室に移動することとなり、助手であった著者は、お守り役をおおせつかった。やがて、CT撮影のため、三重の棺の「箱入り娘」は百年めの外出となるが、検査の結果、なんと男性だった!
彼(女)と縁ができたことから、世界のミイラの例、日本におけるミイラの歴史、ミイラの「作り方」までを、一冊にまとめた。鼻の穴から脳髄を掻き出す難しさなど、もともとが解剖学者の著者らしい言及だ。臓腑摘出も、財力の乏しい者はていねいに施されず、下剤で腸を洗浄されるだけという、ちょっと哀しいお話も。死後の世界も金次第か。
著者個人としては、いつかミイラが再びエジプトの地で眠りにつくのが願いという。それまでの間は、単にめずらしいものとしてでなく、きちんとした調査を行うのが、遠来の異邦人に対しての、また、死者に対しての礼儀であり、国際的科学的なマナーではないかと。ミイラへの接し方に込められた節度と愛が、好ましい。
アイリック・ニュート著、猪苗代英徳訳『世界のたね』(NHK出版)は、ギリシャ時代から現代までの科学の歴史を俯瞰(ふかん)して、高校の世界史ではぶつ切りだった、人間の精神の流れをとらえる、見取り図ともいえる。
むろん、その中にいる人々は、全体の絵がどんなものか知らない。真理の探究の歴史は、ジグソーパズルに似ている、と著者。研究者は、ただひたすら自分にとってのテーマを追い続けるだけ。
それがときおり、絵の中のほんの小さな部分、けれどもなくてはならない一ピースの発見につながるのだ。
【単行本】
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする