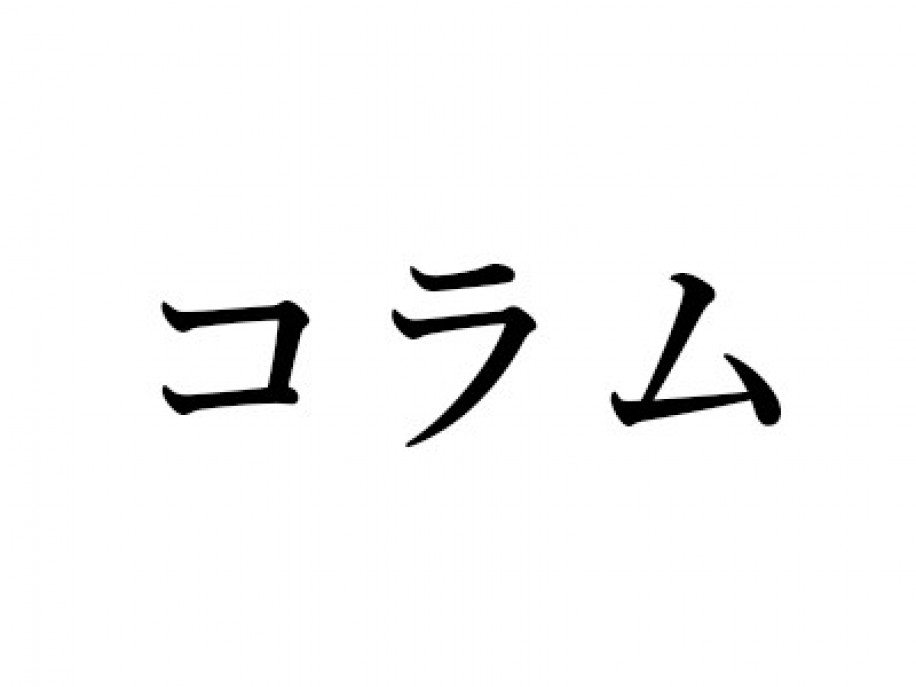コラム
森 まゆみ『鴎外の坂』 (新潮社)
図書館は近いのが一番だ。
調べ物をして書く仕事であるのに、家は狭いしお金はないし。図書館にない資料は古本屋さんで探す。
だから引越せない。自転車で十五分以内に芸大の図書館(音楽・美術)、東大明治新聞雑誌文庫、お茶の水女子大女性資料センターなどがある。だが、この二十年、いちばんお世話になっているのは、団子坂の上にある文京区立鷗外記念本郷図書館だ。
とにかく仕事場にいく行き帰りに前を通るのだ。坂の途中にある汐見保育園に末っ子を預けていたときは、小学生の上の子たちはいつも学童保育の終わったあと、図書館の児童室で私を待っていた。いやたのしそうに本を読んでいた。
文京区は図書館と保育園行政だけは進んでいる。現場の方の努力だと思うが、十数万の区民に十二館ある。となりの台東区は同じくらいの人口で三館しかない。ときどき思う。文京区には大学や出版社も多く、書庫をもつ蔵書家も多いんだもの、この狭い区にいったいどれくらい本が埋蔵されているのだろうかと。考えるだけで気が遠くなる。
通称、鷗外図書館はその名の通り、森鷗外の旧居跡にある(ALLREVIEWS事務局注:平成18年4月に徒歩3分ほどの地に移転)。旧千駄木町十九番地。鷗外が三十歳の明治二十五年から六十歳で大正十一年に亡くなるまで、ほぼ生涯の半分を過ごした土地である。戦後、一部は公園となり末子の類さんが千朶(せんだ)書房を開いておられたところを区が譲りうけ、谷口吉郎氏の設計で図書館が建てられた。
一館ごとの蔵書がそう多くないのは、文京区の図書館の特長である。杉並や横浜のような一極集中型の中央図書館ではない。
私がここを好くのは、近いことに加え、なんといっても鷗外先生の旧居だからである。一階のいい場所には森鷗外記念室があって、鷗外の原稿から、文人たちとやりとりした書簡から、観潮楼にかかっていた額から、愛用のジョッキやペーパーナイフが並んでいる。中には仲の悪い母と妻を仲良くさせようと、鷗外が買った双六盤まで並んでいる。
そして書見に目が疲れれば、書籍カードボックスの脇から庭に出られる。観潮楼は一時、町工場に貸して昭和十二年、失火により焼失、そのあと昭和二十年の空襲で跡かたもなくなったが、庭の銀杏や沙羅の樹は残っている。鷗外、緑雨、露伴の写真で有名な「三人冗語の石」も丸みをおびてそのままである。ベンチもあり、晴れた日も雨の日も庭を眺めていると良い気分だ。
じつは森家の本門は団子坂にではなく、藪下道に面しており、昔の玄関あとの敷石はそのまま残っている。通称見晴しといって、私が子どもの頃も松坂屋のアドバルーンが見え、その昔は両国の花火やツェッペリン飛行船が見えたと近所の人に聞く。いまでは学校の建物にさえぎられ何も見えない。
さらに、鷗外図書館は鷗外に関する本や研究論文をあたうかぎり集め、分類もしている。さっきのカードボックスをあけると、それらの所蔵資料名が並んでいるが、これは鷗外の作品別、鷗外とかかわりのあった人別にも引くことができ、大変便利である。鷗外図書館がこんなに至近距離になければ、私は『鷗外の坂』(新潮社)を書き上げることはできなかっただろう。
私のみではない。地域雑誌「谷中・根津・千駄木」は創刊以来、十四年間、鷗外図書館の団体貸出しで資料を借りている。通常の二週間でなく一ヵ月の期限で何冊でも借りられるうえ、日本文学関係の資料は全集や評論、伝記も充実しているのがありがたい。文京区の図書館は館ごとにテーマを決めてメリハリをつけて集めている。たとえば地図や地誌は小石川図書館に、本郷ゆかりの文学者は真砂図書館に、というぐあいである。
館員は勉強熱心でリファレンスに応じてくれ、もちろんどの本が区内のどこの館にあるかはパソコンですぐ分かるし、区内になくても都立中央図書館や日比谷図書館などから相互貸借で二、三日のうちに本が届く。
おそらく私の納める区民税をはるかに越える本を図書館で借りていると思う。だから鷗外図書館から紹介されたのですが、と地域史についての問合せがあると、せっせと答えている。そのうえ、毎月のように「文学講演会」を開き、木下順二、吉村昭先生から、島田雅彦、田中優子氏ら気鋭の若手まで来て下さって、無料でお話が聞けるのだから狭い部屋は立錐の余地がない。
鷗外はいいけれど、と私は本郷ゆかりのもう一人の文豪を思う。同じ千駄木町五十七番地で『吾輩は猫である』や『坊っちゃん』を書いた夏目漱石についても、これくらいの資料整備がされ、誰でも調べられるといいと思う。日本中に、その町の出身者というだけで、レベルを問わず文学館は多いが、一番読まれている国民作家漱石について、充実した資料館があると聞かないのはさびしいことである。
【このコラムが収録されている書籍】
調べ物をして書く仕事であるのに、家は狭いしお金はないし。図書館にない資料は古本屋さんで探す。
だから引越せない。自転車で十五分以内に芸大の図書館(音楽・美術)、東大明治新聞雑誌文庫、お茶の水女子大女性資料センターなどがある。だが、この二十年、いちばんお世話になっているのは、団子坂の上にある文京区立鷗外記念本郷図書館だ。
とにかく仕事場にいく行き帰りに前を通るのだ。坂の途中にある汐見保育園に末っ子を預けていたときは、小学生の上の子たちはいつも学童保育の終わったあと、図書館の児童室で私を待っていた。いやたのしそうに本を読んでいた。
文京区は図書館と保育園行政だけは進んでいる。現場の方の努力だと思うが、十数万の区民に十二館ある。となりの台東区は同じくらいの人口で三館しかない。ときどき思う。文京区には大学や出版社も多く、書庫をもつ蔵書家も多いんだもの、この狭い区にいったいどれくらい本が埋蔵されているのだろうかと。考えるだけで気が遠くなる。
通称、鷗外図書館はその名の通り、森鷗外の旧居跡にある(ALLREVIEWS事務局注:平成18年4月に徒歩3分ほどの地に移転)。旧千駄木町十九番地。鷗外が三十歳の明治二十五年から六十歳で大正十一年に亡くなるまで、ほぼ生涯の半分を過ごした土地である。戦後、一部は公園となり末子の類さんが千朶(せんだ)書房を開いておられたところを区が譲りうけ、谷口吉郎氏の設計で図書館が建てられた。
一館ごとの蔵書がそう多くないのは、文京区の図書館の特長である。杉並や横浜のような一極集中型の中央図書館ではない。
私がここを好くのは、近いことに加え、なんといっても鷗外先生の旧居だからである。一階のいい場所には森鷗外記念室があって、鷗外の原稿から、文人たちとやりとりした書簡から、観潮楼にかかっていた額から、愛用のジョッキやペーパーナイフが並んでいる。中には仲の悪い母と妻を仲良くさせようと、鷗外が買った双六盤まで並んでいる。
そして書見に目が疲れれば、書籍カードボックスの脇から庭に出られる。観潮楼は一時、町工場に貸して昭和十二年、失火により焼失、そのあと昭和二十年の空襲で跡かたもなくなったが、庭の銀杏や沙羅の樹は残っている。鷗外、緑雨、露伴の写真で有名な「三人冗語の石」も丸みをおびてそのままである。ベンチもあり、晴れた日も雨の日も庭を眺めていると良い気分だ。
じつは森家の本門は団子坂にではなく、藪下道に面しており、昔の玄関あとの敷石はそのまま残っている。通称見晴しといって、私が子どもの頃も松坂屋のアドバルーンが見え、その昔は両国の花火やツェッペリン飛行船が見えたと近所の人に聞く。いまでは学校の建物にさえぎられ何も見えない。
さらに、鷗外図書館は鷗外に関する本や研究論文をあたうかぎり集め、分類もしている。さっきのカードボックスをあけると、それらの所蔵資料名が並んでいるが、これは鷗外の作品別、鷗外とかかわりのあった人別にも引くことができ、大変便利である。鷗外図書館がこんなに至近距離になければ、私は『鷗外の坂』(新潮社)を書き上げることはできなかっただろう。
私のみではない。地域雑誌「谷中・根津・千駄木」は創刊以来、十四年間、鷗外図書館の団体貸出しで資料を借りている。通常の二週間でなく一ヵ月の期限で何冊でも借りられるうえ、日本文学関係の資料は全集や評論、伝記も充実しているのがありがたい。文京区の図書館は館ごとにテーマを決めてメリハリをつけて集めている。たとえば地図や地誌は小石川図書館に、本郷ゆかりの文学者は真砂図書館に、というぐあいである。
館員は勉強熱心でリファレンスに応じてくれ、もちろんどの本が区内のどこの館にあるかはパソコンですぐ分かるし、区内になくても都立中央図書館や日比谷図書館などから相互貸借で二、三日のうちに本が届く。
おそらく私の納める区民税をはるかに越える本を図書館で借りていると思う。だから鷗外図書館から紹介されたのですが、と地域史についての問合せがあると、せっせと答えている。そのうえ、毎月のように「文学講演会」を開き、木下順二、吉村昭先生から、島田雅彦、田中優子氏ら気鋭の若手まで来て下さって、無料でお話が聞けるのだから狭い部屋は立錐の余地がない。
鷗外はいいけれど、と私は本郷ゆかりのもう一人の文豪を思う。同じ千駄木町五十七番地で『吾輩は猫である』や『坊っちゃん』を書いた夏目漱石についても、これくらいの資料整備がされ、誰でも調べられるといいと思う。日本中に、その町の出身者というだけで、レベルを問わず文学館は多いが、一番読まれている国民作家漱石について、充実した資料館があると聞かないのはさびしいことである。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする