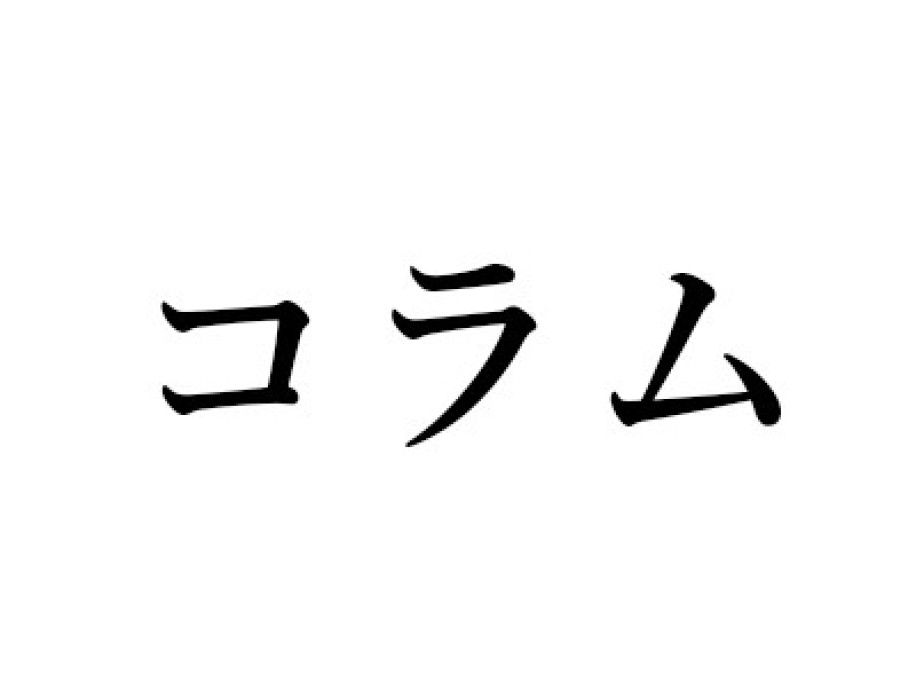コラム
栄原 永遠男 『正倉院文書入門』(角川書店)、杉本 一樹『正倉院 あぜくら通信』(淡交社)
古代の「息吹」を伝えるために
毎年十月ともなると、正倉院展が奈良の国立博物館で開催される。日本の古代史ファンのみならず、研究者も待ちかねたかのようにして見にくるが、多くの人の目は出品された華麗で精巧な工芸品や珍しい宝物の数々に目が釘付けになる。昨年は特に「螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんごげんびわ)」が出されて人だかりになり、今年は織田信長が一部を切り取ったという「蘭奢待(らんじゃたい)」の香木が出され賑わっていた(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆年は2011年)。しかし文書(もんじょ)を展覧している部屋になると、疲れのせいもあってか、人だかりもなくなってくるのだが、その付近から熱心に見入っているのは、古代史の研究者とみてよいだろう。
栄原永遠男(さかえはらとわお)氏はまさにその一人であって、正倉院文書に魅せられ、正倉院文書の研究に邁進してきた。活字本『大日本古文書』が刊行され、写真版もあるので、傍目から見ると研究はたやすいかに見えるが、どっこい、相当な難物である。
文書が二次利用され、切られ、バラバラにされ、継がれるなどして原型を探るのが容易ではない。難解な用語や意味不明な符牒なども多い。
『正倉院文書入門』はそうした正倉院文書解読の手引きである。正倉院文書の紹介にはじまって、その整理がどう行なわれてきたのか、実際にどう調べたらよいのかを丁寧に解説する。具体的に光明皇后などが中心になって行なわれた写経事業を例にとって、写経所関係の文書を解読してゆく。
写経所とはどういうものかを語り、「造東寺司解(ぞうとうじしげ)」の解読を通じて様々な用語の説明を行い、写経事業の実際を丹念に探ってゆく。職人技ともいうべきこの作業を著者は後学に伝えるべくこの本を著したと語るが、この作業は正倉院文書だけでなく、広く紙背(しはい)文書の復元に役にたつ。
もちろん、単に復元するだけではない。写経所文書にうかがえる文芸の香りを引き出し、本来の探究の目的である写経に籠められ王権の祈りを探ってゆく。文書に息吹をあたえる緻密な作業がよく伝わってくる。
本書を読むなか、思い起こしたのが杉本一樹氏の『正倉院 あぜくら通信』である。正倉院事務所長の著者が、正倉院の日常の業務を通じて、その歴史や所蔵する宝物の概要、倉の御開封から始まる一年の行事などを語る、こちらは正倉院入門といえよう。
雑誌『なごみ』に連載されたものをまとめたもので、正倉院の概観に始まり、正倉院の一年の動きを淡々と、しかし目をきらっと光らせ、さわやかに語っている。特に正倉院という場とそこに納められた宝物、それらに深く関わってきた人、三つの関係を注意深く探ってゆく。
宝物が納められた倉の問題、宝物に関与してきた聖武天皇・光明皇后から現代にいたるまでの管理に携わってきた人のあり方、御開封に始まる正倉院展の開催の裏方の動き、宝物の修理や復元・模倣の問題など、全十五章にわたって、正倉院の隅々まで案内してくれる。
近寄りがたい正倉院を身近に感じさせてくれるだけでなく、これだけ多くの時間、風雪に耐えて護られてきた正倉院を今後とも護ってゆく意義がひしひしと伝わってくる。
二つの本の著者はともに正倉院文書研究の先達である皆川完一氏の指導を受けたが、その皆川氏がつい最近になって亡くなられたことを聞いた。その冥福を祈るとともに、正倉院が今後よく伝えられ、その文書をはじめとする研究がさらに広がりをもつことを期待したい。
ALL REVIEWSをフォローする