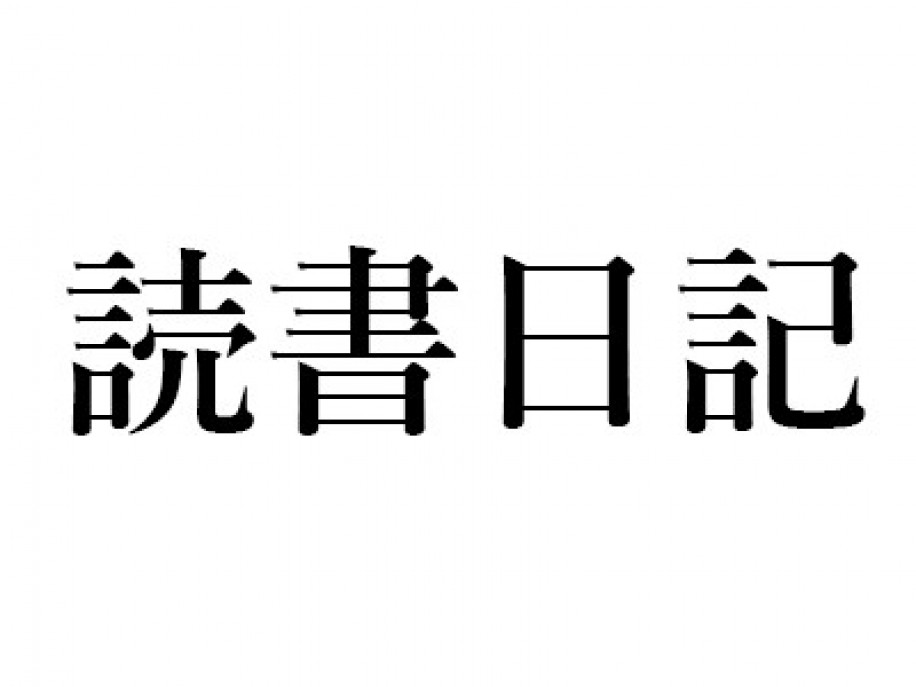後書き
『〈女帝〉の日本史』(NHK出版)
あとがき
このところ、日本では女性の政治家に関する話題が連日のようにテレビのニュースやワイドショーなどをにぎわしています。しかしその多くは、政治家としての品性や資質が疑われるというマイナスの評価を伴っているように思われます。もちろん女性政治家自身に問題があり、そうした報道が当たっている場合も少なくはないのですが、男性であればそれほど問題にならないようなことが、女性であるというだけでことさら問題となる場合もないとは言えません。こうしたこと自体、日本における女性政治家の少なさを暗示しているのではないでしょうか。その一方で、皇后の存在感はますます大きくなりつつあるように見えます。それとともに、女性皇族の話題にも事欠きません。彼女らは世俗の権力とは無縁で、国民の平安を日々祈っている無私の存在であるかのごとく報道されます。品性や資質の疑われる女性の政治家とは対照的にとらえられるわけです。
私は男性の政治学者ですが、こうしたマスコミのステレオタイプ的な報道の仕方に何ともいえない居心地の悪さをずっと感じてきました。一体なぜ、西洋諸国はもとより、東アジアでも女性の政治参加は着実に増えているのに、日本はそうならないのか。はじめから日本はそういう国だったのか。それを知るためには、目の前の現実からいったん離れて、歴史の起源にまでさかのぼるとともに、東アジアのなかで日本をとらえるという視点も同時にもつ必要があると思いました。
歴史には、ミクロな視点とマクロな視点の双方が必要です。歴史学者は前者だけを行い、後者は専門外として敬遠する傾向があります。しかしそれでは、いつまでたっても肝心の謎は解けません。本書で不十分ながら示した、〈女帝〉から歴史を見るという視点は、まだ土台ができたばかりです。今後は西洋の帝国や王国との比較も視野に入れながら、この遠大な研究をさらに続けてゆきたいと強く念じています。
本書は、二〇一六年三月から一一月にかけて、NHK出版で七回にわたって行われた講義をもとにしています。この間に天皇の退位をにじませた「おことば」が発表され、強い刺激を受けたことは序章で述べた通りです。本書の出版を勧めてくださった大場旦さん、構成を担当された澁川祐子さん、そして『団地の空間政治学』(NHKブックス、二〇一二年)で編集を担当されて以来、再び編集の労をとってくださった加納展子さんに心からの感謝をささげたいと思います。
二〇一七年九月一日 原武史
ALL REVIEWSをフォローする