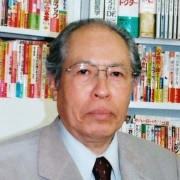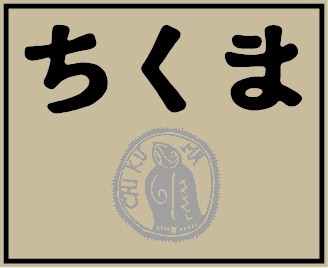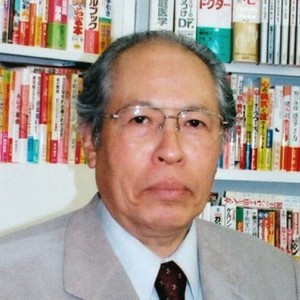自著解説
『日本語大博物館―悪魔の文字と闘った人々』(筑摩書房)
日本語の"縁の下"を覗く
高校生のころ、「雑木林」ということばは国木田独歩によってつくられたとか、「含羞」ということばは太宰治が考え出したという話を文学全集の月報などで読み、わけもなく感動したものだ。そのうちに、明治以降の日本語は文学者がつくったものと、何となく思いこんでしまった。大学で私は財政学という、いまから思えば柄に合わない分野を専攻したが、浜口雄幸の金解禁などに関心をもったことから、昭和史に熱中するようになり、物書きとして独立した際には日本近代史を一つの看板として掲げるようになった。ここから、近代の日本語はどう成り立ったかというテーマを見つけるまで、ほんの一歩にすぎなかったが、もう一つ忘れられないことがある。それは二十歳台のサラリーマン時代の体験である。
一九五〇年代の半ばごろ、私は商社の貿易部門に勤務していたが、英文書簡と邦文書簡の能率の差に悩まされていた。英文は見よう見まねで打つこともできるが、邦文はまったく手におえない。夜間、残業でオフィスの英文タイプをポツリポツリ打ちながら、英文が機関銃とすれば邦文は幕末の大筒というほどの大差があると思ったものだが、さりとて当時急速に普及しつつあった片仮名の宛名表記や文書の片仮名化には、非常に抵抗を感じていた。
近代史関係の執筆活動を行うようになって、私の関心は少しずつ辞書をつくった人々の事績に向かった。はじめて近代的国語辞典を編んだ大槻文彦。戦争を挿む三十年以上を費やし、五十二万語の漢和辞典を編纂した諸橋轍次――。このような人たちの生涯を辿りながら、必然的に辞書づくりが一生の仕事にならざるをえなかった理由を考えさせられた。
その後に現れたのがワープロである。私は一九八三年(昭五八)からワープロを使い始めたが、すぐにシステム内部の辞書の優劣が、使い勝手をきめることに気づいた。初期の開発者たちは複雑な日本語文法をよく研究し、複雑かつ例外の多い内容をたくみにシステム化している。日本語の弱点は同音異義(異字)の多いことである。このままでは入力のたびに同音の漢字がいくつも出てきて、使い物にならないが、「一度使用した語彙を記憶する」というアイディアで乗り切ったのは画期的で、ブレイクスルーというにふさわしいものだったと思う。
辞書の編纂者もそうだが、近代から戦後にわたる日本語の発展は、じつはこのような"知の職人たち"の数々のイノベーションに負うところが多いのではないだろうか。
ただし、初期のワープロは辞書(正確には語彙データベース)がいかにも貧弱だったので、そのことを何かに書いたところ、「それなら、あなたが語彙を選んだらどうか」という提案があった。当時評判になりつつあったワープロソフト「一太郎」の開発元(ジャストシステム)である。面倒なことになったと思ったが、行きがかりでお手伝いをしているうちに、この会社が出していたユーザー情報誌に依頼され、日本語の歴史に関するエッセイを連載することになった。私は迷うことなく、日本語を縁の下の力持ちとして担った人々のことを書くことにした。辞書の編纂者についてはいうまでもなく、漢字を廃して片仮名やローマ字にせよと主張したような人々の情熱や時代背景にもふれることにしたのである。硬い内容と思われては困るので、写真図版をふんだんに入れた。これはカメラマン宇田和義氏の努力で、予期以上のものになったのはうれしかった。
以上が『日本語大博物館』執筆の経緯である。一九九四年(平成六)に上梓したさいには、私の著書としては注目され、百いくつかの書評・紹介が出た。図版ばかり褒められ、いささか複雑な思いをしたことも思い出す。
今回「ちくま学芸文庫」に収録されたものは、その後に集めた資料をすべて盛り込んだ増訂版である。これからも日本語という複雑な建物の、"縁の下"に目を向けて――いや、覗きこんでいきたい。
ちくま 2001年9月
筑摩書房のPR誌です。注目の新刊の書評に加え、豪華執筆陣によるエッセイ、小説、漫画などを掲載。
最新号の目次ならびに定期購読のご案内はこちら。
ALL REVIEWSをフォローする