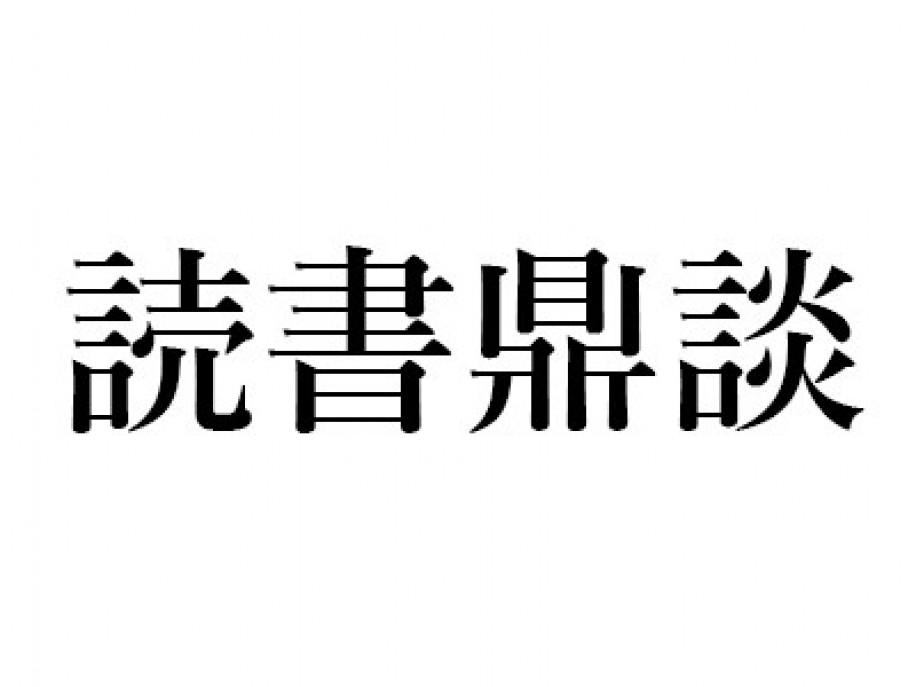書評
『日本語の発音はどう変わってきたか-「てふてふ」から「ちょうちょう」へ、音声史の旅』(中央公論新社)
音声を書きとどめる努力の足跡
古代日本は書写記号が模索されている最中に、漢字に出会った。万葉仮名は革命的な大発明だが、この創意に富んだ考案には致命的な欠点がある。表意文字が表音文字として用いられていたため、導入時の発音は必ずしも後世に伝わらない。そのことは鎌倉時代から気付かれ、日本の音韻についての探究が積み重ねられてきた。古代日本の音声を知るのに、中国の韻書が役に立った。韻書とは漢字を韻によって分類した音韻学書で、詩作には不可欠な参考書である。隋唐時代の韻書には発音が記されているから、これを参考に万葉時代の日本語の発音を復元することができた。
中世後期の発音が復元できたのは歴史的な偶然もあった。ポルトガル人宣教師が編纂(へんさん)した日本語の資料には、室町時代の音声がローマ字によって精度よく記録されているからだ。
本書の眼目は歴代の発音を録音機のように再生することではない。平たく言えば、日本語の音声史を概説したものである。ただ、結果として日本にはなぜ音声表記の規範がなかったのか、音声の正しい書き表し方を確立できないために、国語史にどのような混乱が生じたかが、音声表記の変遷を通して読み解かれた。
この問題を説明するため、藤原定家、契沖、本居宣長の三人の名が挙げられている。
『源氏物語』『古今和歌集』など平安時代の原本は平仮名で書かれた上、句読点もなく段落分けもない。鎌倉初期になって、もはや解釈と注釈がないと、読めなくなった。藤原定家の『下官集』は古文を書き記すときの留意事項を列挙している形でありながら、はじめて仮名遣いの規範を示した。その「定家仮名遣い」について、一つ一つの語に即して例示し、増補したのは南北朝の行阿(ぎょうあ)(源知行)の『仮名文字遣』である。中世以降、後者の方が長らく歌詠みたちに親しまれた。
近世になると、文化境域の拡大に伴い、「日本」に向ける想像力が新たな広がりを見せた。王朝文化の地域的限界に気付いた学者たちは「みやこ」にかわって、より広域的な象徴性を持つ「ヤマト」を精神の拠り所にした。彼らが『万葉集』に文化のルーツを求めたのはごく自然な成り行きであろう。万葉の注釈から始まった契沖の試みはやがて『和字正濫鈔(しょうらんしょう)』として実を結んだが、「五十音図」を命名し提案した契沖の仮名遣い論はずっと冷遇されたままであった。
十八世紀、木版印刷の興隆にしたがい、大衆的読み物の漢字の読み仮名には大混乱が起きた。本居宣長は古代の日本人が漢字の原音をそのまま受け入れたのではなく、日本語の音声に近い形に加工して表記したという認識を示した上、日本漢字音という新たな言語概念を用いて、音読みの仮名遣いを確定した。
明治に入ると、契沖と宣長の仮名遣いが教育現場に持ち込まれたが、発音の実態を反映する「現代仮名遣い」が告示されたのは終戦の翌年である。複雑極まりない音声表記の歴史だが、丁寧な解説と豊富な用例の引用により、より身近なものになった。新書という発行形態にしては、専門的な知識と知見がぎっしりと詰まった、重厚な一冊である。
ALL REVIEWSをフォローする