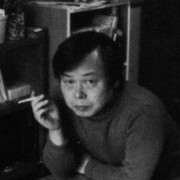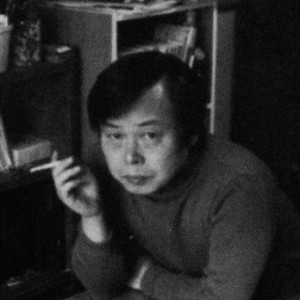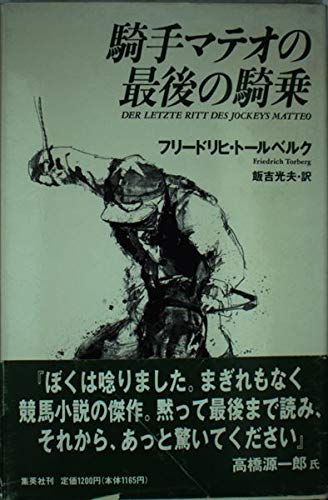書評
『オーストリア文学とハプスブルク神話』(書肆風の薔薇)
予言する死後解剖図
かつて中・東欧を中心に、ときにはスラブ諸国、イタリアの一部からスペイン、メキシコにまでかけて巨大な版図を世界にひろげた帝国があった。ハプスブルク家を帝統として維持された帝国はほぼ千年続き、一九一八年に消滅した。では、多民族多言語国家としてたえず民族主義的分離主義による解体の危機に脅かされながら、ヨーロッパ千年の激動の歴史のなかでこの国がなぜ安定を保っていられたのか。マグリスは、その秘密を「ハプスブルク神話」にさぐる。まずこの国の「超民族主義の神話は、神聖ローマ帝国のコスモポリタン精神を受け継ぎながらも、その精神の代用品でしかなく、したがって政治的活力たるダイナミズムはそこには欠如していた」。それゆえ隣国プロイセンの能動的な国家意志とは対照的に、不動主義ともいうべき官僚主義の静力学が政治原則となった。「のんべんだらりとやってゆくこと」、優柔不断とことなかれ主義。そのアジア的悪徳の裏にウィーン人の感覚的享楽主義が巣くう。生まれながらにして老成した人びとが、同時にモーツァルトからオペレッタにいたる感覚の洗練をはぐくんできたのである。
神話は現実が衰弱しはじめるとその構造を露呈してみせる。グリルパルツァー、ホーフマンスタール、シュニッツラーのような、おなじみの黄昏のウィーンの詩人たちに早くもきざした頽廃が、落日に照らされて「神話」のなげかけた影であるとすれば、臨終に居合わせたムージルやヨーゼフ・ロートは死後解剖作業からしてさらに正確な神話の骨格をあらわにして見せる。これは、詩人たちが提示したそれらの神話解剖図になかばは嫌悪をかくそうともせずに、しかし神話のアイロニーのためにいつしか死せる神話に巻き込まれて、ついには啓蒙的批評が詩に、政治が文学に呑み込まれゆく過程をまざまざと見せる、それ自体がアイロニカルな文学批評である。
それならば現実的効用とは一切無縁でありそうなものだが、中・東欧の現在をこの死後解剖図に重ねてみると、ありうべき中・東欧のシナリオが、すでに本書描く「ハプスブルク神話」にことごとく先取りされていると見えないこともない。政治経済の現実もまた、不動と思えるほどゆるやかに動く文化神話の母胎から生みだされるほかないからだろう。
【この書評が収録されている書籍】
朝日新聞 1990年10月21日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする