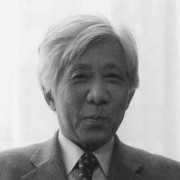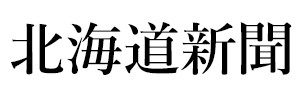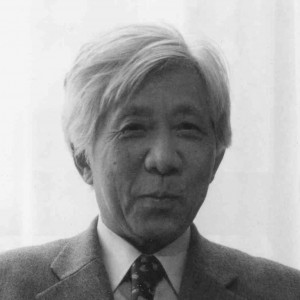書評
『澁澤・三島・六十年代』(リブロポート)
情勢論を抜け出た醒めた精神
五十を過ぎてからの澁澤龍彦は、一九六〇年代のことを語りたがらなかった。サド裁判当時の反社会性が旗じるしだった彼の文章を話題にすると、真顔で、やめてくれ、といった。あれは時代に言わされたんだ、本来のおれの言葉じゃない、という意味だったと思う。綺譚(きたん)を愛し、綺譚を語り、語りつくさないうちに他界したのが澁澤龍彦だと、私自身は考えているので、六〇年代の、オピニオン・リーダーのような発言を彼がみずから嫌悪するに至った道筋が、よく見える。しかしそれは、私のような澁澤と同い年の人間から見ての話で、一九六〇年の生まれだというこの本の著者が、一九七〇年に割腹自殺した三島由紀夫と、ポスト・三島をこそ生きた澁澤龍彦とを並べて論じ、何だったんだ、あの時代は、と問うのはごく自然なことだ。六〇年代はすでに甘やかな伝説のにおいを立てはじめている。そのあとの四半世紀が、ひたすら「表層化」の歴史だったからといって、六〇年代に何か「大義」があったと考えるのは、いたましい錯覚だ。思い入れも買いかぶりも無用、六〇年代こそは、ひたすら冷静に検証されるべきだと思う。
三島由紀夫が自殺して果てたとき、澁澤龍彦はきわめて調子の高い追悼文を発表した。親しかっただけに、衝撃はさぞ大きかったことだろう。しかし澁澤は、三島の死で、この怖(おそ)るべき観念的ラジカリストの呪(じゅ)縛から、少しずつではあれ、解放されていったと思う。澁澤は、ノスタルジーの人だった。彼の文学の核は、郷愁だった。幼年期と、人類の過去への、甘美をきわめた郷愁にこそ、彼の本領があった。三島由紀夫の、あのゲルマン的、法制史的な体質ほど、澁澤と遠いものはない。
倉林氏は、そこをよく掴(つか)んでいると思う。三島と澁澤を熱愛しながら、読んでいてどきっとするほど醒(さ)めている。だからこそ、この二人を相手どって、情勢論からみごと抜け出た六〇年代論が書けたのだろう。
ALL REVIEWSをフォローする