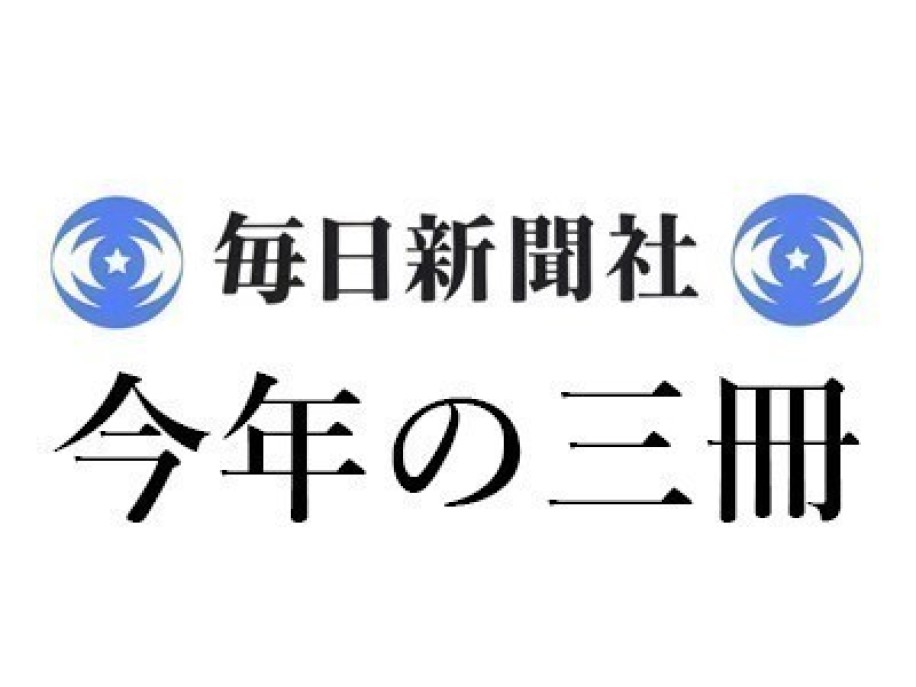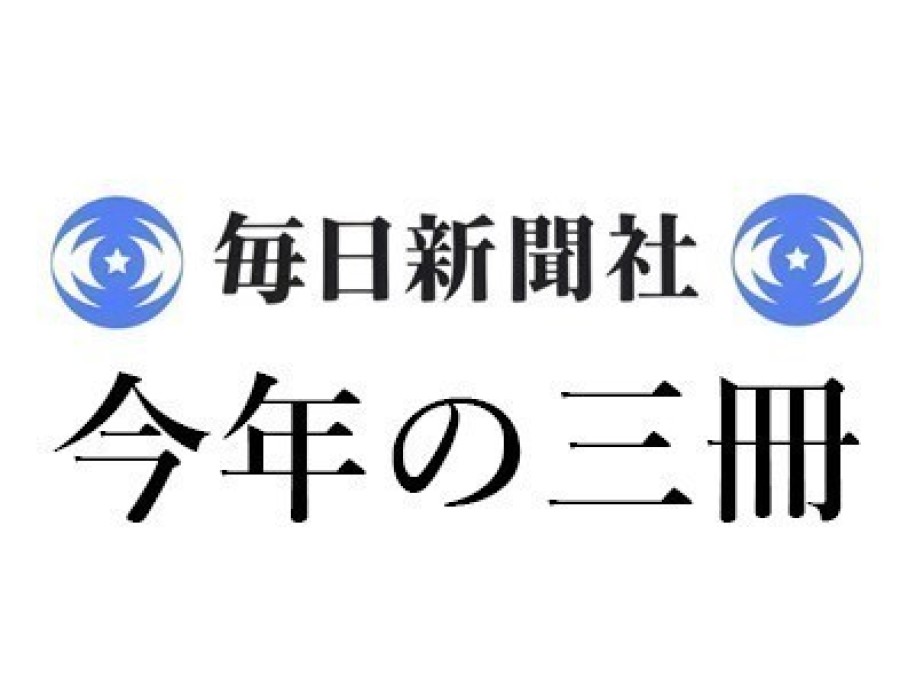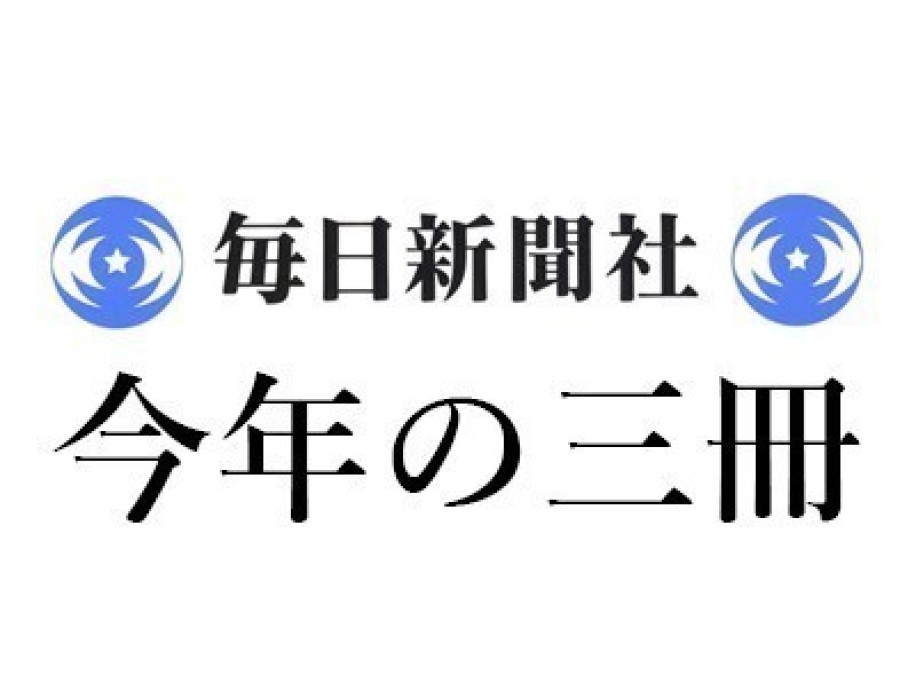解説
『詩・広場の孤独 他』(筑摩書房)
焦点なき収赦
いまから十八年ほど前、約三か月間、時事通信社の外信部でアルバイトをしたことがある(ALL REVIEWS事務局注:本解説執筆時期は1993年頃)。初め、外信部ということなので翻訳でもさせられるのかと思ったが、その方面の仕事はまったくなくて、完全な雑用だった。だが、本当のことを言えば、仕事の内容などどうでもよかったのである。というのも、堀田善衛の『広場の孤独』を読んだときの印象が強烈に残っていたので、ぜひ一度、外信部というところの雰囲気を味わってみたいと思っていたにすぎないからだ。そのときはちょうど、プノンペンがクメール・ルージュの攻勢にあって陥落寸前、サイゴンにも解放戦線が迫るという状況で、外信部のテレックスからは、生々しいニュースが刻々と打ち出されていた。現在、外交評論家として活躍している田久保忠衛氏が外信部長で、大声で部下を叱咤しながら、猛烈な勢いで原稿をかきなぐっていた。そうした外信部の光景を見ながら、『広場の孤独』の一字一句を反芻していたのを記憶している。
ところで、『広場の孤独』は、一九五〇年に勃発した朝鮮戦争を背景に、複雑な政治的状況の中におかれた知識人の心の揺れ動きを描いた戦後文学の傑作ということになっているが、今日読み返すと、描かれた内容もさることながら、堀田善衛文学の核をなす独特の方法論が確立されたという点で形式の面でも最重要の作品であるということができる。
堀田善衛の方法論、それはひとことで言えば、「焦点なき収敏」ということになろうか。『広場の孤独』の中で、というよりも、堀田善衛のすべての作品の中でもっとも注目しなければならないのは、まちがいなく次の一節だろう。
世に任意の人物、臨時にちょっと雇ったといった人物というものは存在しない。みな特定の人物なのだ。だから任意の人物とは、全くの虚構である。これは普通の、生きた人間のあり方とは逆であるが、逆算することによって未知数のX、すなわち各人を特定の各人として他から別様に成立させている、予見不能の地域をはっきりさせる。そこを照射することに力を集中する。云いかえれば、颱風を颱風として成立させている、颱風の中心にある眼の虚無を、外側の現実の風を描くことによってはっきりさせるこうしておれの存在の中心にあるらしい虚点を現実のなかにひき出してみれば、おれは生身の存在たるおれを一層正確に見極めうるのではないか。予見不能の地域、颱風の眼、それは人間にあっては魂と呼ばれるものではないか。もしそれが死んでいるならば、呼びかえさねばならぬ。この〈小説〉の題名は、そうだ、ひとまずStranger in Town これを意訳して、広場の孤独、とする。
これは、『失われた時を求めて』のプチット・マドレーヌの挿話に等しい、小説の方法論のマニフェストだが、同時に誤読されやすい一節である。つまり、通り一遍の読み方だと、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中世の戦乱、フランスの宗教戦争などといった乱世の中に投げ出された個人の内面を抽出するのに、時代状況やそれに翻弄される複数の人間を積分的に描き重ねていくだけのものと解釈されそうだが、それだと古めかしい社会主義的リアリズムになってしまう。堀田善衛の方法論は、じつはこれとはまったく異なる。というのも、堀田善衛においては、たしかに、時代状況は収斂するように構成されているのだが、その中心にあるのは、焦点ではなく、あくまで「虚点」なのである、というよりも、はじめから、収斂は、焦点をもたぬように、あるいは焦点というものを拒否する形で行われるように設定されている。堀田善衛は、よく、「私」とすべきところに「少年」「男」と置く。それは、「私」という形で焦点が結ばれてしまうのを拒もうとする方法論的潔癖さのあらわれである。ではなぜ、焦点を拒否するのか。同じく『広場の孤独』にこんな一文がある。
判断停止というよりも何よりも、木垣は、自分の思考乃至動揺の中心部に、ぽっかりと暗い穴、颱風の眼のようなものがあって、さまざまな相反する判断が敲ちあって生れる筈の思考の魚が、生れかけるや否や途端にその穴、その眼の中へ吸い込まれてゆくように思われた。もしその穴、その颱風の眼をそこだけ切り取って博物館に陳列するとしたら、それには、人間的、という符牒のような札がかけられるかもしれない。
すなわち、収斂されて焦点が結ばれるとしたら、それは「小説的」ではあっても、「人間的」ではなくなる。「人間的」でありつづけようとすれば、いくら収敵がおこなわれても、永遠に「虚点」でありつづけるような「颱風の眼」を必要とする。
しかしながら、これは、口でいうのは簡単だが、小説においては、危うい均衡を必要とする、とてつもなく難しいポジションである。
『若き日の詩人たちの肖像』はこうしたポジションを最後まで保ちえた傑作だが、『橋上幻像』は、時代の状況に流されたのか、「虚点」でありつづけようとする本来の姿勢が失われ、あと一歩のところで、「焦点」が結ばれかけている。
おそらく、堀田善衛自身もそれに気づいていたにちがいない。一九七三年から始まる『ゴヤ』の連作は、そうした方法論的危機を乗り越えようとして模索した末に生まれた独特の視点に立っている。といっても、それは「収斂の虚点」として、「男」の代わりにゴヤを置いただけではない。また安易に「男」とゴヤが二重映しにされているわけでもない。『ゴヤ』連作においては、いうなれば、語り手とゴヤという形で「虚点」が二つ設定され、それらが巧みにリンクされているのである。そして、このダブル・フォーカスならぬ、ダブルの「虚点」によって、収敏が輻輳的に行われている。『ゴヤ』連作が、たんなる評伝におわらず、まぎれもない堀田善衛の「作品」となりえたのはそのためである。
現在、『すばる』に連載中の『ミシェル城館の人』は、モンテーニュという、フランス文学の生んだ最高の「虚点」を題材に得て、まさに堀田善衛のライフ・ワークというにふさわしい仕上がりをみせている。カンボジアの虐殺や連合赤軍事件で言葉を失いかけた世代の人間として、堀田善衛が、この宗教戦争の時代をどのように収斂させていくか興味はつきない。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする