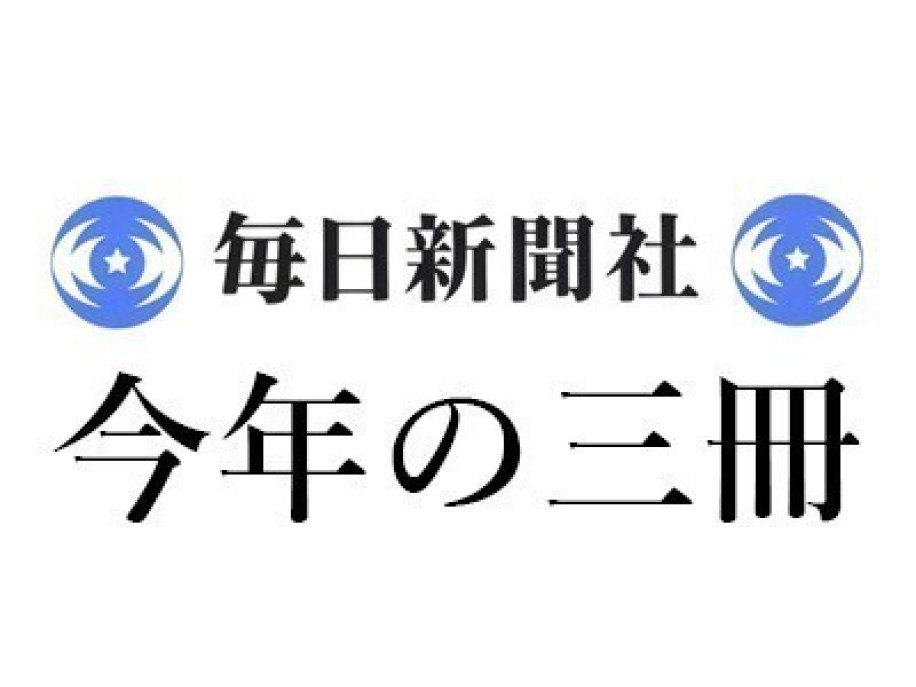書評
『婦系図』(新潮社)
「俺を棄てる歟(か)、婦(おんな)を棄てる歟(か)」。”封建的師弟関係”の精華
1899(明治32)年、硯友社(硯友社)の新年会で25歳の泉鏡花は、神楽坂の芸妓桃太郎こと17歳の伊藤すずを知った。1903年、友人が工面してくれた金で鏡花はすずを身請(みう)けし、神楽坂下の借家に同棲した。しかし6歳年長の師・尾崎紅葉は、芸妓を落籍(ひか)すなど身のほどを知らぬ、それで身が立つなら立ててみろ、「俺を棄てる歟、婦をすてる歟」と江戸前のたんかで叱責した。「婦を棄てます」と泣いて誓った鏡花はいったんすずを離別したが、半年後、紅葉が35歳の若さで病没すると今度は正式に妻として迎え、生涯をともにすごした。
東京朝日新聞に入社した漱石が近代的職業作家として出発した1907年、鏡花は『婦系図』という古典的小説を書き、この事件を自分の内部で歴史に転換した。
内容解説
時は明治。有名な大学教授・酒井の下で修行する文学士・早瀬主税(ちから)が密かに所帯を持っていたのは、芸者あがりのお蔦であった。ところが酒井の愛娘に縁談が持ち上がり、お蔦との関係を師に責められた主税は別離を決意、お蔦は泣く泣く身を引いた。これが後に舞台で満場の紅涙を絞った「湯島の白梅」の名場面である。純愛の難しかった時代の、お蔦を始め女性たちの健気な愛が胸を打つ。【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする