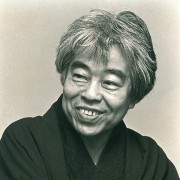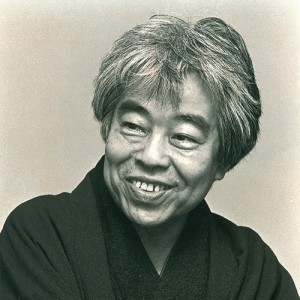書評
『切腹論考』(作品社)
意外史を軸としたエッセー集
これは「信長殺し、光秀ではない」「信長殺しは、秀吉か」「謀殺・続信長殺し、光秀ではない」など、一連の異色作で知られている八切止夫の、意外史を軸としたエッセー集である。タイトルになっている「切腹論考」をはじめ、捕物、やくざ、演歌、遊女、呪術、忍術など計十二編の時代考証批判をあつめ、全体を通して、これまでのチャンバラものに対するイメージの百八十度転換を策した、おもしろい書物だ。八切止夫は自分が生きていたという実存のあかしになる本だとまで自画自賛しているが、その自分のための広告が、読み進んでゆくと決して誇張でないことに気づく。つまり一般の通念などというものは、きわめて眉ツバもので、常識的に考えれば通用しない説であることが、彼の縦横なメスによって切裂かれているからだ。
たとえば、どう刀を腹に突きたてたところで、致命傷にはならないハラキリ行為を、武士道精神のシンボルのようにいうのはなぜかと疑問を提起し、「即死ではなく緩慢な死への道程に身を処して、そこで憤りと口惜しさとをぶちまけ、こんなザマに誰がしたかと抗議するのが、切腹それ自体の本来の姿でなくてなんであろう」とナゾ解きをする。元禄十六年から慶応三年までのおよそ二百年の間に、代々の首斬り浅右衛門が切腹の介錯をしたのはわずかに二十人、しかもその半数は安政の大獄で逮捕された志士たちだったという。非公式な数はともかく、江戸伝馬町牢内だけの限られたデータではあるが、それでも十年に一人の割合では、切腹の数が少なすぎる。にもかかわらず、あれほどまでにハラキリが世に知られるようになったのは、刑場の取締りにあたった弾左衛門一家が、芝居興行を一切とりしきっており、本職が演技指導をするとでも錯覚して、芝居の舞台をそのままハラキリ作法だと、うのみにしたためではないか、と八切説は意外な方向へそれてゆくのだが、それはそれで、飛躍のおもしろみが加わり、首をかしげながらもいつか八切意外史のとりこになってゆくからおもしろい。
また「捕物論考」のくだりでは、チャンバラ小説や映画、あるいはテレビで、捕物の場面となると、いずれも召捕る側がバッタバッタと斬られるのに反して、追われるものが抜身の大刀をふりかざして大活躍をしている。本来ならば、国家権力の走狗である捕方の武器の方がすぐれているはずなのに、十手やさす叉(また)などで召捕ることができたのであろうか、といったきわめて常識的な疑問からはじめ、何事によらず、鞘ばしればお家は断絶、その身は切腹といった帯刀者全部への掟にふれ、召捕られるものが鞘のまま刀をふりまわすのにたいして、無理にでも鯉口をきらせ、刀身を露出させて罪に落すために十手を用い、抜刀術も考案されたと説く。
その論理の運びかたにはかなりな飛躍があるが、歴史的なセンサクはともかく、大衆読者にとっては、その飛躍が興味をひく。おまけに自由に強用される史書に幻惑されて、なんとなく意外史発掘の網の目にふみこんでしまう。
著者にいわせると、ハラキリは「八ら切り」つまり八切となって、筆名の由来ともなるわけらしいが、文中の随所に出てくる被圧迫民衆としての日本原住民の系譜は、八切日本史として別にまとめてもらいたい問題である。
ALL REVIEWSをフォローする