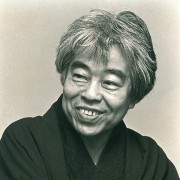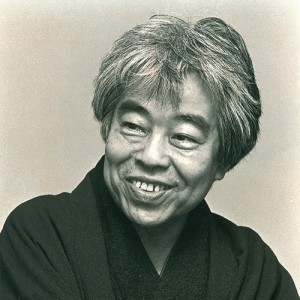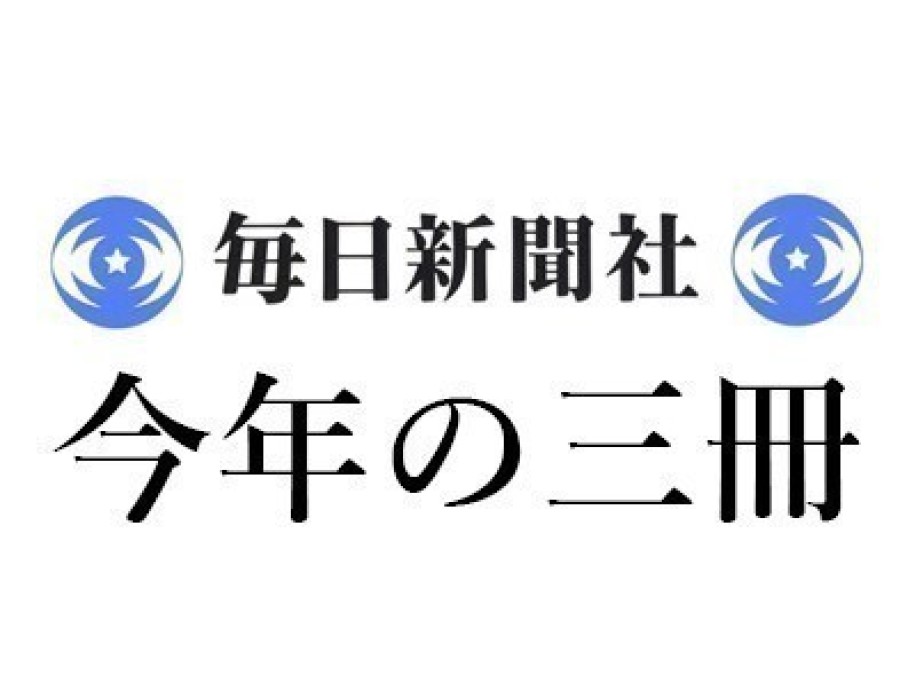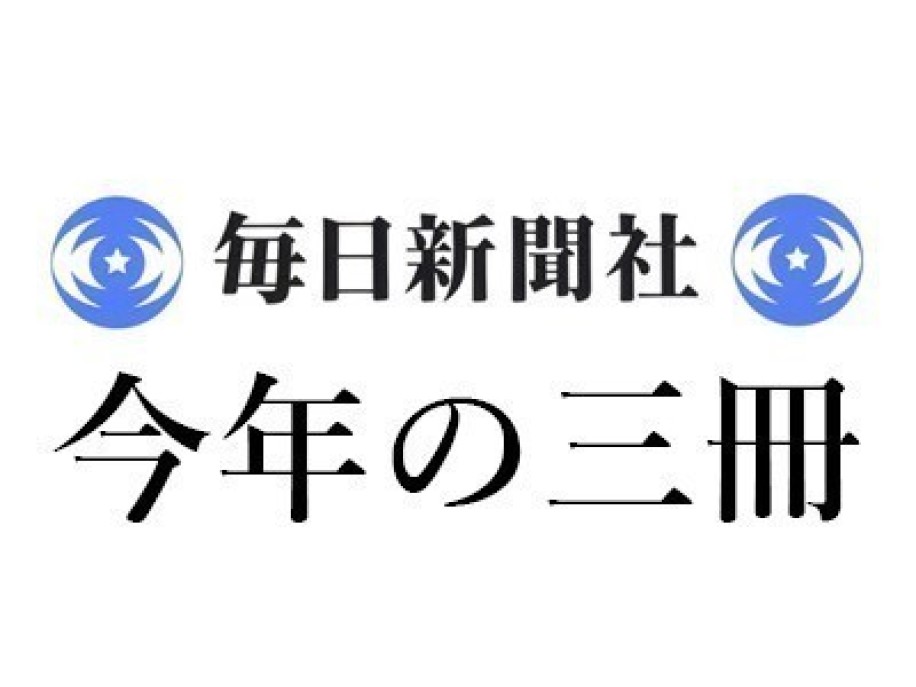書評
『小説GHQ』(集英社)
多角的に描かれる占領下日本
梶山季之が亡くなって一年近くたつ。一周忌を前に刊行された「小説GHQ」は、昭和三十九年から翌年へかけて「週刊朝日」に連載され、単行本にならないままでおかれていた長編である。失敗作ならともかく、丹念な取材と作者なりの野心的な構図をもって取り組んだ作品だけに、刊行が見送られてきたのは、おそらく納得ゆくまで筆を加えるつもりだったからではないだろうか。
「小説GHQ」は千葉県下のある村に駐屯していた一中隊が、敗戦を迎える場面からはじまり、米軍の厚木進駐につづくさまざまな占領政策の実施、それをおしつけられる日本側の反応、とくに財閥解体をめぐる動きなどがたどられるとともに、食糧難に苦しむ日本民衆の姿や、その混乱の中でたくみにのしあがってゆく男の生きかた、あるいはGHQ内部の意見の対立やそれにからむ異動、さらに占領軍の腐敗にまでメスを入れ、これら戦後日本の社会における多くの問題を多角的にとりあげた、スケールの大きな作品だ。
登場人物も多岐にわたるが、なかでも興味ぶかいのは姫野兵長だ。貧農出身の姫野は軍隊時代にも要領のよさで有名だったが、敗戦のどさくさに軍の物資を手に入れて闇でさばき、ときには進駐軍の権威を利用して儲けながら、次第に成り上がってゆく。その動物的なたくましさは、「赤いダイヤ」の木塚慶太などとも共通するものだ。
姫野の中隊長だった綾小路冬彦は華族の息子で、三井系の軍需会社の社長をしていた父の秀樹は、元外交官のキャリアを生かして財閥解体指令の対策にあたり、後には終戦連絡事務局の次長に就任する。冬彦は綾小路家としたしい子爵夫人の島田春代に誘惑され、一時愛欲に溺れるが、やがて姫野の事業に協力するようになる。
また一高生の田丸小弥太は三菱に縁故ある人物の妾腹の子で、父への反抗からニヒルな生活を送っていたが、新宿の闇市で姫野と知りあい、その参謀役をひきうける。そして春代はその美貌を武器に米軍関係者の間をたくみに泳ぎ、新しい時代に対応してゆくのだ。
一方占領軍の側では、広島に妹のいる二世のトム・塚田中尉や、ニューヨーク・タイムスの記者ロバートソンが前述の人々と交渉をもち、塚田中尉の場合は二世という立場からみた日本の状況や、占領軍のありかたについての悩みにもふれている。
こうして昭和二十一年秋ころまでの占領下日本の様相が、GHQの動きを中心にたどられるが、あまりに構想が大きすぎたためか、主題が完結しないままに終わっている観がある。しかしこれだけでも、山口瞳が解説で指摘しているように、「黒の試走車」「赤いダイヤ」と並ぶ梶山季之の代表的な経済小説といえるもので、アメリカの占領が歴史的な検討を加えられつつある現在、多くの問題を投げかけている。
ALL REVIEWSをフォローする