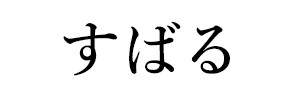書評
『ほんとうの私』(集英社)
あたらしい更年期小説
主人公は、法的に結びついてはいない熟年の男女である。女性には離婚歴があり、前夫とのあいだにもうけた男の子を五歳で亡くしている。愛息の死を契機に、彼女は夫と別れる決意を固め、仕事に復帰して収入を確保すると、新しく出会った男と暮らし始める。自由を見出した彼女に、しかしほどなく大きな危機が訪れる。「生理的な路程の終わり」にさしかかって、自分をとりまくいっさいの要素が崩れ、揺らぎだすような、精神的、肉体的変調に見舞われるのだ。彼女自身、当初はこの説明しがたい微妙な変化をきちんと理解できてはいなかった。老化への無意識の怯えを残酷に暴いたのは、なかば冗談のつもりで口にした、「男たちはもうけっしてあたしを振り返ってくれない」という言葉だった。異変を察知した男は、すぐ近くから彼女を見守っている匿名の人物になりすまし、恋文めいた手紙を送る。これが予期せぬ反応を引き出すあたりから、物語は十七世紀のフランス心理小説にも似た繊細な振幅を獲得していく。クンデラは手品師のようにカードを左右均等に配布し、得意のアフォリズムを随所にちりばめながら、両者の心の動きを追う。
「ほんとうの私」とは、だから年齢的な峠の見えた女性の内奥ばかりでなく、そういう女性と暮らしを共にしている男の立場をも包み込む表現なのだ。じじつ男は、相手より年下で、収入も低いという現実を、「彼女に必要なのは愛の眼差しではなくて、共感もなく、選択もなく、優しさも礼儀もなく、宿命的に、避けがたく注がれる、見知らぬ、粗野な、貪欲な眼差しの氾濫なのだ。そのような眼差しこそ彼女を人間社会に引き留めるのにたいし、愛の眼差しのほうはそこから彼女を引き離すのだ」と独りごちて、力弱い理性で乗り越えようとする。
けれども彼らが迷い込んだ袋小路に、とつぜん退路を示すのは、たがいの頭をよぎる乱交パーティーの妄想にからめた、語り手の操作だった。精緻なパズルが最後の最後で夢に押し戻される仕掛けは、クンデラの独壇場といってもいいだろう。だが注目すべきは、政治的背景をいっさい抜きにした日常の表層に潜むロマンスを、彼が苦もなく描き切っていることの方だ。いかなる留保も粉飾もない裸形の感情をつむぐ、大いなる「通俗」作家としての力量と可能性を、彼はこの一作であらためて示しえたのである。
本書は著者の意向に従い、原版に先駆けて刊行された掛け値なしの最新作である(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1998年)。クンデラの母国語ではない、仏語による小説が、日本語を通して最初に書物の形をなす。それだけでもう、じゅうぶん刺激的なことだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする