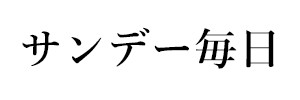書評
『存在の耐えられない軽さ』(集英社)
小説の堪えられない旨さ
東欧社会主義圏のひとつチェコで束の間実現した自由主義体制、いわゆる「プラハの春」と呼ぼれた一時期のこと、当のプラハで妻子と別れてこれも自由を取り戻した医師のトマーシュは、女漁りの日々を過ごしていたが、ある日、無垢な田舎娘テレザと出会う。女たらしの彼がぼんやり窓から庭のむこうの壁を眺めていて、はっとなってテレザとの恋に落ちる。ミラン・クンデラの傑作小説『存在の耐えられない軽さ』の出だしはこんなふうだ。しかし、トマーシュには画家で聡明なサビナという愛人もいた。テレザとサビナは友情と嫉妬でつながれる。テレザは写真を学び、駆け出しのカメラマンとして活動し始めるが、サビナと互いのヌードを写真に撮り合ったりする。と突如、ソ連軍がチェコに侵攻して、「プラハの春」はあっけなく終わる。
トマーシュとテレザはチューリッヒへ逃げ、そこで医師としての生活も安定したかとみえたが、トマーシュはジュネーブに逃れていたサビナと逢引きする。テレザは絶望してプラハへ去る。トマーシュは、もう二度とチェコから出られないと分かっていながらテレザを追ってプラハに戻る。二人の苦難の人生が始まる。ソ連軍に占領され、警察国家に逆戻りした権力がたえず無力な二人の生活に介入して、トマーシュは窓拭きにまで落ちぶれる。やがて二人はプラハを出て田舎に逃れ、トマーシュは農場のトラック運転手、テレザは牛追いの仕事につく。トマーシュは年を取った。テレザはやっと彼を自分のものにし、トマーシュは諦念とテレザの愛にやすらぎを見出す。
いっぽうサビナはジュネーブで妻子ある有能な大学教授フランツに愛される。しかしフランツがサビナとの関係を妻に打ち明けたとき、サビナはさらに自由を求めてパリへと去る。パリで暮らして三年目、トマーシュの先妻の息子からトマーシュとテレザの死を知らされる。
フランツはサビナが忘れられず、冒険を求めて内戦のカンボジアに出かけ、バンコクで強盗に殺される。サビナはさらに自由を求めてアメリカへ。
粗筋は以上。トマーシュ、テレザ、サビナ、フランツの四人が絡みあった人生のドラマはこれで終わりで、この程度の物語なら特筆するほどのことはないかもしれない。しかし、じつはこの小説はここまでで物語の七分の三にすぎず、残りはまだたっぷりある。トマーシュとテレザの死が告げられたあと、再び彼らの物語が、それまで明かされなかったドラマが展開するのだ。父を慕ってトマーシュの息子シモンが登場したり、癌にかかった愛犬カレーニンを安楽死させなければならなかったり、逃亡の果ての日々の暮らしが胸を打つ精彩さで奏でられる。
読者は既に、いつ、どこで二人が死んだかを知っているわけだから、彼らの死の近いことをたえず意識させられながら読み進むことになる。
そして、親切な農場長と、トマーシュが怪我を治してやった青年の四人で久しぶりにポンコツ・トラックに乗って隣町までダンスに出かけ、「ピアノとバイオリンの音に合わせ、テレザは頭をトマーシュの肩にのせ、ダンスのステップを踏んでいた」という幸福の場面で小説の幕は閉じられる。トマーシュとテレザにこのあとトラックの転落死が待っているのだが、その場面は描かれない。
クンデラの小説技法の新しさを云々されることが多いが、それはあまり大したことではないと思う。デュマの『三銃士』が面白いように、クンデラの小説にも、堪えられない旨さがある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする



![存在の耐えられない軽さ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/511nhFF0qJL.jpg)