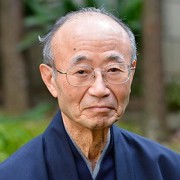書評
『江戸時代とはなにか―日本史上の近世と近代』(岩波書店)
日本史二分した「役」の体系
江戸時代を、日本史の枠組みだけでなく、世界史的展望のなかで浮かびあがらせた、胸のすくような作品だ。今日いわゆる江戸時代論が花盛りである。レトロ趣味、ポスト・モダン論、江戸・東京論とあげていけばきりもないが、そのほとんどがこの作品の登場によって顔色を失い、生気を剥奪(はくだつ)されるのではないか。
著者による設問の眼目は、ただ一つ、二百七十年に及んだ江戸時代の平和の原因は何であったのかという点にある。かたい言葉でいえば、十四、五世紀の社会変動と、その結果としての近世国家の形成がその後の日本の運命を決した。この「近世」は日本の全史を大きく二分する画期の出発点をなし、明治維新をつらぬいて今日の象徴天皇制国家にいたる政治・社会的背骨をつくったのだという。しかも、ここが大切なところなのだが、その国家形成において外来文明の影響はむしろ微弱であって、内発的に自生した社会発展の活力と創意にこそ目をむけるべきだと主張する。
なぜ、それが可能となったのか。その根本が近世に発達した「役(やく)」の体系すなわち職分の観念、およびそれにもとづく政治、社会制度の成立であった。武士も百姓も町人もひとしなみに自己の社会的役割の有用性を自覚し、これを共同体や国家と調和させることに意を用いた。それだけではない。天皇も幕府もまた、このような社会的職分の考えを分有し、そこに幕府権力や天皇権威をもこえる「公」または「公儀」の観念が成立することになったのだという。
なかでも圧巻なのは、巻末近く明治憲法に筆をすすめて天皇機関説論争に説き及んでいる部分である。この一種の天皇職分論は近世の「役」の体系の考えをうけついだものであり、その点にかんしては伊藤博文も美濃部達吉も何ら異なるところはなかったという驚くべき結論を、折り目ただしく、沈着冷静な論理にもとづいて明らかにしている。
ALL REVIEWSをフォローする