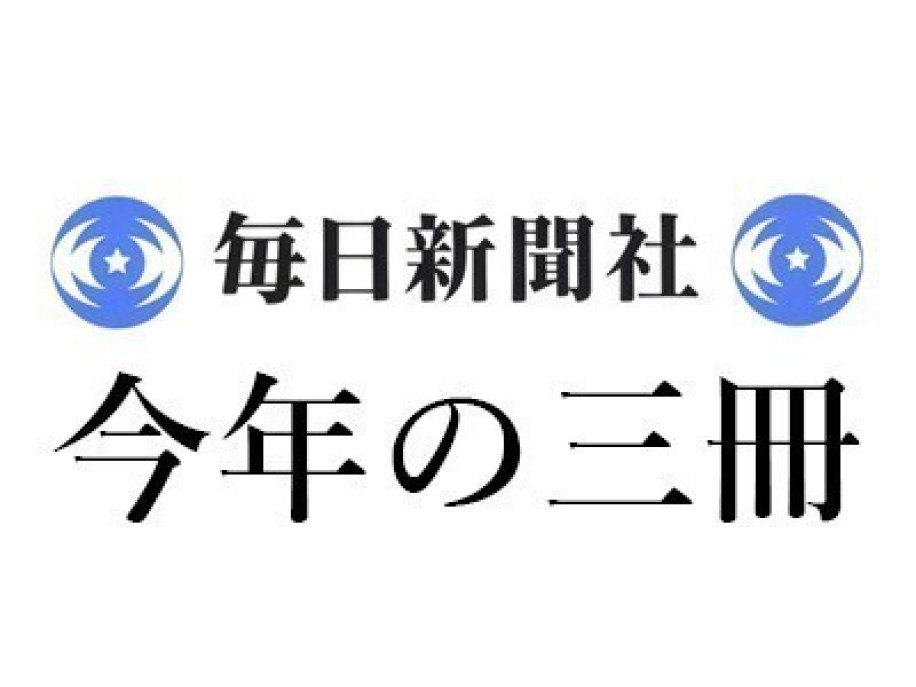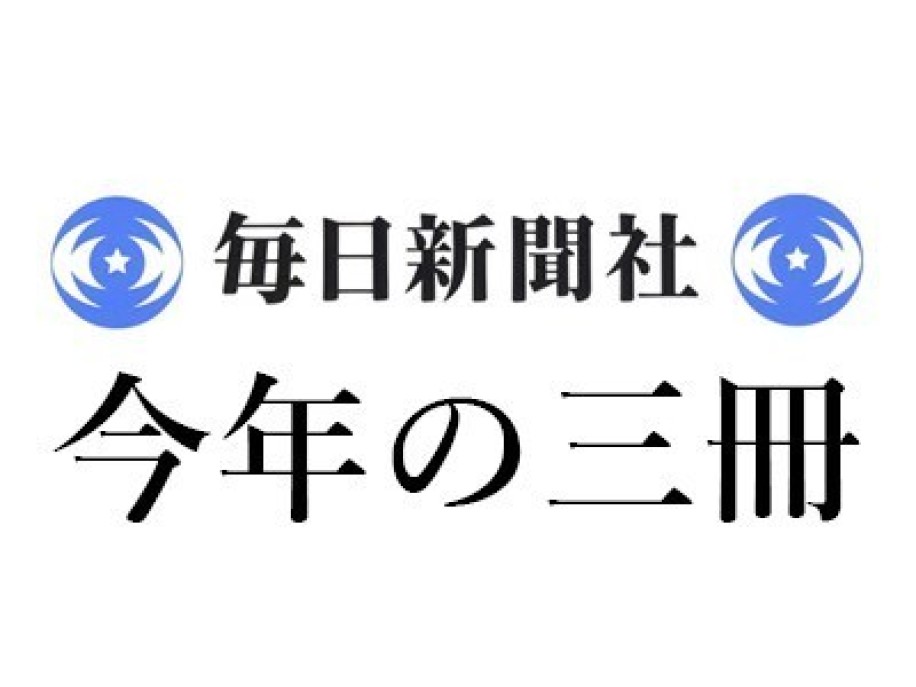書評
『沈むフランシス』(新潮社)
あらためて証明した力量
編集者から小説家に転じ、デビュー作の長編「火山のふもとで」で読売文学賞を受賞した著者の2作目。東京での生活と、13年間つとめた仕事に区切りをつけた桂子という女性が、中学時代を過ごした北海道東部地方に戻ってくる。かつて住んだ町にほどちかい、人口800人ほどの村で、非正規雇用の郵便配達員の職を見つけたのだ。
村の暮らしにも慣れたころ、桂子は配達先の一人の男と知り合う。男は自然音や生活音を収集し、高音質の機器で再生するという趣味をもっていた。男からの性的な誘いを桂子はあっさりと受け入れ、二人は定期的に会うようになる。青年期を過ぎ、北国で新たな人生を模索する彼女は、まだ得体(えたい)のしれないところのある男に心ひかれていくが、噂(うわさ)はすぐに広まり、やがて桂子は男の不実を知らされる。
男は「フランシス」と名づけた水車のある小屋の近くで暮らしている。村の電力は水車がうみだすエネルギーによってまかなわれており、「フランシス」は男の暮らしだけでなく、この村全体の運命とも深く結びついている。この作品を深いところで駆動させているのは、この「フランシス」のもつ象徴性だ。
郵便配達員である桂子は、人びとのプライバシーを知りうると同時に、自らのプライバシーにも制約があるという、両義的な立場にいる。だが村のコミュニティーは桂子を断罪するどころか、その再生を静かに見守る。なかでも視力を失った老婦人は、まるで神話に登場する人物のように、啓示的な言葉により桂子の導き手となる。
北海道の架空の村を舞台にした、「大人のためのファンタジー」ともいえる本作は、長編というより中編というべき作品。端正ななかにも不気味さとエロティシズムを湛(たた)えた筆致で、力量をあらためて証明したこの作家の、次の本格的な長編にも期待したい。
初出メディア
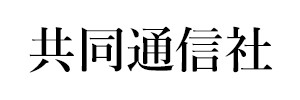
共同通信社 2013年11月7日
ALL REVIEWSをフォローする